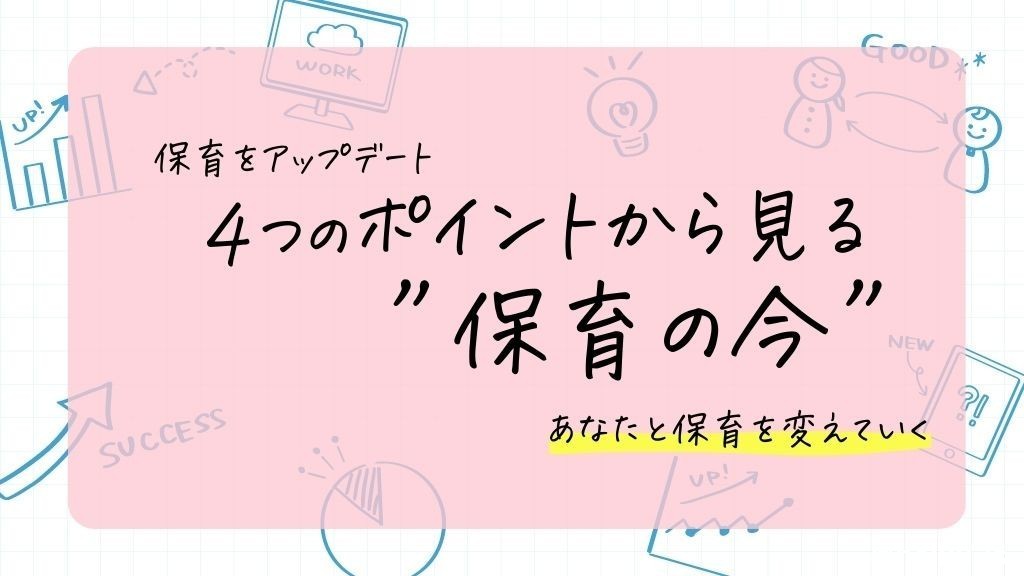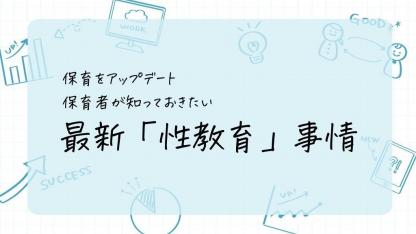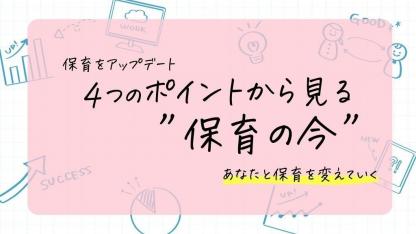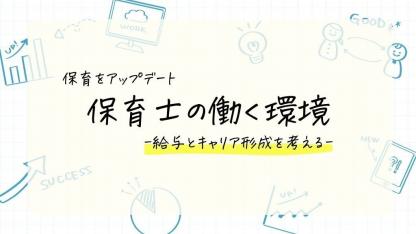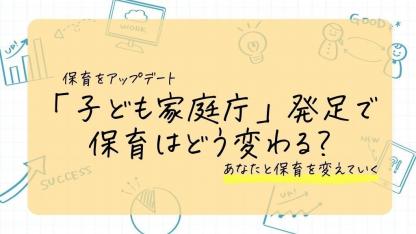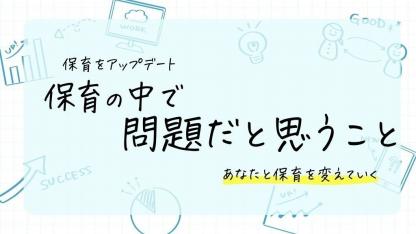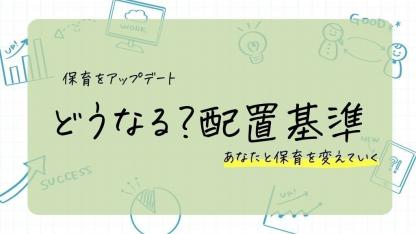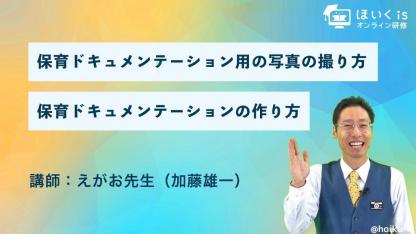保育所における保育とは

厚生労働省が発表している「保育所保育指針」によると”保育所における保育”とは、全ての子どもの最善の利益のため、保育所保育指針に基づきながら行われるものであり、「各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。」とあります。
つまり、園によって方針は違えど、全ての子どもの最善の利益のため、国が定めた原則・指針に基づいて機能と質を向上していく姿勢が求められています。
保育に求められるものが変化してきている
こういった原則のもと、今の保育に求められているものは、制度的にも、世の中的にも、預ける保護者的にも大きく変わってきています。徐々に変わるものもあれば、制度として大きく変わることもあり、アンテナを常に張っていないとその変化に気づかないこともあります。今回は変わりゆく「保育の今」をさまざまな角度からご紹介します。
「保育の今」を見るための4つの視点
ここからは、「保育の今」を捉えていくために必要なことを考えていきたいと思います。ほいくis編集部では、以下の4つの視点をピックアップしました。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。