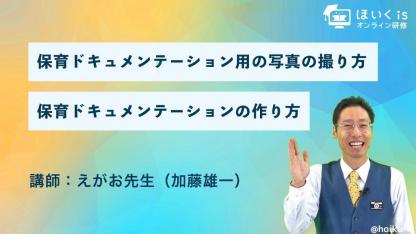言葉遣いはなぜ重要か?

社会人の観点
社会人とは、自立した大人のことです。給与を受け取る代わりに責任を持って仕事をする必要があるので、たとえ社会に出て一年目だとしても、世間からは大人としての対応を求められます。正しい言葉遣いで話し、目の前の相手に失礼のない対応をすることが社会人にとって大切な仕事の一つだと言えます。保育士の観点
保育士は保護者との信頼関係を築くために、言葉遣いに気をつける必要があります。1日のほとんどを子どもと過ごす保育士にとって、保護者とやりとりをするのは送迎時のわずかな時間だけ。言葉遣いや態度で保育者の印象が決まってしまいます。保護者が安心して子どもを預けられるよう、保育士は信頼を得られるような言葉遣いを意識する必要があります。
保護者対応で注意したい言葉遣い
「保護者と親しくなりたい」「相談しやすい雰囲気を作りたい」という思いから、意図的にくだけた話し方にする保育士さんもいることでしょう。園の雰囲気や地域性、保護者との関係性によって言葉遣いは変わってきます。そんな中でも、保育士として気をつけたい言葉遣いについてご紹介します。
若者言葉

若者言葉には、以下のような言葉が挙げられます。
| マジ/ヤバい/ガチ/超/ウケる/ダサい/エモい/バズる/オワコン など… |
友だち言葉
保護者と親しくなってくると、つい使ってしまいがちな「友だち言葉」にも気をつけましょう。友だち言葉には、先に挙げた若者言葉の他に以下のような言葉遣いが挙げられます。
| ・「〜だよね」「〜でしょ?」とくだけた語尾を使う ・「ねぇ」「ちょっと」などと呼びかける ・冗談を言ったり、軽薄な表現を使う ・保育士が自分のことを「うち」「俺」と言う |
子どもの呼び捨て
名前の呼び捨ては、子どもに対する親しみを感じる一方、不快に感じる保護者の方もいます。保育園で子どもの呼び方を統一して、保護者に周知しておくことも大切です。子どもたちのことは、「〇〇くん」「〇〇ちゃん」のように呼ぶと良いでしょう。中には園の方針で、性別に関わらず「〇〇さん」と統一して呼ぶところもあるので、初めて働く園の場合は最初に確認しておく必要があります。
上から目線の言葉
何気なく使ってしまいがちですが、「〇〇くんに、~してあげました」という言葉遣いは避けましょう。中には「上から目線だ」と感じる方も。保育士にとって子どもの支援は「してあげる」ものではなく「する」ものです。「~すると、嬉しそうに笑っていました」など、子どもの様子と合わせて丁寧に伝えると良いでしょう。
指示的な言葉

否定的な言葉の言い換え例
保護者との会話の中でつい言ってしまいがちな言葉の中には、意図せずネガティブな印象を与えてしまうものがあります。これらの言葉は、上手く言い換えることで印象ががらりと変わります。どのように言い換えできるか見てみましょう。「でも」「しかし」の言い換え

話を最後まで聞いたうえで、「実は…」と言い換えるとネガティブな印象が減りますね。また、その前に「そうですね」など、保護者の感じ方を受け止めるような言葉を加えると、さらに丁寧になりますよ。
「普通は」「一般的には」の言い換え
「普通はこの年齢だと〇〇ができますよ」などと、アドバイスの中でも言ってしまうことがあるかもしれません。しかし聞いた相手は、「できない自分の子どもが異常なの?」と感じてしまうことがあるので気を付けたいところです。なるべく使わないのが無難ですが、やむを得ない時には「こんなケースが多いです」と柔らかく言い換えて伝えると良いですよ。
「そんなはずないです」「違います」の言い換え

その場で反射的に返事をしようとせずに、「すぐに確認いたします」と、確実な返事ができるようにしましょう。
言葉遣いで気をつけたいポイント
言葉遣いを意識する上で、特に気をつけたいポイントについてご紹介します。電話対応はより丁寧に行う

後々トラブルに発展しないよう、電話で話す時は保育現場で話す時よりも気をつけて言葉を選びたいですね。
「ウチ」と「ソト」を使い分ける
敬語は「ウチ(内)」と「ソト(外)」を正しく使い分けることが重要です。上司は同じ職場の人なので「ウチ」の人になります。対して、保護者は「ソト」の人です。「ソト」の人と話をする際、「ウチ」の人に対して敬語は使用しません。
例えば「園長先生が〇〇とおっしゃってました」ではなく「園長が〇〇と申しておりました」となります。
この場合、敬語を外しても上司に対する無礼にはなりません。むしろ間違った使い方は保護者に対して失礼になってしまいます。
普段からの心がけ
丁寧な言葉遣いをするためには、普段からの心がけが重要です。どのようなことを意識したら良いのか、見てみましょう。正しい言葉遣いを習慣化する
正しい言葉遣いは一朝一夕で身につくものではありません。意識していたとしても、ふとした瞬間にいつも使っている言葉が出てきてしまうものです。せっかく築き上げた信頼関係が壊れないよう、普段から正しい言葉遣いを意識し、習慣化していきましょう。ポジティブな側面に目を向ける

自分を客観的に見る

保護者との信頼関係を築こう
保護者対応は適切な言葉遣いを意識して行いましょう。もちろん言葉だけでなく、保育士として「保護者を理解したい」「寄り添いたい」という思いも大切です。その上で傾聴や共感を大切にしながら保護者との信頼関係を築いていきたいですね。保護者対応で悩んでいる方は参考にしてみてください。
【関連記事】