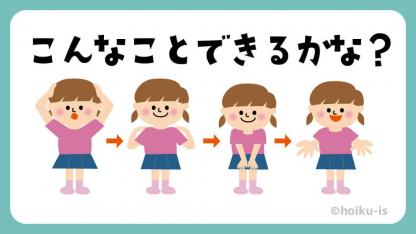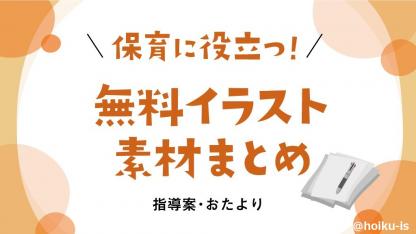保育のポイント【2歳児・5月】
2歳児クラスになると、この時期はだいぶ園の生活や流れにも慣れて、自分でできることが増えてきます。少しずつ、他児との関わり方や生活習慣の自立に向けたサポートをしていきましょう。例年、5月は暖かい気候の日が多いので、戸外で春の自然に触れる機会を持てると良いですね。また、「こどもの日」を始め、季節の行事や伝統的な風習について知る活動をしていってはいかがでしょうか。

ねらい【2歳児・5月】
- 基本的な生活習慣を身に着ける。
- 体操でのびのびと身体を動かし、健康に過ごす。
- 遊びを通して他児との関わりを増やしていく。
- 保育者や他児と一緒に見立て遊びを楽しむ。
- 草木などの自然物を使って遊びを楽しみ、新しい発見をする。
- 伝統的な文化に触れ、興味や関心を広げる。
- 自分が感じたことを言葉で表現する。
- 製作遊びやお絵描きを通して色の違いを知る。
内容/五領域対応【2歳児・5月】
- 食事前には手を洗ったり、着替えを自分でしたりと、自分でできることが増える。(健康)
- 「どうぶつたいそう1・2・3」をして、全身を使って遊ぶことを楽しむ。(健康)
- ままごとや簡単なゲームなどを通して、他児と触れ合ったり、会話をしたりしながら遊ぶ。(人間関係)
- 保育室にあるものを使ってごっこ遊びや見立て遊びをして、保育者や他児とイメージを共有し合う。(人間関係・環境)
- 園庭や公園で見つけた草木を食べ物に見立ててままごとに取り入れたり、色や感触、大きさなどを観察したりする。(環境)
- こどもの日に関する絵本を読んだり、外に飾られたこいのぼりを見たりして行事を楽しむ。(環境)
- 「これがいい」「ちがうよ」など、自分の感情を言葉を使って少しずつ表現しようとする。(言葉)
- クレヨンを使って塗り絵やお絵描きを楽しみ、好きな色を見つける。(表現・環境)
| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |
内容/養護【2歳児・5月】
- 自らトイレに行って排泄しようとする気持ちを大切にしながら、見守ったり手伝ったりする。
- 慣れてきた環境の中で心地よくのびのびと過ごせるような雰囲気づくりをする。
- 簡単な身の回りのことを自分でしようとする気持ちを受け止めながら、見守ったり手伝ったりする。
- 友だちや保育者と一緒に好きな遊びが楽しめるような環境を整える。
環境構成・保育者の配慮【2歳児・5月】
- 子どもが自分で身の回りのことができるよう、物の場所を、イラストを使って明記する。
- のびのびと身体を動かせるよう、体操を行うときは広い場所を確保する。
- 保育者が仲介しながら、子ども同士の関わりを増やしていく。
- 見立て遊びの幅が広がるようなおもちゃや廃材を用意して、子どもが好きなときに使えるようにする。
- 興味を持ったものに対する知識が深まるよう、図鑑を用意していつでも読めるようにする。
- こいのぼりが見られる道を散歩コースに取り入れる。
- 子どもが何かを伝えようとしているときはゆっくりと向き合いながら、安心して表現できる環境を作る。
- 子どもが自分で好きな色を選んで製作を楽しめるように、クレヨンや画用紙をたくさん用意しておく。
予測される子どもの姿【2歳児・5月】
- 身の回りのことを自分の力で行おうとし、保育者の手伝いを拒むことがある。
- 大きく身体を動かして、音に合わせた動きを楽しむ。
- 子ども同士で会話をしながら、同じ遊びを楽しむ。
- 保育者や保護者など身近な人の真似をして、ごっこ遊びをする。
- 園庭や公園で見つけた草木に触れて、色や感触の違いを保育者や他児と共有する。
- 散歩の途中で見つけたこいのぼりに興味を示し、保育者に「あれはなに?」と質問したり、知りたがったりする。
- うまく言葉が出なかったり、伝えられなかったりして泣いたり怒ったりすることがある。
- 色へのこだわりを持ち、好きな色のクレヨンを繰り返し使いたがる。
前月の子どもの姿【2歳児・5月】
- 進級後すぐに新しい環境や保育者に慣れ、2歳児クラスでの生活を楽しむ様子が見られた。他児との関わりも増え、友だちと遊ぶことを好む様子がうかがえた。
- 自然に興味を持ち、虫を探したり草花を集めたり、実際に触れながら楽しんでいるようだった。
職員間の連携【2歳児・5月】
- 一人ひとりの好きな遊びや行動範囲を共通理解し、柔軟に対応していく。
- 戸外遊びでは子どもから目を離さず、常に複数人の保育士で見守ることができる体制をとれるよう話し合っておく。
家庭や地域との連携【2歳児・5月】
- 暖かい日が増えて汗をかくので、着替えを多めに用意してもらう。
- さまざまな遊びが展開されている様子を、保育ドキュメンテーションを掲示して伝える。
健康や安全【2歳児・5月】
- トイレや外遊びの後、食事の前など、手洗いが必要な場面を話して一緒に実践していく。
- 子ども自身で身を守る意識を持てるよう、交通マナーについての話をする。
食育【2歳児・5月】
- 個々の状況に合わせて、スプーンの持ち方を下手持ちや3点持ちに移行する。
- さまざまな食材に興味が湧くよう、食事の前にその日の献立について話をする。
長時間保育の配慮【2歳児・5月】
- 保護者への連絡事項や一日の様子を担当の保育士に伝え、共通理解しておく。
- 保育士から話しかけたり一緒に遊んだり積極的に関わりながら、長時間保育に慣れていけるようにする。
今月の行事【2歳児・5月】
- こどもの日
- 身体測定
- 避難訓練
- お誕生日会
- 保護者会(全体懇談会)
今月の遊び【2歳児・5月】
生活リズムを安定させていく中で、保育者と一緒に身体を動かす遊びがおすすめです。- ハイハイレース
- バルーンマット
- こんなことできるかな?
- しっぽとり
- バスにのって
今月の歌・手遊び歌・体操【2歳児・5月】
5月の歌
- ちょうちょ
- てをたたきましょう
- もりのくまさん
- ぶんぶんぶん
5月の手遊び歌
- コロコロたまご
- つくしんぼ
- ミックスジュース
- わにのかぞく
5月の体操・ダンス
- どうぶつたいそう1・2・3
- ちょんまげマント
- すすめ!だんごむし
今月のおすすめ絵本【2歳児・5月】
- はらぺこあおむし
- もこもこもこ
- くっついた
- くだもの
自己評価【2歳児・5月】
少しずつ慣れ始めた新しい環境での生活も、5月は大型連休を挟んで逆戻り…ということがあったのではないでしょうか。焦らず、ゆっくりと慣れていけるようなサポートや見守りができたかどうかを考えてみましょう。新入園児はまず信頼関係を築くことが第一歩。一人ひとりと密に関わり、少しずつ生活リズムを整えていく環境設定をしていきましょう。
2024年度版フォーマットのダウンロード【2歳児・5月】
ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけ印刷して使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。
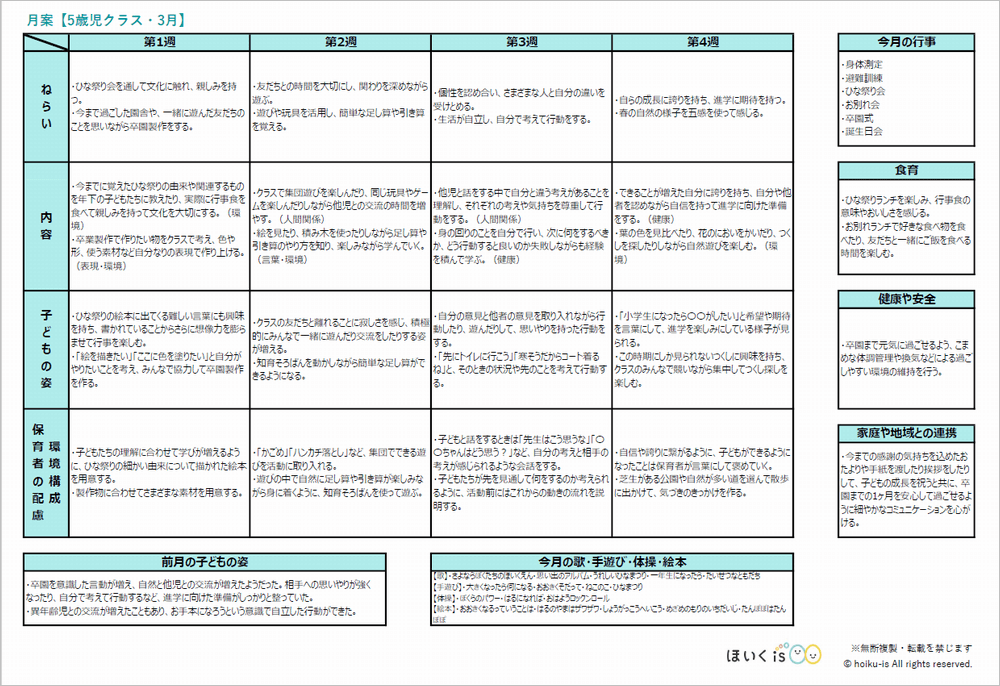
PDF版の月案文例【2歳児・5月】

自分の言葉で作る意識を
参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】