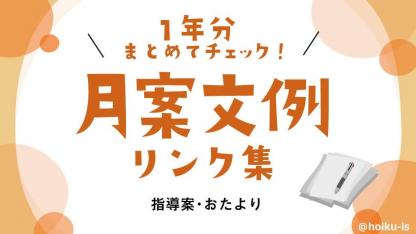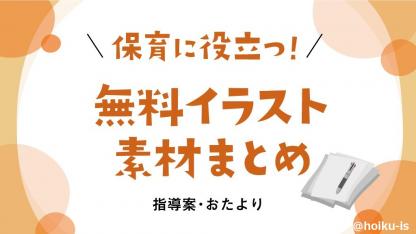保育のポイント【2歳児・6月】
基本的な生活習慣が身に着いてくる2歳児クラス。ボタン留めや衣類の着脱など、自分の力でできるようになっていくと良いですね。そのためにも指先を使った遊びがおすすめです。紐通しやクリップ遊びなど、子どもたちの興味に合わせて取り入れると良いでしょう。またトイレトレーニングを進めている園も多いのではないでしょうか。子どもたち一人ひとりのペースに合わせて、焦らずに成功回数を増やしていけるようサポートしていきましょう。

ねらい【2歳児・6月】
- 保育者のサポートを受けながら、自分で衣類の着脱をする。
- トイレでの排せつが身につき、成功が増える。
- 他児との関わりが増え、一緒に遊ぶことを楽しむ。
- 相手の話を聞き、理解しようとする。
- 季節の移り変わりに気付く。
- 虫などの生き物を大切に扱う。
- 自分の気持ちを言葉で主張する。
- 五感を使った遊びを楽しむ。
内容/五領域対応【2歳児・6月】
- 保育者に衣類の正しい向きを教えてもらいながら、自分でボタンを留めたり腕を通したりして着脱をする。(健康)
- トイレに行くタイミングが分かり、自分から「おしっこ出る」と保育者に伝える。(健康)
- 「お店屋さんごっこ」「電車ごっこ」などテーマを決め、他児とイメージを共有しながら同じ遊びを楽しむ。(人間関係)
- 保育者や他児の話を聞いて反応したり、自分の気持ちを伝えたりする。(人間関係・言葉)
- 梅雨に入り雨が増えたことや、気温があがり始めたことに気付き、「あったかいね」「雨だね」と季節の変化を言葉にして表現する。(環境・言葉・表現)
- アリやダンゴムシを見つけると、「踏まないようにね」「虫さんご飯食べてるね」など、生き物の命を認識して大切に扱う。(環境)
- 自分でできることが増えたことで自立心が芽生え、周囲の手伝いに対して「自分でやる」など言葉で拒みながら自己主張をする。(言葉・健康)
- 泥遊びを通して、水の量や砂の種類で異なる感触に気付き、自分で調整したり選んだりして遊ぶ。(表現・環境)
| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |
内容/養護【2歳児・6月】
- 暑い日の戸外活動で消耗した体力が回復できるよう、安心して午睡ができる環境を整える。
- 自分で着替えたり食具を使って食べようとしたりするなど、身の回りのことをしようとする子の気持ちを受け止めながら、必要に応じて手伝う。
- 安心して自分の気持ちを表現できるような声かけやかかわりをする。
- 自らトイレに行って排泄しようとする気持ちを大切にしながら見守り、必要に応じて手伝う。
環境構成・保育者の配慮【2歳児・6月】
- パンツやズボンなどは子どもが着脱しやすいように並べ、その先は自分でできる環境を作る。
- 個々のタイミングに合わせてトイレに行ったり、失敗を重ねたりすることで排せつの感覚を掴めるように保育者は無理にトイレに連れていかないようにする。
- 子どもたちの興味に合わせてごっこ遊びに必要な素材や玩具を用意する。
- 自分の話を聞いてもらうことを通して相手の話を聞く大切さが感じられるように、保育者は子どもの話に耳を傾け向き合う姿勢をとる。
- 散歩の際は、自然の変化が見られるコースを選んだり、季節に関する話をしたりして子ども自身の気付きのきっかけを作る。
- 生き物や植物を乱暴な扱いをした際は、叱るのではなく自分に置き換えて気持ちを考えられるような声かけをする。
- 子どもが安心して自分の気持ちを表現できるように、保育者は相槌や声かけで受け止める。
- 他クラスにも協力してもらい「泥遊びの日」を作り、園庭の砂場に水を入れて泥に触れられる環境を作る。
予測される子どもの姿【2歳児・6月】
- うまく着替えができずに保育者に助けを求める姿が見られる一方で、自分でやりたい気持ちも強く、時間をかけて取り組もうとする。
- 最初はトイレを嫌がり失敗する様子もあるが、少しずつ感覚を掴んで自らトイレに行きたがるようになる。
- 身近な保育者や保護者、お店などの様子を模倣してごっこ遊びを楽しむ。
- 「〇〇くんはこれがいいの?」「嫌だった?」など相手の気持ちを考えて聞き返す姿が見られるようになる。
- 葉の色や花の様子、天気の変化に気付いて「葉っぱが緑だね」「今日は空が黒いね」など表現する。
- 生き物を見つけると踏んだり潰したりしようとする姿が見られるが、子ども同士で「かわいそうだよ」「やさしくね」などの声かけが見られる。
- うまく自分の気持ちが伝わらないときは泣くこともあるが、ゆっくりと言葉で伝えようとすることも増える。
- 普段とは違った砂の感触に驚きながらも、夢中になって泥遊びを楽しむ。
前月の子どもの姿【2歳児・6月】
- 少しずつ生活習慣が身に着いて自立しようとする姿が増えた。保育者の手伝いを拒んだり、自分で最後までやり遂げようとしたりすることも多く、頼もしい様子だった。
- 自己主張が増える中で、子ども同士でのトラブルが多かった。噛みつきやひっかきなども見られ、不安定な子もいた。
家庭や地域との連携【2歳児・6月】
- 泥遊びを行うことを知らせ、着替えの準備をお願いする。
- 保護者面談のお知らせを配布する。
健康や安全【2歳児・6月】
- 日々の検温や便チェックなどをしっかり行い、体調の変化に気をつける。
- 気温が上がるとともに、湿気が多い日が増えるため、室内の湿度調整や換気、除菌を徹底して清潔を保つ。
食育【2歳児・6月】
- 他児や保育者と「おいしいね」「甘いね」などと言葉を交わしながら食事の時間を楽しむ。
- さまざまな食材に興味が湧くよう、「どんな味がするかな?」「何が入っている?」と話をしながら食事を進める。
今月の行事【2歳児・6月】
- 身体測定
- 避難訓練
- お誕生日会
- 歯科健診
今月の遊び【2歳児・6月】
梅雨の時期となりますが、室内でも体操などを取り入れて適度に身体を動かせる遊びをするのがおすすめです。- おちたおちた
- かみなりゲーム
- 階段マット滑り台
- しっぽとり
- ぐるぐる洗濯機
- うえから したから
今月の歌・手遊び歌・体操【2歳児・6月】
6月の歌
- だからあめふり
- しあわせならてをたたこう
- かたつむり
- ながぐつマーチ
- 歯を磨きましょう
6月の手遊び歌
- バスにのって
- グーチョキパー
- かみなりどん
- おべんとバス
6月の体操
- 月夜のポンチャラリン
- アンパンマン音頭
- かえるのみどりちゃん
今月のおすすめ絵本【2歳児・6月】
- ぞうくんのあめふりさんぽ
- はっぱのおうち
- あめふりさんぽ
- おさんぽおさんぽ
自己評価【2歳児・6月】
5月は大型連休を挟んだ園もあり、子どもたちの体調も不安定になりがちな月でしたよね。日々の子どもたちの様子をしっかりと見て、落ち着いたペースで保育を進められていたかどうか振り返ってみましょう。少しずつ暖かくなってきたタイミングでもあったので、気候に合わせて遊びを取り入れられたかどうかもポイントです。
2023年度版フォーマットのダウンロード【2歳児・6月】
ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけプリントして使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。
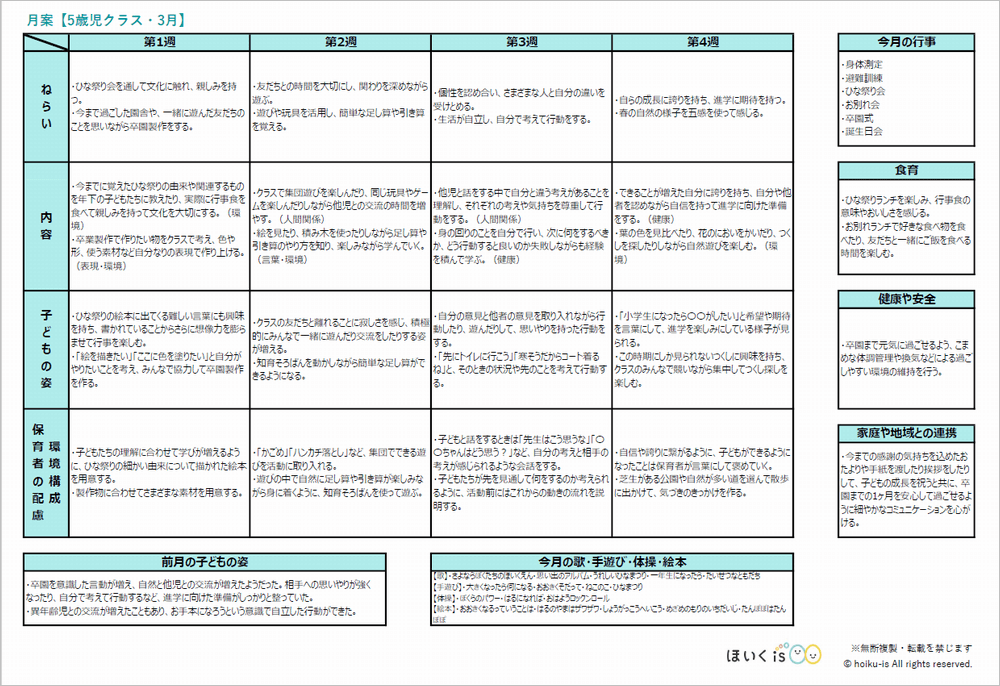
PDF版の月案文例【2歳児・6月】

自分の言葉で作る意識を
参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】
>>指導案・おたより一覧