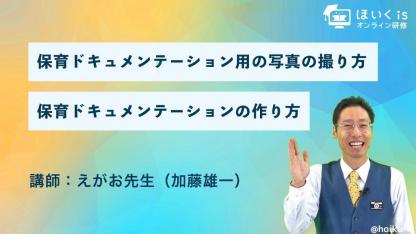季節感のある定番の文例
まずは定番の文例からご紹介しましょう。時節・気候・健康管理に関する文例
- 気温・湿度共に上がり、汗ばむ季節になってきました。園では子どもたちの汗対策をはじめ、健康管理に十分気を付けていきたいと思います。
- 「あーしたてんきになーれ!」という子どもたちの声が聞こえてきました。この機会に、お天気に関係するお話しやおまじないについて子どもたちに伝えていこうと思います。
- 6月は旧暦の和名で「水無月(みなづき)」とも言います。梅雨なのに“水が無い”と書くのも不思議ですが、この場合の「無」は無いという意味ではなく「の」という意味合いで使われているようです。子どもたちには、「6月は水の月なんだよ」と伝えていきたいと思います。
- 子どもたちにとっては、お日様の光が恋しい季節です。園では、てるてる坊主をぶら下げて、一緒にお願いをしています。
- 雨の日が増える時期。お外遊びが楽しみな子どもたちには、「雨が降ったすぐ後には、虹が見えるかもしれないよ」とお話ししてみようと思います。
- 「梅雨」と書く漢字の由来には諸説ありますが、もともと中国で梅の実が熟す時期に降る雨のことを梅雨(ばいう)と呼んでいて、それが日本に伝わったとも言われています。また「つゆ」と読むようになったのは、雨から連想される「露(つゆ)」の読み方を「梅雨」にあてるようになったからとも言われています。子どもたちには、「梅の実が大きくなる季節なんだよ」など、由来についてお話ししてみても良いですね。
- 6月と言うと一般的には衣替えの季節ですが、既に夏が始まったかのように蒸し暑い日が続いていて、子どもたちは一足早く「衣替えは完了」という状況です。本格的な夏に備えて、子どもたちの服装や健康状態にも気を配っていきたいと思います。
行事・祝日・活動に関する文例
- 今月は歯と口の健康週間(※そのほか「歯の衛生月間」「虫歯予防デー」など)ということで、歯科健診と歯磨き指導のほか、クラスでのお話しや絵本の読み聞かせで、歯の健康について教えていく活動を予定しています。
- 春から初夏、梅雨と、子どもたちが季節の移り変わりを体感するには良い時期とも言えます。園では自然観察など、気付きを促すような活動をしていきたいと考えています。
- 子どもたちも園生活に慣れ、子どもたち同士や、先生たちとの関わりも徐々に深まってきたように感じています。
- 今月は、雨の日にてるてる坊主の製作をする予定です。子どもたちには、活動を通して由来や梅雨のこと、昔からある風習などについて伝えていきたいと思います。
- どうしても室内での活動が多くなる時期です。園でもいろいろ工夫をして、できるだけ子どもたちが身体を動かせるようにしていきたいと思います。
- 新年度スタートから3カ月目。環境の変化や大型連休を経て、子どもたちもすっかり園生活のリズムに馴染んできたように感じられます。
情景が目に浮かぶ文例
- 雨上がりの草花の中、小さなアマガエルやカタツムリが気持ちよさそうにたたずんでいる姿が。子どもたちも興味津々の様子で観察していました。
- 晴天に恵まれると、園庭からは外で遊びたくてウズウズしていた子どもたちの元気な声が聞こえてきます。
- 雨上がりの陽射しで、園庭の草花の葉っぱについた水滴がキラキラ輝いています。子どもたちにも、自然が描く風景を感じてもらえるよう促していきたいと思います。
- 紫、青、ピンクと、アジサイが色とりどりの花を咲かせています。英語ではhydrangea(ハイドレンジア)と言い、「水の器」という意味もあるそうです。何だか、イメージにぴったりの素敵な名前ですね。
- しとしと降る雨の中、カタツムリがゆっくり進んで行く姿がありました。そこだけ、ゆっくりと時間が流れているように思えました。
- 下駄箱を見るとカラフルな長靴がいっぱい。ぐずついたお天気が続きますが、逆に雨の日だからこそ見られる風景に癒されています。
- 小さい花、大きな花がてくてく。「傘の花が咲く」という例えもありますが、雨の日の登園風景は微笑ましく感じます。
- 雨上がりの水たまりに映る青い空と、子どもたちの元気な姿。この季節ならではの景色が微笑ましくもあります。
- 「しとしと」「ざぁざぁ」「ぽつぽつ」。雨が多い季節になりましたが、耳を傾けてみるとさまざまな雨音があることに気付きます。子どもたちにも、そういった気付きに繋がるよう促してみたいと思います。
- 雨音に誘われて現れたアマガエルを見つけた子どもたち。ぴょんぴょんとと跳ねる姿を見て、子どもたちが真似している姿が微笑ましかったです。
- 好天に恵まれたときの日差しは、本格的な夏そのもの。ジリジリと音が聞こえてきそうですね。子どもたちも汗をたくさんかくようになってきたので、しっかりと健康観察をして体調に気を配っていきたいと思います。

新型コロナウイルスに対応した文例
2023年度は、新型コロナウイルスも少しずつ収束の気配を見せています。しかし、さまざまな人が出入りする社会インフラでもある園としては、なかなか気を緩めることはできません。引き続き保育園や幼稚園、こども園から保護者へのおたより・クラスだよりでも伝えるケースがあると思います。書き出しで織り込んだ文例もご紹介しておきます。- 気温・湿度共に上がる季節を迎えます。新型コロナウイルスのほか、この時期から増える感染症や暑さ対策など、子どもたちの健康管理には、十分気を付けていきたいと思います。引き続きご協力をお願いいたします。
- 間もなく園生活も3カ月目。子どもたち同士の関わりも増え、楽しく毎日を過ごしている様子がうかがえます。引き続き新型コロナウイルスを始めとする感染症対策へのご協力をお願いする中ではありますが、引き続き子どもたちの成長を見守っていきたいと思います。
- どうしても室内での活動が多くなる時期となります。園でも、室内の換気や消毒・除菌などの衛生管理をの徹底に務めながら、安心して子どもたちが活動できる環境作りをしていきたいと思います。
自分のパターンを見つけよう
いかがでしたか? さまざまな文例を参考に、自分なりのオリジナルのパターンを身に付けられるようにしましょう。季節の風物詩や、子どもたちの様子など、身の回りにはたくさんの“ネタ”が転がっているものです。楽しみながら考えてみてくださいね。【関連記事】
>>指導案・おたより一覧