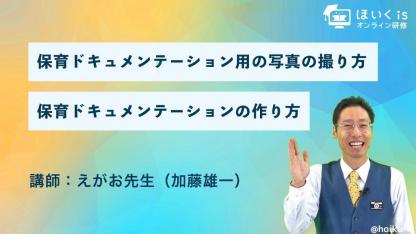お泊まり保育のねらい

- 行事を通して他児や保育者との親睦を深める
- 他児と協力して物事に取り組み、協調性を育む
- 保護者のもとを離れて過ごすことで自立した生活を送り、自信をつける。
- 規則正しい生活を習慣づける。
1日の流れ

1日目
15:00 登園15:30~ 活動
17:00~ 夕食
19:00~ 入浴
20:00~ 活動
21:00 就寝
1日目は午後から登園し、活動が始める園が多いようです。それに合わせて担当の保育士も出勤することになります。近隣の銭湯に出向いて入浴したり、子どもたちと一緒にカレー作りを楽しんだりと楽しみが詰まった1日です。
2日目
6:00 起床6:30~ 体操
7:00~ 朝食
8:00~ 朝の活動
9:00~ 解散式
9:30 解散、降園
2日目は朝に解散になるため、土曜日にあてている園も多いようです。楽しみだけでなく、緊張や不安などさまざまな感情を抱えながら頑張った子どもたちを笑顔で見送りたいですね。
おすすめのレクリエーション
園内でのお泊まり保育では、夕方や夜の活動時間にゲームなどのレクリエーションタイムを用意することが多いと思います。そこで、子どもたちがみんなで楽しめるアイデアをご紹介します。宝探し

お友だちと協力することで、協調性や団結力も高まりそうですね。一斉に探し始めるのではなく、グループごとに探す場所を決めておくなどしてみんなが見つける楽しみを感じられる工夫をしておきましょう。
スタンプラリー
各場所でクイズやゲームをして、クリア出来たらスタンプを押してもらえるスタンプラリーもおすすめです。全部クリアできたら、プレゼントやメダルを用意しておくのも良いですね。ここでもみんなで一緒に考えたり、力を合わせて何かをやり遂げることを体験することができます。
花火
夏の風物詩といえば花火。せっかくなので季節を感じられる遊びを取り入れてみるのも良いでしょう。お友だちや先生と一緒にする花火はきっと子どもたちの思い出に残ります。火を取り扱うので、事前に注意事項をしっかりと話しておきましょう。また終わった後の始末にも注意して、安全に楽しんでくださいね。
お買い物体験

料理
夕飯は調理スタッフさんのおいしいご飯も良いですが、余裕があれば子どもたちと一緒に作ってみるのも良いかもしれません。一から全てやっていると時間がかかってしまうので、子どもたちに任せるところを決めておき、ある程度準備をしておきましょう。お米の研ぎ方や包丁の使い方だけでなく、手洗いや器具の除菌などの衛生面にもしっかりと気をつけて取り組んでくださいね。
お泊まり保育の注意点

保護者への連絡は余裕を持って
お泊まり保育は子どもにとっても保護者にとってもドキドキの行事です。初めて親と離れて過ごすという子も少なくありません。物の準備はもちろんですが、子どもの心の準備も必要です。保護者には早めに連絡をして、不安や心配なことがないか確認しておきましょう。お風呂の入り方を確認
銭湯などの施設を利用してお風呂に入る場合は、入浴時間の保育士の動きをしっかり考えておきましょう。園によって一緒にお風呂に入るところ、Tシャツなどを着て付き添いをするところなどさまざまです。複数人の子どもがいるので、事故やケガがないよう目が行き届く体制にしておきましょう。また、中には銭湯の営業時間内に行くこともあります。そのときは他にお客さんがいるかもしれないことを子どもたちに事前に説明し、公共の場でのマナーを一緒に考えておきましょう。
持病は医師とも連携を
普段とは違う雰囲気に緊張や興奮をして、持病の症状が出る可能性があります。服薬などをしている子どもの対応は、事前に保護者だけでなく医師とも連携を取っておくと安心です。緊急時の対応や連絡先などは参加する職員全員が把握するようにしておきましょう。園生活の思い出に
お泊まり保育は年長クラスで行うことが多く、園生活最後の1年の行事のひとつですよね。協調性や自立心などさまざまな面を育てながら、素敵な思い出になるように工夫してみてくださいね。【関連記事】