運動会のねらいとは?

ねらいを決める際にも、園の体制や開催状況などを踏まえて考えてみると良いでしょう。子どもたちの力をさらに伸ばすことができるねらいを考えてみてくださいね。
【例】
- 友だちと協力してひとつのことをやり遂げることで協調性を育む。
- のびのびと身体を動かす楽しみを感じる。
- 親子競技を通して、一緒に身体を動かしながら触れ合いを楽しむ。
- 競技に挑戦したり、成功することで自信をつける。
- 運動会を通して悔しさや喜びなどいろいろな感情を経験する
テーマはどうする?

子どもたちに身近なもの
子どもたちの身の回りで出会う生き物や遊び、絵本の内容などをもとに、出来るだけ身近なものをテーマに選びましょう。なじみのないものを掲げても、子どもたちにとっては分かりづらく主体的に取り組めないものとなってしまいます。普段の様子から探ったり、子どもたちと一緒に話し合うなどして決めると、子どもの想いを反映したものになります。勝敗だけが目的でないもの
運動会というとチーム分けをして勝敗を競う…というイメージがありますが、ここでは勝敗が全てではありません。もちろん勝ち負けを経験することで喜びや悔しい気持ちを育てることも大切ですが、保育園の運動会のテーマとしてはそれだけに絞らず、ねらいを達成できるようなものを考えてみましょう。0歳児クラスにおすすめのプログラム

ハイハイレース
運動会や親子イベントなどでも行われることが多い「ハイハイレース」。マットを敷いて、保護者や保育者が待っているゴールまで一直線! まっすぐに進んでくる子もいれば、全く違う方向に行ってしまう子もいて、その姿がとても可愛らしいです。親子で触れ合い遊び
低月齢の子が多いクラスに特におすすめなのが、親子(保護者と子ども)で行う触れ合い遊びです。「バスにのって」や「いっぽんばしこちょこちょ」など、スキンシップをとれる遊びを取り入れてみましょう。運動会の雰囲気に緊張してしまう子もいますが、親御さんと一緒であれば安心ですね。段ボールカーリレー
段ボールで作った乗り物に子どもを乗せて、保護者がコースを運ぶリレー競技です。段ボールはしっかりと補強し、リレー中に壊れないような作りにしましょう。また、その年のテーマに合った装飾をするとよりよいですね。
トンネルくぐり競争
筒状の遊具か、ダンボールでトンネルを作って、子どもたちがそこをくぐる競技です。屋外で行う場合はマットを敷くなど、安全に配慮して行ってくださいね。また、当日までにトンネルくぐりを保育に取り入れて、慣れておくことも大切です。
おんぶリレー
保護者が子どもをおんぶして行うリレーです。子どもが保護者のところまで進み、そこからは保護者が子どもをおんぶして走ります。かけっこ形式でも、チームごとのリレー形式でも楽しめますよ。子どもが保護者のところに着く前に止まってしまった場合は、迎えに行ってもOK! 柔軟に対応しましょう。
マラカスダンス
子どもにペットボトルマラカスを渡して、音楽に合わせて自由に身体を動かしましょう! 「ぺんぎんたいそう」や「ちょっとだけたいそう」など、普段クラスで流している親しみのある曲を使うといいですね。
▼おすすめの体操ソングはこちら
1歳児・2歳児クラスにおすすめのプログラム

積み木積み競争
コースの真ん中にバラバラにした積み木を置いて、保護者や保育者と一緒に積み木を積んだらゴールへ走ります。積み木は大きなソフトブロックがおすすめ。「どうすれば上手に積めるか?」を考えて慎重に積んでいく必要があります。大きな積み木であれば1歳児クラスでも扱いやすいですよ。絵合わせ借り物競争
箱の中から絵が書かれたカードを1枚選択。机に並んだものの中から、絵と同じものを探し出す借り物競争です。自分の持っているカードの絵と、実際に置かれたものを見比べて絵合わせを行うので、じっくりと物を見たり判断することが大切。普段の遊びの延長として楽しめる競技ですよ。親子ペンギン歩き競争

的当てゲーム
ボール遊びが好きなら、的当てゲームを取り入れるのはいかがでしょうか。的の柄をその年のテーマに合ったものにすれば、一気にその年らしさがでるのが嬉しいですね。「いくつポイントが入ったか?」が分かりやすい的当てゲームの例は、以下の3つです。①的の下に籠を置いておき、その籠に入ったら1ポイント
②ボール(または的)に粘着テープを貼っておき、ボールがくっついたら1ポイント
③段ボール箱に大き目の穴を空けておき、その穴に入ったら1ポイント※穴は動物やキャラクターの口に見立てると良い
果物玉入れ
果物狩りごっこと玉入れを組み合わせた競技です。段ボールで作った木から果物をもぎ取り、籠の中まで届けます。1・2歳児の場合は勝ち負けにこだわらず、果物をもぎ取る→届けるの流れを楽しみましょう。保護者が抱っこで補助して籠に入れられるようにするなど、親子競技としてもおすすめです。動物なりきり競争
「よーい、どん!」でスタートしたら途中で好きなカードをめくり、そこに描かれた動物になりきってゴールを目指す競争です。なりきる動物は、ウサギ、カエル、イヌ、ヘビなど普段リトミックで行っている動物にするといいですよ。動物なりきり競争(親子競技バージョン)
親子競技として楽しめる動物なりきり競争は、保護者と子どもの2人でペアになって行います。くじを引いたら、そこに描いてある動物になりきってゴールを目指します。どんな動きをするかはくじに記載しておくとスムーズですよ。おすすめのお題をいくつかご紹介します。- コアラ:おんぶ
- ペンギン:親の足の上に子どもを乗せて歩く
- ウマ:背中に乗せてハイハイ
- カンガルー:だっこしてスキップ
- ゾウ:子どもの脇を両手で支え、ゾウの鼻のように揺らしながら進む
- キリン:子どもを肩車して大股歩き
宝探しゲーム
宝物を探して、ゴールを目指す競技です。くじを引いて、そこに描かれたお題のものを決められた範囲で探しましょう。動物、果物、乗り物など、子どもたちに身近なお題を設定することがポイントです。3歳児クラスにおすすめのプログラム

巨大パズル
段ボールなどで作った巨大パズルを、友だちや保護者と協力して完成させましょう。リレー形式で、順番に1ピースずつ当てはめていくのがおすすめです。考える力や協力することが必要になってくるので、周囲の人との関係性が築けてくる幼児クラスにはぴったりですよ。カードめくりゲーム
2チームに別れて紅白のカードを自分のチームの色にひっくり返す定番ゲームです。瞬発的に自分のチームの色か相手チームの色かを判断したり、素早い動きでカードをひっくり返したりする必要があります。意外と全身を使うので、運動会にっはぴったりですよ。玉入れ (異年齢交流競技として)
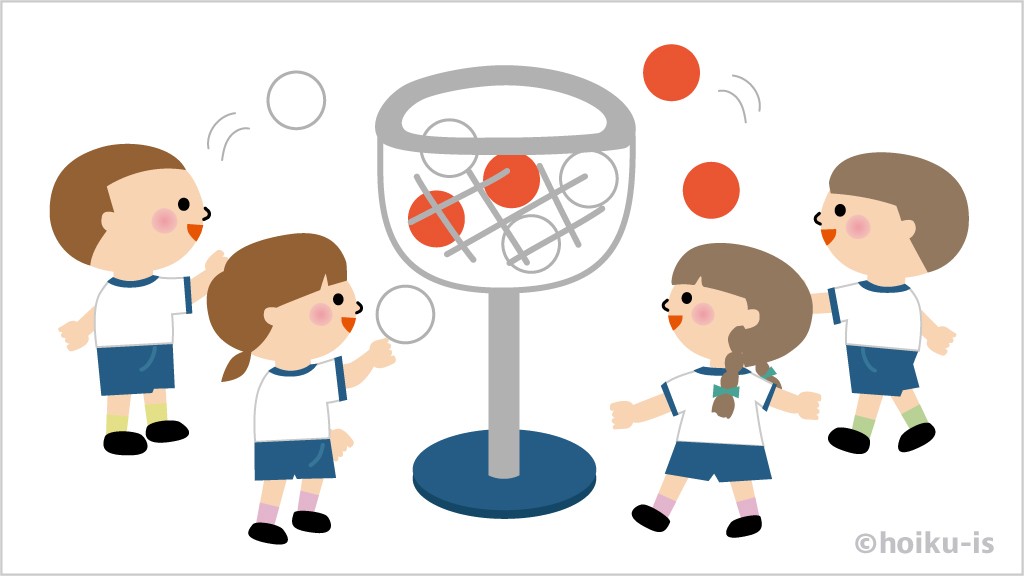
<遊び方>
①赤組・白組に分かれて、それぞれ自分のチームの籠の周りに円になります。
②「よーい、どん!」の合図で、まず3歳児が自分のチームの籠に玉を入れます。笛が鳴ったら投げるのをやめて、元の位置に戻ります。
③「よーい、どん!」の合図で、次は4歳児が自分のチームの籠に玉を入れます。笛が鳴ったら投げるのをやめて、元の位置に戻ります。
④「よーい、どん!」の合図で、最後に5歳児が自分のチームの籠に玉を入れます。笛が鳴ったら投げるのをやめて、元の位置に戻ります。
⑤籠の中に入っている玉を数えて、より多いチームの勝ちです!
玉入れダンス(ダンシング玉入れ)
玉入れとダンスを掛け合わせた競技です。音楽が流れて、先生の笛の合図があったら、玉入れを止めてダンスを踊ります。玉入れが少し苦手な子も、音楽に合わせたダンスをみんなで楽しめるのがポイント。見ている保育者、保護者も、あまりの可愛さに思わず見入ってしまいますよ。ダンスパートにおすすめの曲は「チェッチェッコリ」です。歌詞が流れているときはダンスの時間だよと、子どもたちにタイミングを伝えやすい曲です。<遊び方>
①赤組・白組に分かれて、それぞれ自分のチームの籠の周りに円になります。
②「よーい、どん!」の合図で、一斉に自分のチームの籠に玉を入れます。
③歌が流れ始めたら、ダンシングタイム! あらかじめ教えてある振り付けを踊ります。
④合図があったら、また玉入れに戻ります。
⑤③④を繰り返し、曲が終了したら玉入れも終わります。
⑥最後に籠の中に入っている玉を数えて、より多いチームの勝ちです!
鬼ごっこ玉入れ
玉入れと鬼ごっこを掛け合わせた遊びです。保育者が大きな籠を背中に背負い、子どもたちはそれを追いかけて玉を入れます。「逃げていく籠を追いかけたい!」と子どもの白熱度は増しますが、逃げる保育者の体力が必要ですね(笑)。また、玉を拾う子、追いかける子、逃げる先生と色んな方向に動くことになるので、ぶつかってケガをしないように注意しましょう。<遊び方>
①赤組・白組に分かれて、それぞれ自分のチームの籠を背負った先生の周りに円になります。(相手チームの先生が背負うのがおすすめです)
②「よーい、どん!」の合図で、籠を持った先生を追いかけて自分のチームの玉を入れます。先生は逃げ回ります。
③笛が鳴ったら投げるのをやめて、元の位置に戻ります。
④籠の中に入っている玉を数えて、より多いチームの勝ちです!
かけっこ
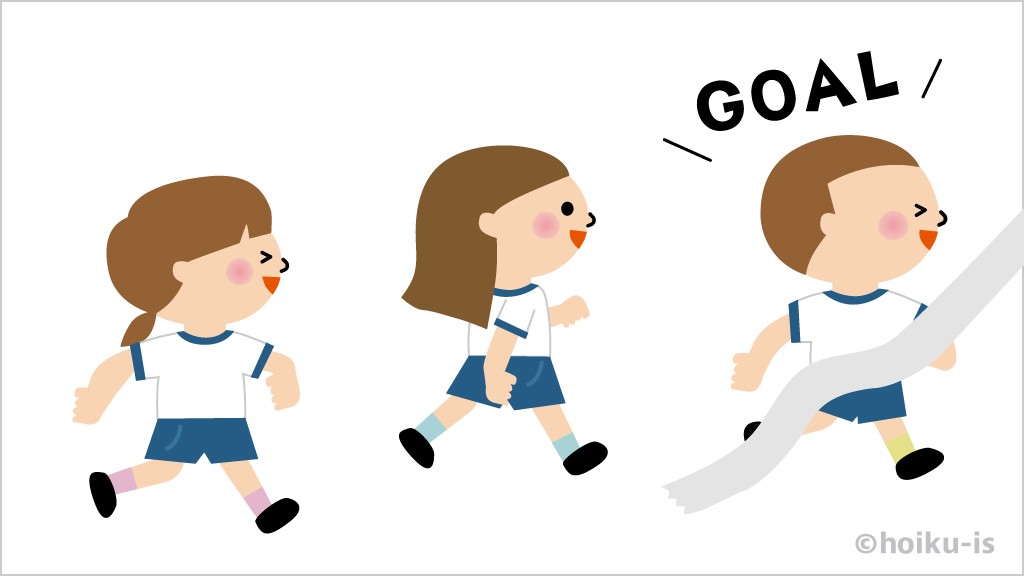
綱引き
相手チームと向き合い、縄を引きあう真剣勝負! 腕の力や足腰を鍛えることができるだけでなく、お友だちと息を合わせることも学べる競技です。「笛が鳴ったら、引っ張るのを止める」というルールを伝えながら楽しんで見てくださいね。また、反動で転んだりしないよう、保育者がサポートをしつつ行いましょう。ボール送りリレー
ボールをお友だちに順番に渡していき、ゴールを目指す競技です。「頭の上を渡していくゾーン」「足の間を渡していくゾーン」のように渡し方を決めたり、渡し終わったら最後尾の子の後ろに並んでいったりと、ルールのアレンジもしやすいです。ダンス

おつかい競争
借り物競争を親子競技にアレンジしました。保護者がくじで引いたお題のものを子どもに伝えて、子どもはそれを借りてきます。最後は保護者と一緒にゴール! コースには障害物を置いて、サーキットレースっぽくしても面白いですよ。4歳児・5歳児クラスにおすすめのプログラム

障害物競走
マットの上をでんぐり返ししたり、フープをくぐったり、平均台の上をバランスを取って歩いたりと全身を使ってのびのび動いてみましょう。普段サーキット遊びをしている園では、そこで使っている遊具も役立ちますね。身体のさまざまな場所を使うので、まさに運動会競技にもってこいです。キャタピラリレー
丸い段ボールの中に入ってハイハイで前進! 2人1組でもできるキャタピラリレーです。まっすぐに進むのが意外と難しいため、広い場所を確保できる場合におすすめしたい競技です。行う場合は、隣のコースの子とぶつからないように保育者がサポートしながら楽しんでくださいね。ニンニン!忍者競争
障害物競走を、忍者ごっこにアレンジした競技です。次々と現れる敵の罠をくぐりぬけるように、「忍法●●の術!」を使って進んでいきます。忍者の衣装を用意しておくとより楽しめるでしょう。ゴールには宝物のありかが書いてある巻物を置いておくのもいいですね。おすすめの障害物は以下のようなものがあります。- 忍法、くもの巣の術!:ネットを潜り抜ける
- 忍法、石渡りの術!:ソフトブロックの上、または点々と置いたフラフープの中をジャンプで渡っていく
- 忍法、大ジャンプの術!:跳び箱を跳ぶ
- 忍法、バランスの術!:平均台を渡る
配達屋さんゲーム
ふろしきなどの上にボールなどを乗せて、2~4人1組でゴールまで配達! バランスをとったり、友だちと協力したりしながらも、スピードが必要になる競技です。速く走り過ぎてもボールが飛んで行ってしまうので、意外と難しいですよ。パラバルーン
プログラムの目玉として5歳児クラスで披露することも多いパラバルーン。きれいに見せるための動き方やタイミングがとても重要になる競技です。周囲との協力はもちろん、自分の動きもしっかりと把握しておかなければいけません。保育者も指示を出したりする必要があり、普段の練習も大切になります。難しいからこそ、園生活最後の運動会競技としておすすめです。大玉転がし
大玉をお友だちと協力して、ゴールまで素早く運びましょう。力加減やスピードが異なると大玉が道を逸れてしまうので、お友だちと息を合わせることが大切です。リレー形式にするとより白熱しますね。台風の目
2~3人で長い棒を持ってコースを走り、台風のようにカラーコーンの周りをぐるんと回って戻ってくる競技です。"台風の目"の側(カラーコーンの近く)を走る子は棒を支える力が必要で、外側を走る子は他の子より走る距離が長くなるので早く走る必要があります。誰がどの場所になるかを相談して決めましょう。<遊び方>
①2~3人で人1組を作り、長い棒を両手で持ちます。
②「よーい、どん!」の合図でカラーコーンまで走ります。
③カラーコーンの周りを1周し、戻ってきます。
④棒を次のペアに渡します。
⑤先に全ペアがコースを走り終えたチームの勝ちです!
マット運びレース
1枚の大きなマットに、チーム全員が走って体育座りをしに行き、全員が座れたらそのマットをゴールまで運ぶ競技です。マットに素早く座ることがポイントなので、「奥から座る?」「座るところを決めておく?」など子ども同士での作戦会議をすることが大切です。<遊び方>
①赤組・白組などチームごとにスタート位置に立ちます。
②「よーい、どん!」の合図で、遠くに置いてあるマットまで走り、マットの上に座ります。
③全員が完全に座ったら、マットから降りてみんなでマットを持ちます。
④先にゴールまで運んだチームの勝ちです!
うさぎジャンプレース
うさぎになりきり、ゴールまで両足でジャンプ! ぴょんぴょんとジャンプする子どもたちがとっても可愛いレースです。普段の保育で動物なりきり遊びをしているクラスは、その遊びの延長線として取り入れるのもいいですね。ウサギの頭飾りを用意しておくのもいいでしょう。また、フラフープをコースに置いておくと目印になって走りやすいですよ。マット綱引き
真ん中にたくさん置いてあるマットを、両端の自分のチームの陣地に引き込んでいくゲームです。単純なルールですが、「あれは相手チームに取られそう、別のにしよう」「あっちのお友だちを手伝いに行こう!」と作戦を立てながら動けるようになっていきますよ。ねことねずみ
ねことねずみチームに分かれて、先生が「ねこ!」といったらネコが、「ねずみ!」と言ったらねずみがオニになって追いかける遊びです。赤組がねこ、白組がねずみ、のようにチームごとで分かれてもいいですね。ピンポン玉リレー
ピンポン玉をおたまの上に乗せて、落とさないようにリレー形式で運んでいきます。ピンポン玉を落とさないようにする慎重さやバランス感覚と、急いで運ぶという相反する動作が同時に求められるので、集中力が見につきます。取り入れる年齢によっておたまからスプーンに変えるなど、難易度を調節しながら行いましょう。風船運び競争
二人一組になり、風船(ボールでも可)を身体の間に挟んで運びましょう。お腹に挟む、背中に挟むはペアごとの自由です。お友だち同士で事前に練習を重ねると、息を合わせて落とさないように運ぶことができそうですね。フラフープ送りリレー
お友だち同士で手を繋ぎ、端から端へフラフープをくぐって通していく競技です。隣の人との身体の大きさが違う方が難しいので、親子競技の1つとして行うのもおすすめです。担任の先生も一緒に参加しても面白いかもしれませんね。デカパンリレー
大きなパンツの片足側に保護者の方が、もう片方が子どもが入り、息を合わせて走りましょう! 体を支え合ったり、「いちに、いちに」と声かけをしたり、走るスピードをいかに合わせられるかが重要です。デカパンは市販でも購入できますが、布やカラーのポリ袋を用意して手作りすることも出来ますよ。<遊び方>
①各チーム、親子でペアになりリレーの順番を決めます。
②先頭のペアは、デカパンの片側に保護者、もう片方に子どもが入ります。
③「よーい、どん!」の合図で、息を合わせてコースを走ります。
④コースを走り切ったら、次のペアにデカパンを渡します。
⑤先に全ペアがゴールしたチームの勝ちです!
バトンリレー
パラバルーンと合わせてプログラムの目玉になることが多いのが、バトンリレー。 クラスごとに心をひとつにバトンを繋いでいく様子は、とても感動的ですよね。かけっこや鬼ごっこなど、身体を動かす遊びが好きな子どもが多い園では、特におすすめの競技です。子どもたちの想いを取り入れた運動会に!
運動会というと保育士さんが競技を決めることも多いですが、今年は子どもたちと話し合って決めてみませんか? 難しい場合は普段の遊びや好きなものを参考にするなど、子どもたちが主体的に参加できるような形を工夫してみてくださいね。▼おすすめの無料ダウンロード素材
保護者への運動会の案内状に役立つイラストのダウンロードはこちら
|
★ 遊び方解説のイラストをダウンロードしてご利用いただけます! こちらのページで紹介したイラストを遊び方の説明などでご利用いただけるよう、ダウンロード素材をご用意しました。ダウンロードするためには「ほいくisメンバー」への登録(無料)が必要です。  |














































