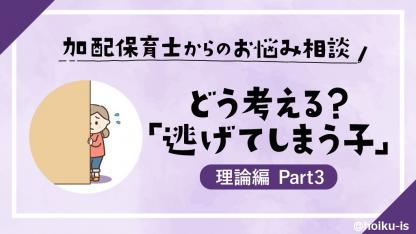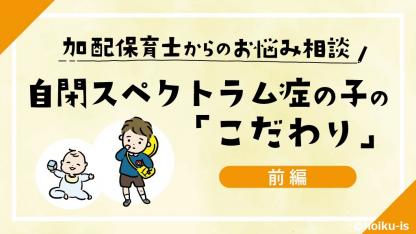>>連載の記事一覧はこちら
「自閉症スペクトラム障害」の対応についてのお悩み
今月から3回にわたって、加配保育士へのアンケートで挙がったお悩みに答えていきたいと思います。|
<今回のお悩み> 「重度の知的障害で、自閉症スペクトラム障害のアオト君。ブロックや人形を渡してもぽいっと放り投げてしまうなど、なかなか園生活で好きな遊びを見つけられません。どのように園の指導内容を考えればいいでしょうか?」  |
定型発達の子どもを含めて、「遊び」をみつけられないでいる子どもが「遊び」を獲得できるよう支援するときのヒントになればいいなと思います。
これから「遊び」をみつけるにはどうしたらいいかについてお話するわけですが、それとはまた別に、すべての子どもの「遊び」において常に配慮してほしい2つのことを先にお伝えします。
- 安全安心を確保すること
- 集中できる環境を整えること
「安全安心」を確保する
不快だったり緊張している状態では「遊び」はできません。「安心できる空間」を整えることは「遊び」においてとても大事です。次のようなことに配慮しましょう。
①感覚過敏のチェック
●発達障害のある子の多くは、感覚過敏などの感覚調整障害があります。嫌な音、嫌な視覚刺激、嫌な触覚、不快な関わり方は何かを確認し、不快な刺激があれば取り除きます。●強い光が嫌ならカーテンを閉め、大きな音が苦手ならば太鼓などの活動を避けます。
②「遊び」をする場所を固定する
発達障害のある子は「何が起きるか予測できない」から安心できないことがありますが、遊ぶ場所を固定すると、ここではこれをして遊ぶ、これをして遊ぶ以外のことは起きないとわかって安心できます。しかし、遊びをする場所を固定するには、そもそも何をして遊ぶかがはっきりしていないといけません。
これから「遊び」を検討していくわけですが、その結果、子どもが楽しむことができる「遊び」がみつかれば、その「遊び」をする場所を固定することで子どもは「ここは楽しいこの遊びをする場所、ここでは他のことは起きない」とわかり、安心できます。
アオト君のような重度の知的障害がある場合「わかっているのか?わからないのか?が、わからない」と保育士から聞くことも多く、これからお話するような検討を通じて「遊び」をみつけることも容易ではありません。
しかし、「遊び」がみつかると、上記のようにそれが「安心」にもつながるのです。発達障害のある子にとって「安心」はとても大事なことです。
ですから、これからお伝えすることを参考に、どうか根気強く、子どもの「遊び」を見つけ出してほしいと思います。
③保育士との間に安心できる関係をつくる
保育士との間に「この人は安心できる」「この人のことを見ていると、おもしろいことがある」という関係があることも大切です。先月のコラムでお話したように「子どもの今の状態に‟ガツッ”と踏み込まない」「関わりを強要しない」というようなことに気をつけながら、少しずつ子どもに安心してもらえる関係を目指したいです。

集中できる環境を整える
発達障害のある子の場合、何かの刺激があるとそこに意識がむいてしまい、「遊び」に集中できないことがよくあります。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。