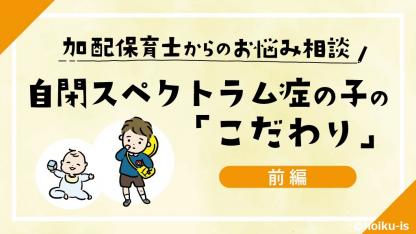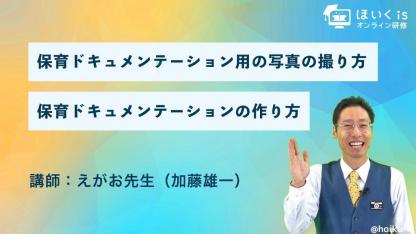>>連載の記事一覧はこちら
今回のテーマ
|
<どう関わる?> 「子どもが一度パニックになると、そこからなかなか平常に戻れない」ケース |
- パニックの原因の特定方法
- 「状況事象の影響」が原因の対応方法
- 「感覚過敏」が原因の対応方法
パニックを防ぐ対応「こだわり」
こだわり行動を止められるとパニックになる子どもは多いです。子どもが示すこだわりは奇異に感じられるので、どうしても叱ったり、止めさせようとしてしまったりしがちですが、こだわりには必ず理由があります。
周りを困らせようとしてやっているわけではないのです。
「こだわりには理由がある」ことを常に意識し、こだわりの理由を理解した上で対処を考えていきたいです。
子どもの特性によるこだわり

●「同じ」状態を志向する特性(同一性保持)
●思ったことを最後までやり終えないと満足できない特性
を持っていることがあり、それがこだわりにつながることがあります。
物を置く位置・衣服の好み・道順などのこだわりで、危険でない・自分や周囲の人に多大な迷惑や支障を引き起こすものではないのであれば、奇異に感じたとしてもやめさせるのではなく、ある程度認めてよいものと考えます。
「嵐の中のブイ(浮標)」であるこだわり

| ●やっている活動の意味がわからないとき、こだわり行動による「自分に理解できる刺激」で時間を過ごそうとする ●感覚過敏による「嫌な刺激」の嵐の中で自分自身を保つために、こだわり行動による「自分に理解できる刺激」を求め続ける |
こだわり行動を止められると「嵐の中でブイを取り上げられた」子どもはパニックを起こします。
対応は「嵐」を起こさないようにすることです。
活動の意味づけができないことで不安ならば、子どもが「わかる」活動にする、感覚過敏を排除する、などの工夫をします。
このようにして「こだわり行動」という「ブイ」を必要としない、ブイがなくても大丈夫、という状態を補償してあげたいです。
思いを「変えない」こだわり

「額を壁から外す」という「思ったこと」を最後までやり終えないと満足できない特性の表れでもあります。
これは「困る」こだわりなので、こだわり行動をしないですむように考えます。
それにはこだわりの「きっかけ」から優樹菜ちゃんを遠ざけることです。
|
<具体的にどうする?> 優樹菜ちゃんは「園長先生の写真の額」を外すことにこだわりがあるとわかったわけですから、次からはこだわりのきっかけとなる「園長先生の写真の額」が優樹菜ちゃんの目に入らないようにします。 保育現場では、子どもが「何をしたい」と思うかが全部わかるわけではないので、いつも先回りして対応できるわけではありません。 でも「水を見ると触って遊ばずにはいられない」「他の子の折った折り紙を見るとくしゃくしゃにしたくなる」などのこだわりがわかっていれば、 それらから遠ざけることで、一定のこだわり行動を抑止でき、こだわり行動を制止されることによるパニックを予防できると思います。 |
パニックを防ぐ対応「予定の変更」
予定の変更や予測がつかない状況など、「次の何が起こるか予想できない」「思っていたのと違う」ことがパニックにつながる場合は、次に何が起こるかを「子どもがわかるように」伝えるという対応がとても重要です。
|
<具体的な対応例> ●一日のスケジュールを子どもがわかる絵や写真で示す ●次の活動をイメージしやすい実物を提示する ●切り替えに対する準備ができるように予告を頻回におこなう ●待つことが苦手な子どもでも理解できるような、待ち時間の目安がわかる道具を使う(キッチンタイマー、砂時計、カウントダウン) 太一君のケースでは、「ちょっと待つ」ってどれくらい待つのか、そのあと誰が来て何をするのかなどがわからなかったために太一君はパニックになったと考えられます。 |

発達障害のある子の場合、「もう少し待ってね」「次はお弁当だよ」など、難しくはない・当然伝わると思ったことが「伝わらない」「わかっていない」ことはあります。
そして「わかっていない」ことが、私たちには想像できないくらい、子どもにとってはとてつもなく不安なのです。
発達障害のある子に向き合うとき、ぜひこのことを理解してほしいと思います。
パニックを防ぐ対応「複数作業」「過負担」
作業ストレスや周りの人の関わりや刺激が本人の許容量を越えるとき、パニックを起こすことがあります。何がパニックの原因かを探すには、保育の環境や子どもがしている活動、保育士の関わり方、本人の周りの他児の状況をよく観察します。
そして、そこに複数作業を含めて子どもの負担になる作業ストレスや過負担がないか、吟味する必要があります。
複数作業
複数作業が子どものストレスになっているようなら、作業を単純化する、分けて提示する、作業の難易度を下げるなどによって、複数作業によるストレスを下げることを考えます。例えば、ぬり絵で「はみ出さないようにしながら」「色を塗る」という複数作業がストレスならば、区切りの線が太いぬり絵にします。
そうすることで作業のストレスを下げられ、パニックを予防できます。
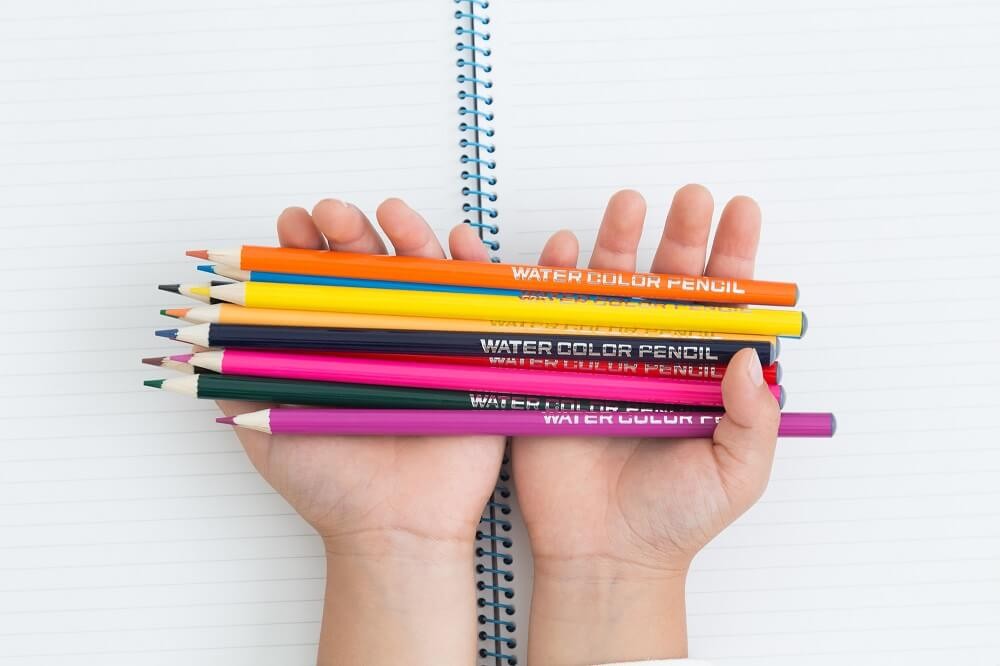
過負担
他児がどういうふるまいをしたとき、どういう子どもが側にいるとき、保育士がどういう関わりをしたときパニックになるかを観察します。過負担の原因が、他児の行動や関わり方だと思われるときは、その子どもとの距離を離したり、背中合わせで視界に入らないようにしたりしてあげます。
保育士の関わりによる過負担を検討するには、子どもと関わっている場面を撮影してもらい、客観的に自身の関わりを点検することもひとつの方法です。
客観的に自分を見ると多くの気づきが得られるものです。
動画撮影でなくても、他の保育士の関わりを観察すること、他の保育士に自分の関わりを見てもらうこと、も気づきにつながります。
| 保育士の関わりが過負担のときに子どもは、 ●無表情になったり、脈絡なくニヤニヤする、表情がこわばる ●興奮しすぎたり、反対に身体をこわばらせる ●動きが激しくなる、逆に、動きが止まる ●モノを投げる、壊す、落とす ●脱力する、眠い、疲れたという などの行動を示すことがあります。 |
じっくり時間をかけたい子のケース

このようなときは先生の出番です。
「美千留ちゃんは自分でやりたいよ」と、美千留ちゃんが周囲の子どもに伝えたいであろうことを代わって伝えてあげましょう。
今回のまとめ
前回と今回にわたって、パニックの原因の特定方法と「状況事象の影響」「感覚過敏」「こだわり」「予定の変更」「複数作業」という5つのパニックの原因別の対応方法をお伝えしてきました。パニックは、心身ともに子どもを消耗させますし、脳が危機モードになり新しいことや人に興味関心が向きにくくなります。
パニックが度重なることで、「うるさい子」「暴力をふるう子」と思われてしまい、他児や周囲との関係が損われることも考えられます。
ですからパニックの原因を探し、対策をうち、パニックを起こさせないようにしてあげましょう。
ただ、いくらがんばって対策をしても、パニックが起きてしまうことはあります。
次回は「それでもパニックになった時は、どう対応するか考えておく」というテーマでお話しします。(2022年2月下旬配信予定です)
▼ほかおすすめの記事はこちら