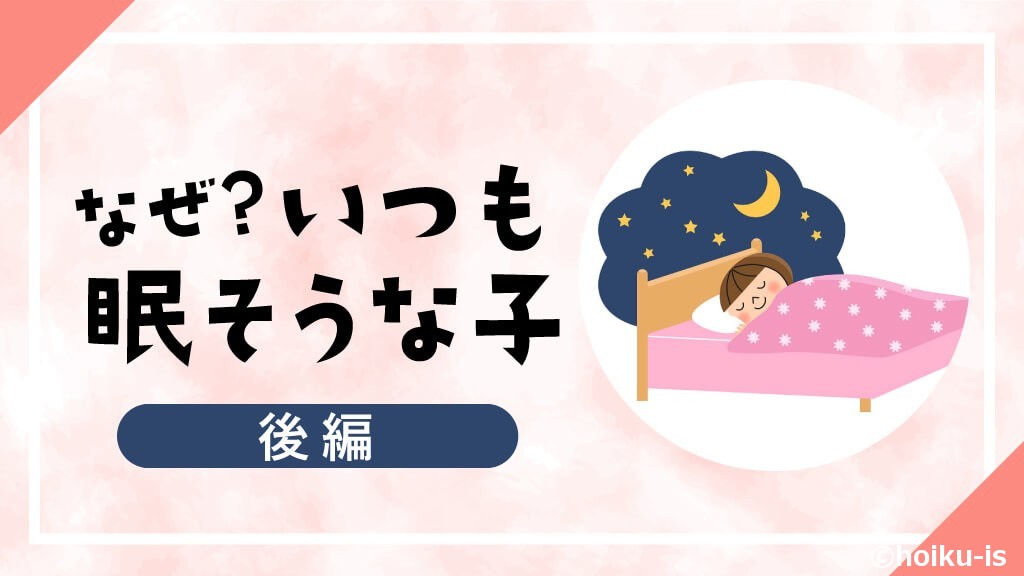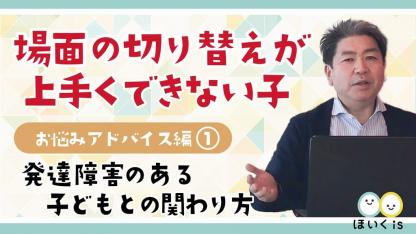【今回のテーマ】睡眠の質を分析する
前回から「いつも眠そうな子」の理由についてお話を始めました。▼前回のお話はこちら 今回はまず「ノンレム睡眠とレム睡眠の最中には、それぞれどういうことが起きているのか?」について、お話ししましょう。
ノンレム睡眠で起きていること
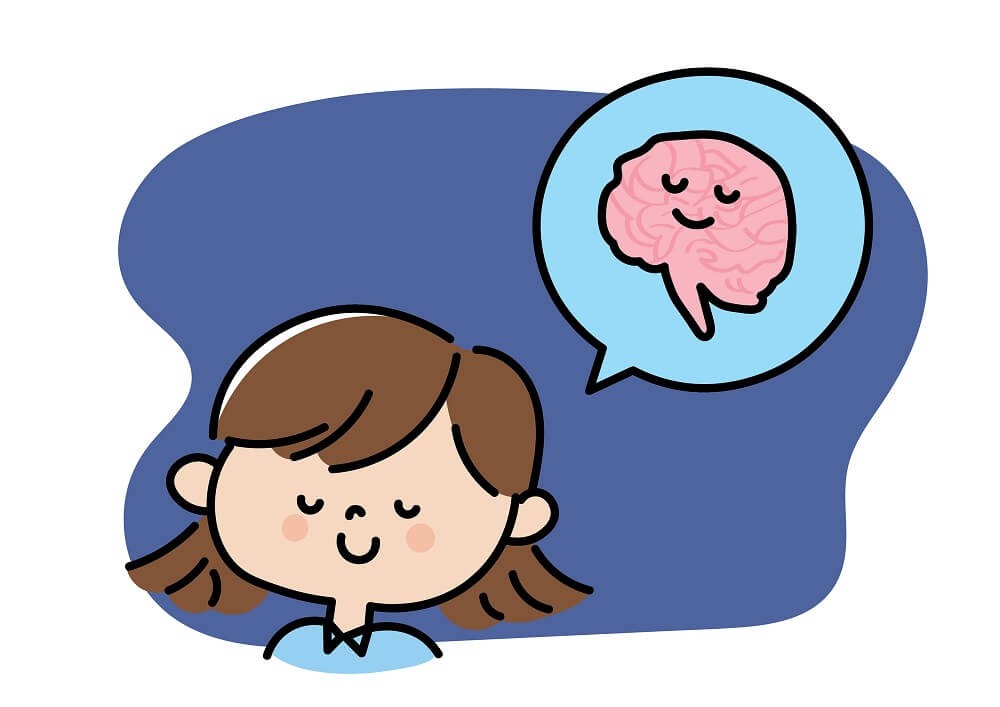
1 脳のメンテナンス
子どもは成長とともに、ことばを話したり考えたり、脳を使うことが多くなります。脳が活動するには脳の情報処理を保つための物質(精神伝達物質)やエネルギー源(ミトコンドリア)が必要であり、脳を使うことでこれらは消費されます。
ノンレム睡眠で脳の深い部分が休息すると、これら「脳が活動するために必要な物質」が分泌されてチャージされ、「脳が活動できる状態」にメンテナンスされます。
2 成長ホルモンの分泌
成長ホルモンは文字通り成長をつかさどるホルモンで、このホルモンの働きで、骨や筋肉が形成され、身長が伸びます。成長ホルモンは、入眠直後のノンレム睡眠、それも最も深いレベル4のノンレム睡眠の時に分泌されると言われています。
成長ホルモンは寝ている間に分泌される
まさに「寝る子は育つ」という諺(ことわざ)どおりなのです。成長ホルモンはその他にも、細胞の新陳代謝を促進し傷を治癒したり免疫を高めたりといった役割も果たします。
ところで、成長ホルモンが骨や筋肉を形成したり細胞の新陳代謝を促進したりといった働きをするとき必要なエネルギーは、脂肪を分解し燃焼することで得られます。
ですから、ノンレム睡眠で成長ホルモンがたくさん分泌されると、たくさんの脂肪が分解され燃焼されます。つまり、十分な睡眠が太りにくい身体を作るのです。
睡眠時間が1日12時間以下の乳幼児は、就学前に過体重になるリスクが2倍あるといわれています。(出典『こどもとねむり』三池輝久 メディアイランド)

レム睡眠で起きていること
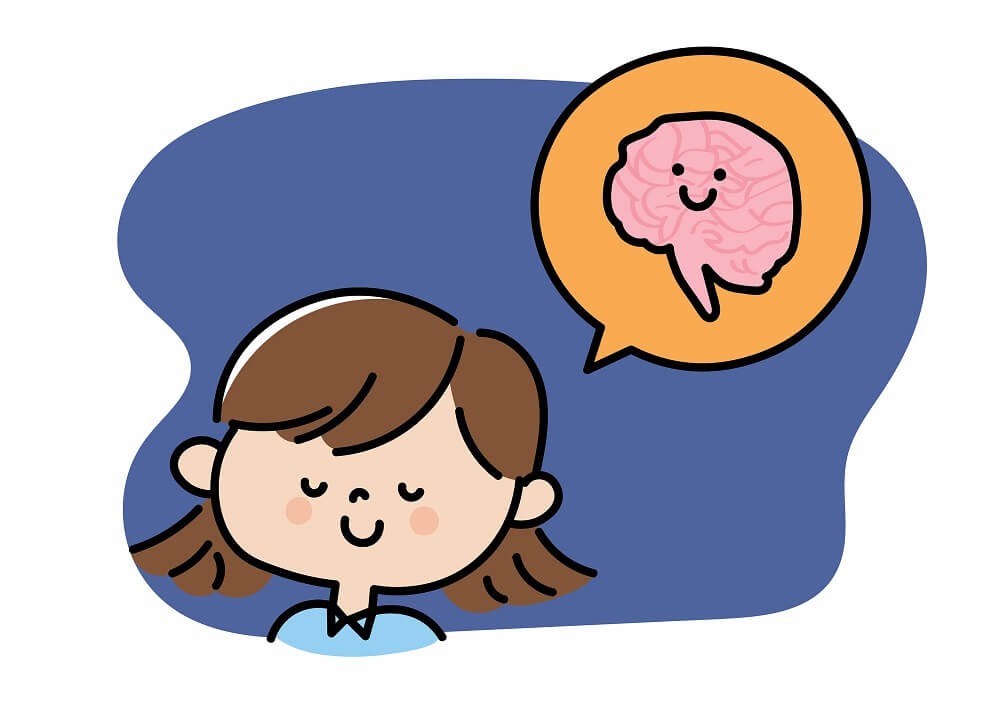
1 身体の休息
レム睡眠中、脳は活発に活動していますが、逆に筋肉は緊張しないようになっていて、体は動かないようになっています。レム睡眠中、身体は休息しているのです。そのため、レム睡眠は「身体の睡眠」ともいわれます。レム睡眠が不十分だと身体が休息できないので疲労がたまり、集中できない、注意散漫になりがちです。様々な疾病にもつながりかねません。
2 記憶の整理と定着
レム睡眠時に脳内では、日中に記憶したこと(学習や経験)を忘れないように脳に定着させる作業が行われています。東北大学の瀧靖之教授チームが、5~18歳の健康な子どもたち290名の「平日の睡眠時間」と脳のMRI「写真」を比較したところ「記憶にかかわる脳の海馬は、睡眠時間が長い子供のほうがより大きい」という結果が出たということです。
以上からわかるのは、ノンレム睡眠とレム睡眠をそれぞれ十分にとることではじめて、
●脳のメンテナンス
●成長ホルモンの分泌
●脂肪細胞の分解
●身体の休息
●記憶の整理と定着
など、子どもの発達や成長に必要なことが十分に行われるのです。こう考えると、前回お話した「良質の睡眠」の基準 である4つのこと、
- 睡眠前半に深睡眠 (ノンレム睡眠の中の睡眠段階4の深い睡眠) が確保されること
- ノンレム睡眠とレム睡眠の訪れるサイクルが安定していること
- 睡眠中盤から後半にかけてレム睡眠の量が確保されること
- レム睡眠が覚醒などで途切れないこと
「朝きちんと起きること」が大切な理由

それがなぜ大切かは、「セロトニン」と「メラトニン」という脳内物質の働きと関わります。
脳内物質「セロトニン」とは?
まず、セロトニンについて説明します。セロトニンは、衝動性や、悲観的な気持ちをコントロールする時に活躍する脳内物質です。十分なセロトニンは情緒を安定させます。「じっくり考える」という行為にも、セロトニンが大きく関わっています。
セロトニンは、朝の太陽の光が網膜に入り神経を刺激することで分泌されます。 ですから、「朝きちんと起きて朝の太陽の光を浴びる」ことが大事なのです。
脳内物質「メラトニン」とは?
もうひとつ大切なのがメラトニンです。メラトニンは睡眠をうながす物質であり、これが分泌されると眠くなります。メラトニンはセロトニンを材料に作られます。朝、きちんと起きて太陽の光を浴びると、セロトニンがたっぷり分泌されます。そして、そのセロトニンを材料として日中、メラトニンが作られます。
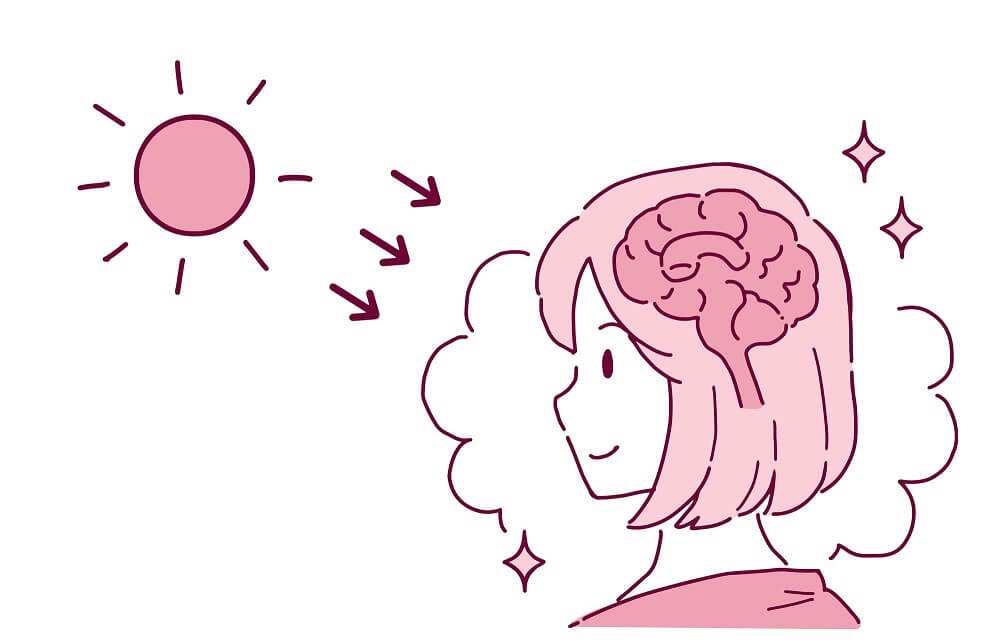
メラトニンは夜じゅう分泌されますが、翌朝太陽の光を浴びるとその刺激で分泌が止まります。そして目が覚めます。
メラトニンの分泌と分泌が止まることで人間は、眠る、目が覚めるという生活リズムが作られるようにできているのです。
「朝きちんと起きる」ことの効果
つまり、朝きちんと起きて太陽の光を浴びると、セロトニンがたっぷり作られる→メラトニンも十分作られ、夜になると分泌されて自然に眠くなる→朝になると分泌が止まり自然に目が覚める→規則正しい生活リズムができる、というわけです。ところが、朝きちんと起きて太陽の光をしっかり浴びることができないと、材料となるセロトニンが十分に生産されないのでメラトニンも少ししか作られません。
眠くならないのでなかなか寝付けない、寝付けないから朝起きられない、朝の太陽の光を浴びられないのでセロトニンができない…という悪循環に陥ってしまいます。規則正しい生活リズムもできません。
睡眠障害の診断基準とは?
今までお話したことから、いわゆる「良質な睡眠」そして、朝きちんと起きること、が子どもの成長、発達、情緒の安定にとっていかに大切か、がわかっていただけたのではないかと思います。では、子どもが必要な睡眠をちゃんととれているかどうか、睡眠に問題はないか、はどう判断したらいいのでしょうか。
乳児については睡眠障害の診断基準はないのですが、1歳以上の幼児については、次のような基準が考えられています。
|
幼児の「睡眠障害」の診断基準 ①なかなか入眠できない ②睡眠中、何度も目が覚めてしまうため睡眠がまとまらない ③一度目が覚めると1時間以上起きている ④睡眠時間が短い(9時間以内) ⑤不機嫌で泣いてばかりいる |
- 脳のメンテナンスや成長ホルモンの分泌がうまくいかない
- 合計の睡眠時間が少なく身体の休息や記憶の整理定着といったことが不十分
- メラトニン不足で規則的な生活リズムができない
前回と今回の2回にわたって、睡眠について知っておいていただきたい基礎的な内容をお話しました。次回からは「園でいつも眠そうな美空ちゃん」への具体的な支援方法を考えていきます。
▼合わせて読みたい!おすすめ記事