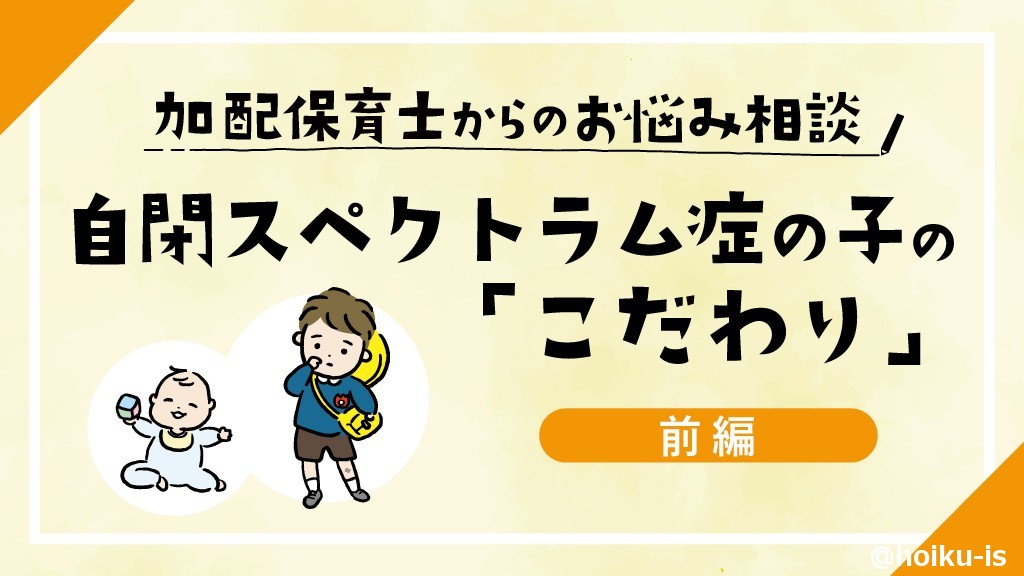今回の加配保育士さんからの相談

まず「こだわり」の種類を考えてみる
「こだわり」には、変えなくてもいいこだわりと変える必要があるこだわりがあります。子どもには、大人の目から見ると「なぜ?」と思うような「こだわり」があることはよくあります。
そして、発達障害のある子の場合、その「こだわり」が特に強いことがあります。その種類には、次のようなものがあります。
「こだわり」の種類一覧
| 常同行動 | 手指を奇妙に動かしたり、くるくる回るなどの全身運動を繰り返す |
| 自傷行為 | 自分を傷つける |
| 強迫行動・儀式的行動 | 特別に決められたやり方や順序でものごとをしないと気がすまない |
| 同一性保持 | 日課やスケジュールの変更を嫌がる 持ち物の位置や家の様子、人の髪形など環境の細かい部分が変わることに抵抗を示す |
| 興味の限局 | 奇妙なものに興味を示す ものに対して異常に強い興味や愛着を持つ |
具体的な行動を種類分けすると?
【行動とこだわりの種類分けの例】
- 手をひらひらさせる行動を繰り返す→常同行動
- 怒った時、拳で鼻を強く叩く→自傷行為
- ミニカーが大きい順に並んでいないと怒る→同一性保持
- 特定のキャラクターのスプーンでないと食事を食べない→強迫行動・儀式的行動
- くるくる回るミニカーのタイヤに固執する→興味の限局
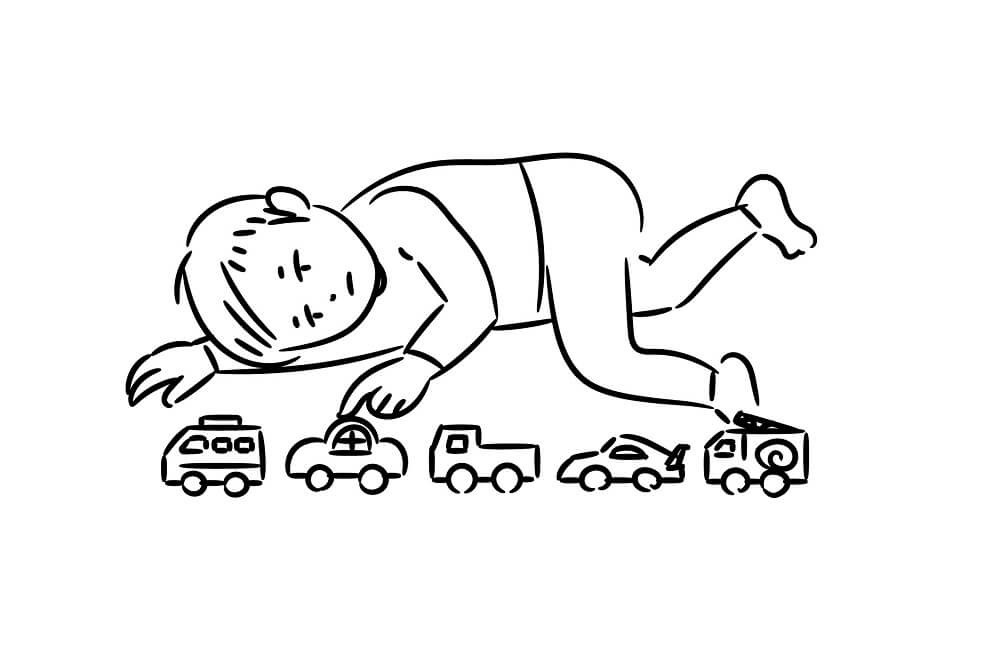
複数種類の「こだわり」の組み合わせも
なかには、複数の種類のものが組み合わさっている「こだわり」の行動もあります。 【行動とこだわりの組み合わせの例】- 夜中に長時間のドライブをしたがる→強迫行動・儀式的行動+同一性保持
- 特定の子どもと遊びたがり、相手が嫌がって泣いても、その子の手を引っ張って遊ぼうとする→強迫行動・儀式的行動+同一性の保持+興味の限局
- 保育園のドアの開閉ばかりを気にして、室内にいることができない→強迫行動・儀式的行動+同一性保持+興味の限局
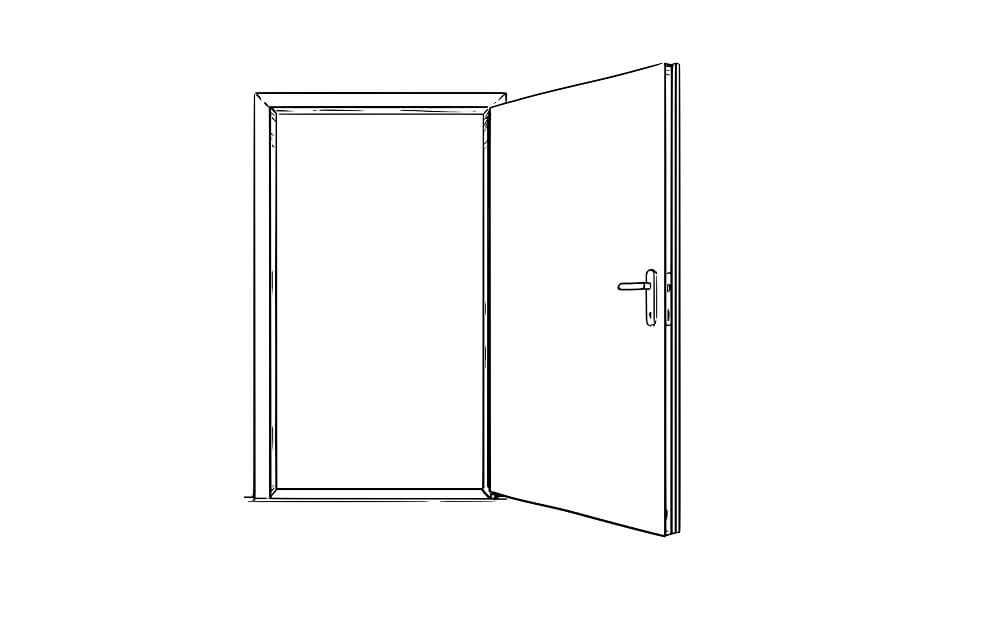
発達障害の子にとっての「こだわり」を知る
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。