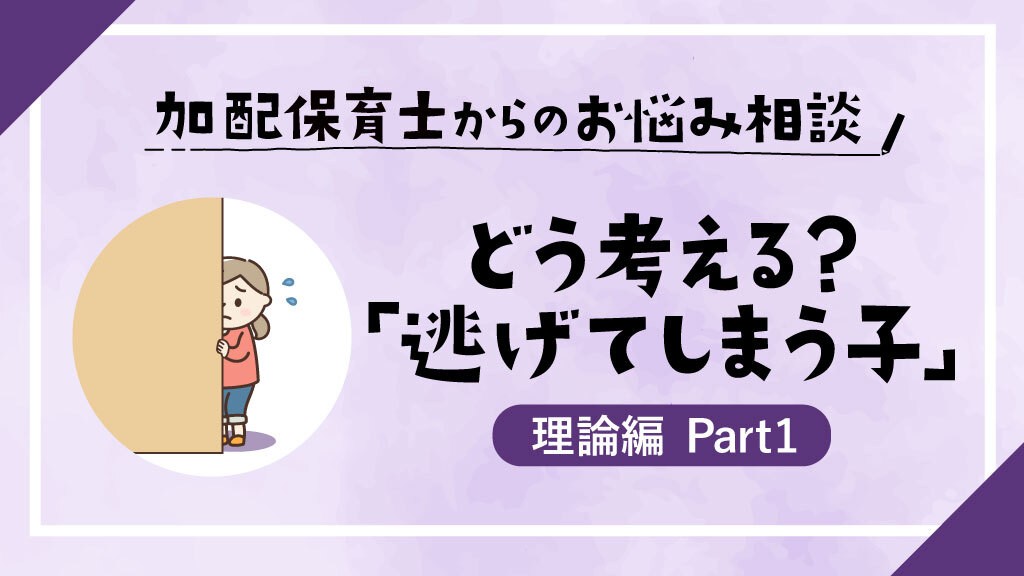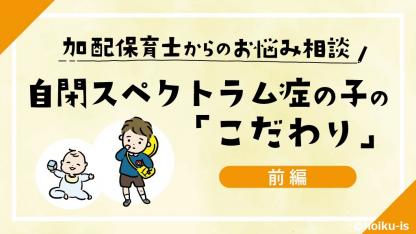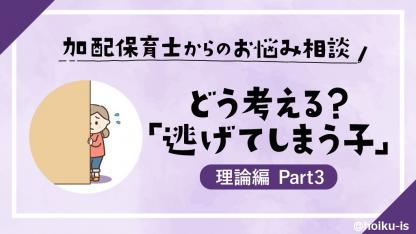【今回のテーマ】加配保育士さんからの相談
今月からは、加配保育士のルミ先生の悩みについて考えていきます。|
<ルミ先生のお悩み> 家ではお話をするのに、園ではひとこともお話をしない美知瑠ちゃん(4歳)との関係づくりがうまくいかないのです。 ルミ先生は今日も元気に明るく、美知瑠ちゃんとお母さんに挨拶をしますが、美知瑠ちゃんはお母さんの後ろに隠れてしまいます。 お部屋でも、ルミ先生が近づくと美知瑠ちゃんは逃げてしまいます。  |
しかし美知留ちゃんは、どうもルミ先生の「元気いっぱいの保育指導」が好きではないようです。ルミ先生が、美知瑠ちゃんとの関係をより良いものにするには、どうしたらいいのでしょうか?
まず「保育」の本質を考えてみる

今回のお悩みを考えるとき、解決策を見つける前に、改めて「保育」の本質を考えてから検討したいと思います。 今回から3回にわたって【理論編】の解説をしていきます。
最初にみなさんにひとつの問いを投げかけてみます。
「保育の場は、誰が どのような経験をすることをめざす所なのか?」いかがでしょうか。
厚生労働省の保育所保育指針は「保育の目的」について、次のように述べています。
| 保育所は、この時期の子どもたちの「現在」が、心地よく生き生きと幸せなものとなるとともに、長期的視野をもってその「未来」を見据えた時、生涯にわたる生きる力の基礎が培われることを目標として、保育を行う。その際、子どもの現在のありのままを受け止め、その心の安定を図りながらきめ細かく対応していくとともに、一人一人の子どもの可能性や育つ力を認め、尊重することが重要である。 ※保育の目標 (保育保育所指針P3(2)ア)より引用 |
保育所保育指針の「保育の目的」解説
ここで言われているのは、- 保育所は、子どもが「現在」幸せを感じる場である。
- 保育所は、子どもが「未来」のために学ぶ場である。
- 1と2を実現するために、保育所は、ありのままの子どもを受け止め、子どもを尊重する。
「保育の目的」考察
ここから言えるのは、まず保育の場は徹頭徹尾「子どものため」の場だということです。保護者や保育士のための場ではありません。ルミ先生のお悩みへの解決策前をお話しする前に、このことを確認していきたいと思います。
「保育の目的」の3つを満たすためには?
では1~3を満たすために、保育所はどうあらねばならないでしょうか。これについて私は、「一人ひとりの子どもの願いを叶える場であること」が最も大切だと考えています。
人は誰しも「願い」を持って生きています。
「願い」を叶えることができたとき、人は生きる喜びや楽しさを感じ、生きていてうれしい、と感じます。
それこそが「幸せ」だと私は思います。

子どもが自分の「願い」を叶える経験を通して、生きる喜びや楽しさを感じ、自分の周りにいる、他の子どもや先生との繋がりを感じられる場でありたい。
そのために保育士は、保育士と子どもの関係、子ども同士の関係を良好に築く必要があるのだと思います。
子どもはどんな「願い」を持っているのか?
ところで「子どもの願い」とは何でしょうか。私は子どもだけでなくすべての人は、
|
●尊重されたい ●安心したい ●信頼したい ●有能でありたい ●楽しみたい ●人とつながりたい この6つの基本的な「願い」を持っていると思います。 ※『発達障害のある子と家族が幸せになる方法』第2章(出版:学苑、2018/9/14発行、原哲也 (著)より引用。 |
すべての人がもつ「6つの願い」

年齢や性別、障害の有無に関係なく、ひとりの人間として尊重してほしいという願いです。
②安心したい
いつ何が起きて自分がどうなるかわからないという状態で人は何事も楽しむことも味わうこともできないし、何かに挑戦することも、人との関わりを作ろうとすることもする気にならないでしょう。だから人は安心したいのです。
③信頼したい
安心・安全の感覚を得る上で大切なのが、「信頼できる人がいること」です。何かあっても信頼するこの人が助けてくれる、と思えることで人は安心できます。

④有能でありたい
「自分にはできることがある」と感じたい、という願いです。人は「自分にはできることがある」と思うからこそ、周囲への興味関心を持ち、周囲に積極的に働きかけ、チャレンジし、その結果、成長します。
⑤楽しみたい
今を楽しみたいという願い、さらには気持ちの通じあう人と楽しみを共有したいという願いです。
⑥繋がりたい
人は一人では生きられません。ですから、他の人と繋がり、他の人と「共に」生きたいと願います。そして人と繋がることは、人が自分の「願い」を叶えるためにも必要です。

子どが「願い」を叶えるための保育者の関わりは?
先にお伝えした「6つの願い」を、子どもが叶えるには、大人(家庭であれば保護者、保育の場では保育士)の関わりが必要なことが圧倒的に多いです。特に、発達障害のある子の場合、特性ゆえのさまざまな制約から、彼らがひとりで自分の「願い」を叶えることは難しい場合が多いのです。
ですから、彼らが「願い」を叶えられるようにするには、「大人の適切な関わり」が必須なのです。

子どもの「願い」を叶えることを考えるとき、
| ★出発点 ①尊重されたい ②安心したい ③信頼したい まずはこの3つの「願い」です。 |
では、この3つの願いを充たすには、どのような関わり方が必要なのでしょうか。
次回は【理論編】の2回目「具体的な保育者の関わり」から解説し、お悩み解決の糸口を探って行きたいと思います。
(次回は2022年11月下旬に公開予定です)
▼一緒に読みたい!おすすめ記事