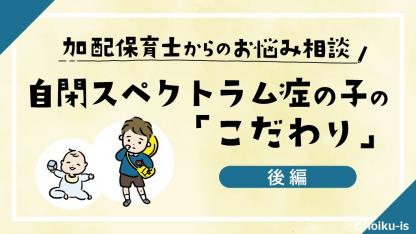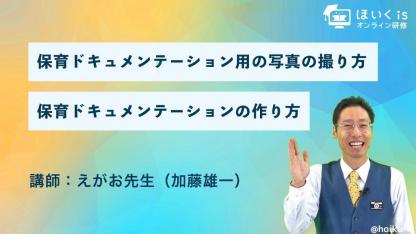今回は、子どもたちが大好きなシャボン玉です。発達障害のある子どもにとっては、楽しく遊べると同時に、療育の観点からもいろいろな意義があります。具体的な遊び方と遊んでいるときに意識しておきたい意義、遊び方のポイントを解説します。
1.シャボン玉遊びの遊び方

- ストロー式:ストローの先にシャボン液をつけ、ストローを吹いてシャボン玉を作る
- リング式 :リング状のシャボン玉器をシャボン液に浸してそれを大きく振ってシャボン玉を作る
「シャボン玉セット」の使用上の注意にしたがって、誤飲などに気をつけて遊びます。
2.シャボン玉遊びの意義

①しっかりと目を使う
発達障害のある子どもの中には、さまざまな視覚刺激や聴覚刺激に反応してしまい、一つのものを見つめたり、ターゲットとするものを目で追う経験に乏しい子どもがいます。シャボン玉遊びでは、そのような子どももシャボン玉を「じっと見る(固視)」「飛んでいく軌道を目で追う(追視)」経験をたくさんすることができます。
②共同注意
共同注意とは、「2人の人が同じものを見ること、注目すること」です。例えば、保育士が空を飛ぶ飛行機を見上げ、「ほら、飛行機だよ」と言い、子どもが同じ飛行機を見上げて、「本当だ!飛行機だ!」と言うようなことです。共同注意は、ことばの獲得の上でとても大切な行動で、定型発達児の場合、8~10か月の頃から始まります。
しかし自閉症スペクトラム障害の子の場合、「ほら、〇〇だよ」という人の投げかけに応じて、その時自分が注意を向けているものから注意の方向を変えて、別のものを見る、他の人と同じものに注目することが難しい、つまり共同注意が難しいことが多くあります。
この点、シャボン玉遊びは自閉症スペクトラム障害の子どもの興味を引くことが多く、共同注意を得やすいのです。子どもと周囲の人が同じシャボン玉に注目し、シャボン玉遊びを一緒に楽しむことができるようになります。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。