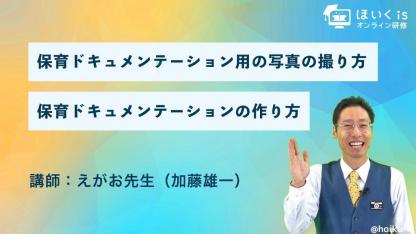魅力①:プロジェクト活動

1つ目の魅力は断トツで「プロジェクト活動」です。子どもたちの興味関心のあるテーマを見つけて、それを1学期間から1年を通じて探究していくというアプローチ。スウェーデンの多くのプレスクールで取り入れられています。
子どもの興味から始まっているので、子どもたちの主体的な学びが起こり、子どもたちの活動への参加や影響力を伸ばすのにとても有効です。
保育者達はプロジェクトを通じて、カリキュラムにある10の発達領域の力を子どもたちが伸ばしていけるように、計画、実践、記録、振返りを子どもたちと繰り返していきます。
そのプロセスそのものが乳幼児期の子どもの学びであり、それを糸で紡ぐように可視化したのがプロジェクト活動です。また、同じテーマを扱ったとしても何一つ同じになることはありません。先の見えない展開に保育者も子どもたちもワクワクしながら取り組めます。
以前に紹介した「りすのプロジェクト」のように、乳児クラスでも取り入れることができます。
>>プロジェクト活動の記事はこちら
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。