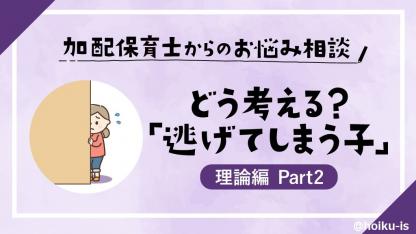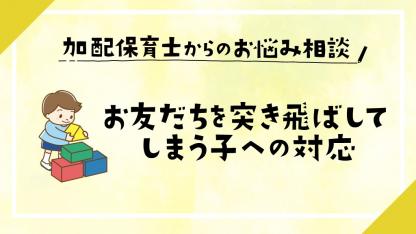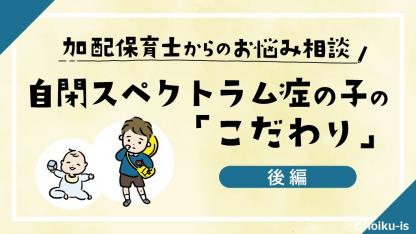前回のおさらい
紙芝居のときに友だちを叩いてしまう竜星君。「乱暴な子」として対応するのと、『だから、だってフォーム』を使って対応するのと、竜星君にとっては何がどう違うのでしょうか。保育の仕事とは
そのお話の前に、そもそも保育の仕事の目的は何か、言い換えると「子どもにどういう経験をしてもらうことが保育士の役目か」を皆さんに問うてみたいと思います。どうですか?「集団生活が送れるようにする」「身辺自立」など、いろいろな考えがあるでしょう。
どれも間違いではありません。
でも私は、最も優先されるべきなのは、子どもの中に
- 自分を好きという感覚
- 家族や友だちや周りの人を好きだという感覚
この感覚は、子どもがその子らしく生きていく上でも、社会で人と共生していくために必要なことを学ぶ上でも、ベースになる大事な感覚です(「③人の役に立つことができる」感覚も非常に重要だと私は考えますが、それはまた別の機会に)。
だとすれば、保育ではあらゆる場面、あらゆる関わりにおいて、子どもの中に「自分が好き」「人が好き」という感覚を育てることを目指さなければなりません。翔太君を叩く竜星君への対応においても、「自分が好き」「人が好き」という感覚を育てることを一番に考えるのです。
「自分が好き」「人が好き」を育てる対応とは
この点、2つの対応はどうでしょうか。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。