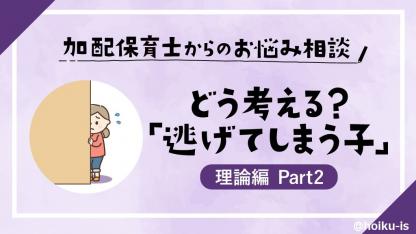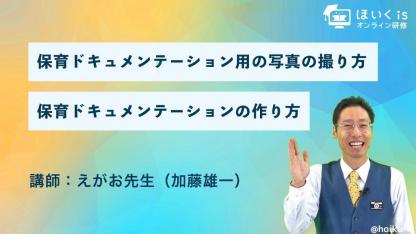今回のケースは?
今回は給食のとき、食べ物を机から払い落してしまう子のケースです。小太郎君は4歳の男の子。まだ、おしゃべりができないので、何かしてほしいときは、指差しや保育士の手を引いて伝えます。
さて、大好きなお給食の時間です。
小太郎君は食べることは大好きですが、嫌なものがあるときは大変です。お皿ごと机からはらい落としてしまうのです。
今日も、ニコニコ顔で自分の席に着きましたが、おかずのお皿を見たとたん、小太郎の顔つきが変わりました。
「バーン」。怒った顔でおかずの皿を机から払い落とします。
保育士はこの子の状況をどう捉え、どう考え、どう対応したらいいでしょうか?
『だから、だってフォーム』=「僕、○○だから机からお皿を払いとしちゃうんだ。だって、机からお皿を払い落とすと●●なんだもん。」を使って考えてみてください。
『だから、だってフォーム』で仮説を立てる
まず、これまでお伝えしたことを復習しましょう。- 保育の目標は、子どもの中に、「自分が好き」「人が好き」を育てること
- 子どもの中に「自分が好き」「人が好き」という感覚を育てることは、子どもが周囲との「つながり」や「信頼」の感覚を育てる基盤となり、他の場面での対応にもつながる
- 「自分が好き」「人が好き」を育てるには、「事後対応」ではなく「予防的な対応」が重要
- 予防的対応をするために『だから、だってフォーム』を使う
- 『だから、だってフォーム』を埋める際は、①静かに ②その行動だけでなく普段の様子を観察し、③子どもの気持ちを想像しながら理由を考える
「僕、どうしても机からお皿を払い落としてしまうんだよ。どうしたらいいの? 本当は僕もみんなと楽しく給食を食べたいのに、先生に褒められたいのに…」
『だから、だってフォーム』=「僕、○○だから机からお皿を払い落としちゃうんだ。だって、お皿を払い落とすと●●なんだもん。」を使って仮説を立て、対応策を考えてみてください。いかがですか?
仮説1
「僕、苦手なものだけ除けたいけどやり方がわからないんだ。だから机からお皿を払いとしちゃうんだ(〇〇)。だって、そうすれば苦手な食べ物が遠くにいくから食べないですむもん(●●)。」
対応:ランチマット(赤や黄色など、小太郎君が苦手、嫌いというイメージを想起しやすく、注目しやすい色が良い)などに「苦手です」「食べられません」の意味の「✖」を書き、その上に食べられない食材を入れるお皿を置く。
小太郎君は苦手な食べ物を「苦手です」の皿に入れる。お皿に残った食べられる食材を食べる。最初は保育士が小太郎君に「これは食べられるかな?」などと声がけをしてサポートするが、少しずつ小太郎君が自分でできるようにしていく。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。