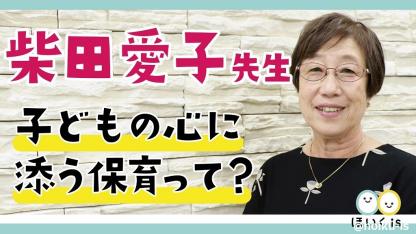「子どもの心に添う保育」って?
「子どもの気持ちを尊重して」「一人ひとりに寄り添って」ということは、どの保育者も一度は先輩に言われたり、保育を学ぶ中で耳にしたりしているのではないでしょうか。しかし実際に現場に立つと、「たくさんの子どもたちがいる中で、どうやって一人ひとりに寄り添えば良いのか…」「子どもの気持ちを尊重したいけれど、危険なことは叱らなければ…」と、どうすれば良いのか分からなくなることも多いですよね。今回のWebセミナーのテーマは『子どもの心に添う保育って?』。“子どもに関わるトータルな仕事をする場”として創設された「りんごの木」代表の柴田愛子先生にご登壇いただきました。
保育人生50年を迎える柴田先生の経験の中で起きた実際のエピソードや教訓を織り交ぜながら、先生が考える「子どもの心に添う保育」についてお話しいただきました。明日からの保育に繋げられる、学びと気付きがたくさん詰まったおすすめの内容です。
| ※『ほいくisオンライン研修』は、保育に役立つさまざまな情報を配信する保育者向け動画プラットフォームです。動画は、ほいくisメンバーまたは園会員の登録(無料)をするだけでいつでも視聴できます。 ぜひこの機会にメンバー・園会員登録をして、園内研修や勉強会、個人の学びなど、さまざまな取り組みにご利用ください。 >>ほいくisオンライン研修はこちら |
「寄り添うこと」は「保障すること」ではない
Webセミナーの公開に合わせて、収録後の柴田先生にインタビューをさせていただきました。今回のセミナーテーマ『子どもの心に添う保育』に関して、保育者さんが現場で抱える悩みについて質問してみました。子どもたち一人ひとりに寄り添いたいという想いは、どの保育者も持っていると思いますが、実際は集団生活の中でそれをするのは難しいこともあります。どうしたら良いでしょうか?
寄り添うということは、「一人ひとりを分かってあげる」とか「子どものやりたいことを保障してあげること」ではないんです。
以前、保育現場でこんなことがありました。お父さんが単身赴任していてなかなか会えない男の子が、月曜日にお父さんが送ってくると別れ際に泣くんです。そのとき、その子の隣にそっとお友だちが座っていました。そして男の子は泣くだけ泣くと、隣にいたお友だちと一緒に遊びに行きました。

|
柴田 愛子(しばたあいこ) 1948年東京都生まれ。保育者。りんごの木代表。幼稚園教諭や自主保育グルー プの保育者、保育雑誌の編集などを経て、1982年「子どもの心に添う」を基本姿勢 とした「りんごの木」を発足。子どものドラマを描いた絵本『けんかのきもち』(伊藤秀男/絵)が、2001年日本絵本大賞を受賞。講演・執筆・絵本作りと様々な子どもの分野で活動中。子どもたちが 生み出すさまざまなドラマをおとなに伝えながら、子どもとおとなの気持ちのいい関係づくりをめざしている。 ●りんごの木ホームページはこちら |
子どもたち一人ひとり違うのに、全員を理解するのは難しいですよ。その中で、“いま気になる子”に寄り添ってそばにいるだけで良いんです。「どうしたの?」と聞くのは、乱入しすぎかもしれませんね。
「寄り添うこと」は、子どもの気持ちを受け止めて理解することだと思っていたので、「何もしなくて良い」という視点は、私自身新たな気付きでした。自分の味方をしてくれる人がいるという安心感は、子どもも大人も同じ気持ちなんですね。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。