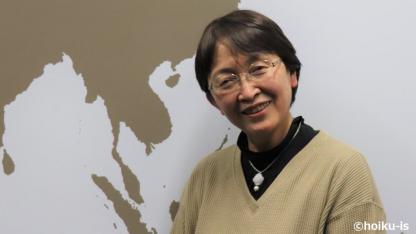「子ども主体」の意味をもう一度考える
「子ども主体の保育を実践しよう」という動きは、近年多くの園で見られます。しかしその取り組みの中で、- 「子ども主体で保育をすると、園生活での規律との線引きが難しい」
- 「わがままと子ども主体の違いは?」
- 「具体的に保育者は何をすれば良いの?」
ほいくisメンバーと園会員向けに配信をしている『ほいくisオンライン研修』では、このような課題感を受けて、『子ども主体の保育をどのように具体化していくか~特に発達過程、環境による保育に注目して~』と題した講座をお送りしています。
登壇者はこの分野の第一人者であり、講演や執筆、メディア出演など多方面で活躍中の汐見稔幸先生。長年にわたり保育業界の変遷を見てきた先生ならではの視点から、これまでと現代の保育の違いや、本来的な意味での「子ども主体の保育」で大切なこと、現場で実践するために必要なことなどをお話しいただきました。
今回のインタビューは、収録直後の汐見先生に、セミナーのテーマに関連したさまざまな質問にお答えいただきました。
| ※『ほいくisオンライン研修』は、保育に役立つさまざまな情報を配信する保育者向け動画プラットフォームです。動画は、ほいくisメンバーまたは園会員の登録(無料)をするだけでいつでも視聴できます。 ぜひこの機会にメンバー・園会員登録をして、園内研修や勉強会、個人の学びなど、さまざまな取り組みにご利用ください。 >>ほいくisオンライン研修はこちら |
「子ども主体の保育」の実施が約7割

事前に公式Instagramでアンケート調査を実施したところ、子ども主体の保育を「推進している」「どちらかというとしている」と答えた保育者の割合が約7割(※)に上りました。この状況についていかがでしょうか?
保育所保育指針の策定に関わった私たちからすると、「ようやく7割まできてくれたな」という気持ちです。実は「子ども主体の保育にしていこう」となったのは、既に30年近く前なんです。しかしなかなか実態は変わらず、子ども主体の保育を実践しようとした園では、「子ども主体」ではなく「放任」になってしまうなど、混乱もありました。子ども主体の保育が「放任保育」と間違われることは今でも度々ありますね。この違いが理解されていくにはもう少し時間がかかるのではないでしょうか。
どこまでを「子ども主体」とするのかで迷っている保育者も多いと感じられます。「子ども主体」と「放任」の線引きについて、今一度考えていきたいですね。 セミナー本編では、汐見先生が考える「子ども主体」の定義について、分かりやすくお話しいただいていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
| ※<アンケート調査について> 調査期間:2022年10月4日(1日)/調査方法:Instagramでアンケートを実施/調査対象:Instagramユーザー/有効回答数:1問目「Q.お勤めの園では、 『子ども主体の保育』を推進していますか?」2,096件、2問目「Q. 『子ども主体の保育』を実践する上で課題に感じていることは?」133件(フリー記述) |
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。