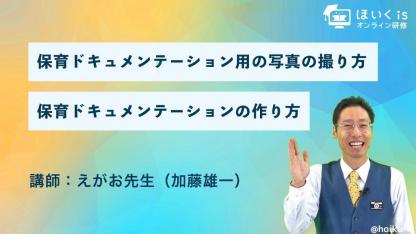「寄り添う」前に「信用」を

保育園や幼稚園に通う年齢の子どもは特に、うまく言葉が出ないことからお友達に手が出てしまったり、大声を出してしまったりということも多いと思います。保育者はこのような子どもたちの言動に隠された想いに寄り添うことが大切ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
寄り添う前に、目の前の子どもが信用してくれへんとあかんと思います。今は、「子どもに寄り添うには」という研修まで行われていますが、決めるのは子どもですよ。寄り添うが先走りしているのですね。
そうです。子どもが安心するかどうか、ですよ。では、子どもが安心する大人ってどんな条件やったらいいのかっていうと、「丸ごと受け止める」ということ。お漏らしをしようと、先生なんか嫌い! と言おうと、まだお部屋にはいりたくないって言おうと。「そうなんや」と受け止めた後に、「なら、どうする?」って答えを、その子に教えてもらうしかないんですよ。
でも、「まだ遊びたい」という子どもに「ダメ! みんなお部屋にはいっているのに〇〇くんだけそんなこと言っていたら迷惑でしょ!」って言って、この子はマル、この子はペケって答え合わせしてしまっているんですよね。
子どもの想いを受け止めて一言声をかけるだけでも、安心感はまったく違いますね。
そうですね。分かった、なるほど、そうなんやって、まずはそこからです。保育士や教師の仕事は、目の前の子どもたちが安心して「この人になら困ったことが言える」と思ってもらえる土俵がない限り、成立しません。自分が寄り添おうとしてスキルを高めたり研修をすればするほど、「こんなに努力しているのになんでこの子はこっちを向いてくれないんや」って思うだけではないですか? そうすると「話を聞けないこの子は発達障害だ」って。「私のせいではない」って思ってしまうんです。
私が見た場面ですが、現場である子どもが他の子と別のことをしていても、受け止める前に「あの子は“グレー”だから当たり前」という空気で、保育士が線を引いていることがありました。
それでは保育園に来る必要がないですよ、ひとりで過ごすなら。「あの子は発達障害で、あなたたちは“ふつう”やから、あなたたちが我慢して」って、ここでもう子ども同士の関係性が分断されているんですよね。集団生活の中での関わりはすごく大切ですが、その機会を大人が分断してしまったら育つ場がなくなってしまいますね。
主語が全部「大人」で、みんな評価を気にしているからです。“ダメ先生”になりたくないんですよ、誰でも。でも、保育士の目的はなんですか? 子どもが安心することでしょう。先生が安心したいのではいけませんよね。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。