創設から7年目のキャリアアップ研修
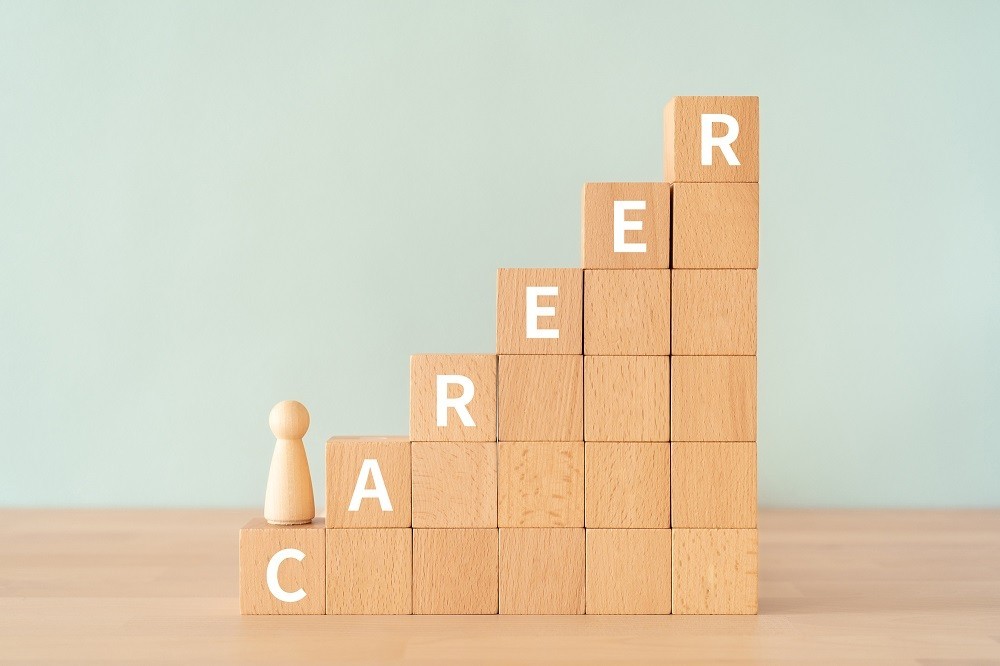
この間、コロナ過で普及が停滞した時期もありましたが、保育士の受講や、園で役職を設けての運用が進むなど、本格的に制度が現場に浸透していくフェーズに移りつつあります。
そこで今回は、制度創設時に中心的な役割を果たされている東京大学名誉教授の汐見稔幸先生に、ここまでのキャリアアップ研修制度の評価と、今後に向けての展望についてお伺いしました。
制度創設の背景と経緯
まずは、そもそも「保育士等キャリアアップ研修」制度がどのような経緯で作られたのかについてお聞きしました。研修制度創設の背景

まずは、保育士等キャリアアップ研修制度が創設された背景についてお聞かせください。

もともとは、待機児童問題で保育園を増やすために、保育士の給料も上げて保育士を増やすということで、国の方で議論が始まったことがきっかけでした。
その際、大きく分けて「保育士」と「園長」という保育園の組織構成をより良く出来る、という話がありました。もちろん「主任」もありますが、役割がはっきりとしていない面もあります。

階層が少ない保育園の組織構成が改善点として出てきた訳ですね。

そうですね。要するに、保育士が頑張って仕事をし、勉強をしてスキルアップしたら職位や職階が上がっていく。そんな制度にしていきたいのです。企業で言うと、係長になった、課長になったという形で、責任も取るけど任されていく「ラダーシステム」と呼ばれる仕組みですね。
「小さな職場だから、全員が対等なのも良いじゃないか」という考え方もありますが、より現代的な組織のやり方を入れていった方が良いだろうと。
そういった経緯で、「頑張って何年か勤めて研修をしっかりと受ければ、身分が上がって給料も上がる」というシステムを作る議論が始まった訳です。
何が検討されたのか

制度を具体化する検討プロセスの中では、どのようなことが議論されたのでしょうか?

方向性については教育再生実行会議という組織で決められていましたが、具体的に制度をどうするかという検討は、厚生労働省の保育課の中に作られた委員会で進められました。そこの責任者を私が担いました。
そこでは、「何科目を受けたら良いことにするのか」「その科目を何時間受けることにするのか」「その中で学ばなければいけないシラバスは何するのか」といったことについて議論をしていきました。

議論をする中で、何か課題点はあったのでしょうか?

現行の制度では1科目あたり15時間以上が要件となっていますが、最初に私たちが出した案では15時間どころではなく、もっと多かったんです。給料が上がるようにするのであれば、それなりの時間をかけて勉強をしてもらう必要があるという考え方でした。
ところが、保育士も仕事をしながら受講をしていくので、あまりに長すぎると制度として上手くいくか分からないという話がありました。それを受けて、乳児保育や障害児保育、幼児保育など、取ってもらわなければいけない科目や、「これくらいはやってもらわないといけない」という時間を整理しました。
そういった経緯で「1科目15時間以上」という時間が決まりました。本来的にはもっと時間をかける方が望ましいですが、保育現場との折り合いをつける形で着地させたというところです。
キャリアアップ研修の現在地
続いて、現状の保育士等キャリアアップ研修の評価についてお聞きしました。キャリアアップ研修の課題

実施団体など、現在の研修制度の枠組みについてはいかがでしょうか?

制度ができた時、研修を自治体が主催するということまでは決められましたが、どういった団体に研修の実施を依頼するかについては決められていませんでした。
この点について熱心な自治体から相談を受けたこともありますが、例えば養成校であれば高い質の研修をしてくれるだろうけど、忙しくて引き受ける余裕が無いという事情があります。一方で、特に都市圏には研修をする団体や会社などがいろいろあると。今は自治体が「手を挙げてください」という形になっていますが、そういったところに頼むということが多くなりました。

その部分について何かしら今後に向けた余地はあるのでしょうか?

地域によっては、そもそも研修ができる団体や会社がまだ限られているという事情があります。保育の研修をした実績がないところが、現場のことを分からないまま実施することで、受講した先生方から不満が出るというケースも実際はありました。
そういう段階を経てきて、現在は「実りある研修にするにはどうしたら良いのか?」というのが次の段階へのステップだと感じています。
保育士として何年か働いている人であれば、必ず問題意識は持っているはずです。「遊びについてもうちょっと面白い指導ができるようになりたい」「絵画指導について勉強したい」とか。そういうテーマを持っている人たちに対して、まったく関係のない講義を一方的にするというやり方は止めて、学びにつながる形にした方が良いのではないかと思います。
実りある研修に変えていくには

先生がおっしゃる「実りある研修」に変えていくためには、どうしていくのが良いとお考えでしょうか?

“キャリアアップ”と言うのであれば、「自分がこういうことをできるようになりたい」というものを出してもらってから進める。そういう形にしていくというのはあります。
例えば、15時間のうち最初の3時間は、「保育の質を上げるためにはどういう勉強をしなければいけないか」「どういうことができるようにならなければいけないか」といったテーマに対して、受講者がこの1~3年で何にチャレンジしたら良いのかを議論して決めてもらうと。
そこで「同僚性を高めたい」「ベテランと若手が上手にやれるような職場を作りたい」といったテーマができたら、一度園に持ち帰って園長や主任と相談する。そして取り組む内容が決まったら、再び次の研修の場で持ち寄ってまた議論すると。またその次では、「成果はどうだったの?」「なかなか出来ないよ」と進めていく。
“往還型”とも言いますが、要するにキャリアアップ研修の場で園での取り組みを練っていくんですね。そういう研修にしていくと、実際の成長に繋がるのではないかということです。
このやり方は、実はキャリアアップ研修に課題感を持った関東学院大学のグループの取り組みの事例なんです。15時間続けて講義をするのではなく、テーマを自分で決めて、それを職場で実践し、また持ち寄って議論する。15時間の間に、少なくとも「ここはちょっと変わった」という研修にしていければ、より意味のある研修になるんじゃないかという課題感ですね。

せっかく作られた仕組みなので、役に立つものにしていきたいという動きが出てきている訳てすね?

現場の方から、そういう形での取り組みが増えてきました。
キャリアアップ研修の未来

保育士養成システムとの兼ね合い

キャリアアップ研修が今後どうなっていくべきかについて、汐見先生はどうお考えでしょうか?

このことを丁寧に議論していくと、保育士の養成システムそのものの今後の発展にまで及ぶと考えています。
今のように社会の変化がものすごく速い時代に、人を育てる専門家・専門職がずっと勉強をし続けていく。そんな動機付けができるようなシステムをどう作るかというところが重要になっている訳です。

養成システムとの関連について詳しく教えてください。

子どもを育てるということが難しくなってきている中で、保育士は高度な専門職として位置付けられる必要があると考えています。誰でもできる仕事ではないということをはっきりさせなければいけない。
しかし現状は、看護師や介護福祉士などと違って、国家資格の中で保育士だけが唯一「保育士法」といった法律が無い状態になっている状況です。ここをどう発展させていくかが今後のテーマになっていくと思います。
法律ができて保育士が高度な専門職ということが明確になれば、「計画的にこういった研修を取る」ということも明記されていくようになり、成長させていくためのプロセスも描きやすくなりますよね。
こういった議論が並行して進んでいけば、キャリアアップ研修をどうしていくのか?ということも、今とは別の地平での議論になっていくと思います。

保育士の地位や給料を上げていくことと、専門性向上の取り組みは同時に行っていくべきということですね。

そうですね。ちなみにヨーロッパでは、幼稚園・保育園の先生の給料と小学校の先生の給料はほぼどこも同じになっています。
今後のキャリアアップ研修に求められるもの

今後のキャリアアップ研修に求められることについてはどうお考えでしょうか?

乳児保育や幼児保育、障害児保育っていう現行の枠をそのままキープするのか、それとももう一回シャッフルしながら考えていくのか。キャリアアップする時に必要な学びの枠を、もう一回作り直していく。そこが重要になってくると考えています。
例えば、発達の捉え方について最新のものはどうなっているのか?とか、脳科学では人間の発達をどう説明しているのか? 発達障害について新しく分かってきたことは何か? 世界の保育がどの方向に向かって変わっていっているか? といったことをどう学んでいくかですね。

アップデートされた情報や、より専門性の高いものをどう取り入れていくかということですね。

また、現場を預かっている人たちがどんな研修を求めているのかという声を聞いていくのも今後の課題です。制度も7年やっているので、必ず何らかの問題意識は出てきているはずですが、そこをきちんと調査して、研修内容を作るということをやっていきたいと思います。

例えばどんなことが考えられるでしょうか?

保育者が経験から感じ取った悩みや問いを持ち寄り、意見を出し合いながら解決していく。そのためにキャリアアップ研修がある。そういうことをもう少しはっきりと示した方が良いと思います。
知識をブラッシュアップしていくこと、実践上抱えた課題を丁寧に吟味し合うこと、この時代にふさわしいテーマを改めて学び直すこと。そういうことがこれからの課題になっていくんじゃないかなと思います。

汐見先生、今日はありがとうございました。
今後の研修制度の動向に注目
今回は汐見先生に、『保育士等キャリアアップ研修制度の未来』というテーマでお話を伺いました。制度創設から7年が経ち、さまざま課題が見えてきている現状がある一方で、より良い形にしていこうという動きもあることがよく分かりました。今後、キャリアアップ研修制度がどのように進化していくのかについては、引き続き注視していきたいと思います。
汐見稔幸(しおみ としゆき)
一般社団法人家族・保育デザイン研究所 代表理事
東京大学名誉教授・白梅学園大学名誉学長・全国保育士養成協議会会長・日本保育学会理事(前会長)
専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学。自身も3人の子どもの育児を経験。保育者による本音の交流雑誌『エデュカーレ』編集長でもある。持続可能性をキーワードとする保育者のための学びの場「ぐうたら村」村長。NHK E-テレ「すくすく子育て」など出演中。
<著書>
・『新時代の保育のキーワード 乳幼児の学びを未来につなぐ12講』2024年(小学館)
・『見直そう!0・1・2歳児保育 教えて!汐見先生 マンガでわかる「保育の今、これから」』2023年(Gakken)
・『汐見先生と考える こども理解を深める保育のアセスメント』2023年(中央法規出版)
・『子どもの「じんけん」まるわかり』2021年(ぎょうせい)
・『教えから学びへ』2021年(河出書房新社)
・『今、もっとも必要な これからのこども・子育て支援』2021年(風鳴舎)
・『エール イヤイヤ期のママへ』2021年(主婦の友社)
・『エール プレ思春期のママへ』2021年(主婦の友社)
・『保育者のためのコミュニケーション・トレーニングBOOK』2019年(ぎょうせい)
・『0・1・2歳児からのていねいな保育』 全3巻 2018年(フレーベル館)
・『汐見稔幸 こども・保育・人間』2018年(学研)
・『「天才」は学校で育たない』2017年(ポプラ社)
・『人生を豊かにする学び方』2017年(筑摩書房)
・『さあ、子どもたちの「未来」を話しませんか』2017年(小学館)、ほか多数。
保育ラボ/家庭ラボ by(一社)家庭まち創り政策ラボ
●保育/家庭ラボHP
https://katei.labo.jp/



































