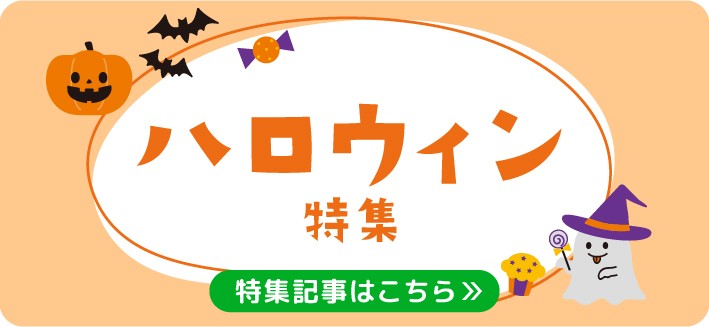マルバツクイズとは
誰もが一度は見たことのある定番の遊び「マルバツクイズ」。テレビのクイズ番組で出題されていることもありますよね。保育の現場では、遠足でのバスレクや、大きな行事での出し物として行うことが多いのではないでしょうか。もちろん日々の保育でも使えます。保育園や幼稚園、こども園で取り入れる際には、子どもたちにとって身近な事柄を問題にすると盛り上がるのでおすすめです。出題者の腕次第で子どもたちの熱中度が変わるので、明るく面白く出題できると良いですよ。道具なしで遊べるので、事前の準備が不要なのが嬉しいですね。
難易度
★★★★☆対象年齢
4歳児/5歳児用意する物・道具
- マルを描いた画用紙・バツを描いた画用紙 ※エリア分けを分かりやすくするため。なくてもよい。
遊びのねらい
保育園や幼稚園、認定こども園での遊びの活動では、ただ単に保育のひきだしの一つとして遊びを行うだけでなく、「ねらい」を意識して取り入れるようにしましょう。そうすることで、月案や指導案の作成にも役立ちますし、子どもたちの成長を促すことにもなります。- 遊びを通して人とかかわる楽しさや面白さを知る
- 勝ち負け関係なく楽しむ心を育む
遊び方・ルール
①大人数で集まり、問題の出題者を決めます※始めは保育者が出題者になるのがおすすめです
②出題者が、「赤信号は、止まれである。マルかバツか?」のように、マルかバツかで答えられる問題を出題します
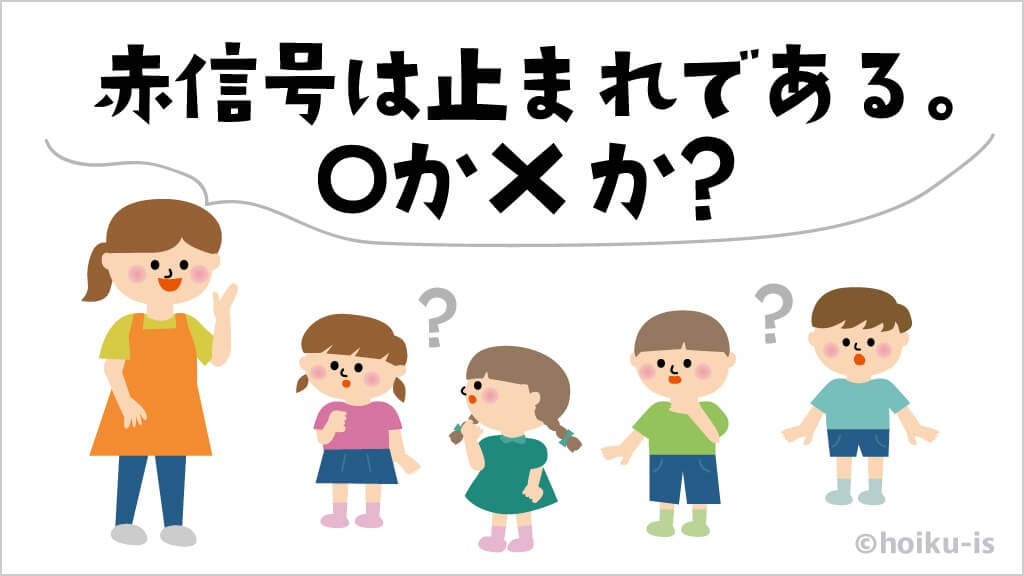
③回答者は、答えを予想して、マルとバツに分かれます

④正解を発表し、不正解だった子は抜けて応援に回ります
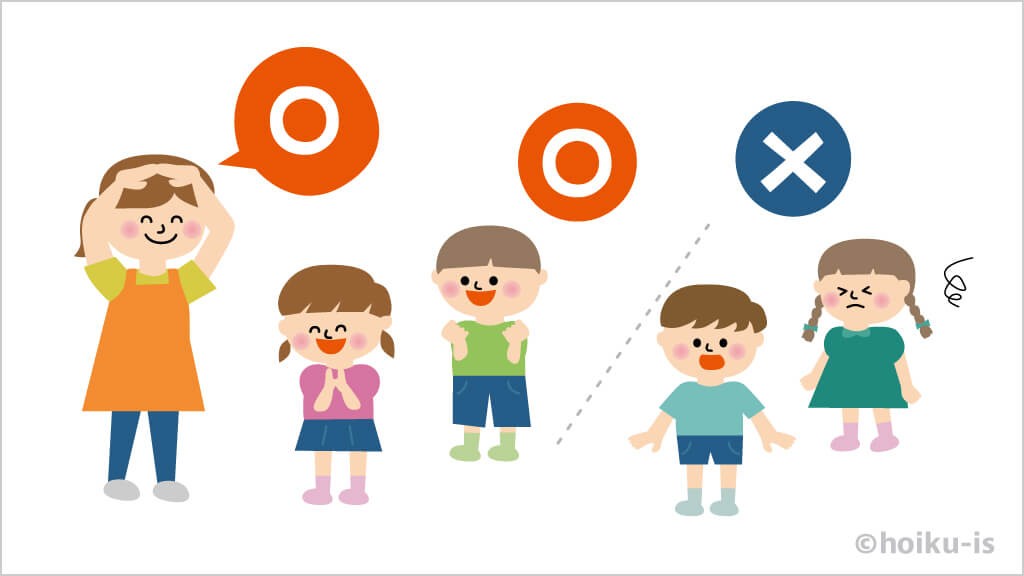
⑤②~④を繰り返して、最後まで残ることができた(正解し続けることが出来た)子が勝ちです!

ポイント
空間の区切りをしっかり作る
マルの子が集まるエリアと、バツの子が集まるエリアを離して、区切りをしっかり作るようにしましょう。中には、正解したい気持ちが強くて答えが発表された後にもう一方のチームに移動してしまう(ズルしてしまう)子も出てきますが、区切りがしっかりとあると防ぐことができます。また、ズルする子が居ても、他の子が注意したり怒ったりと、子どもたち同士で解決することもできます。「遊びを通した関わりの中でルールの大切さを学ぶきっかけになる」と捉えることもできますね。
座ったまま遊ぶこともできる
マルとバツで分かれるような広いスペースがないときや、席に座ったまま遊びたいときは、手で大きくマルとバツのジェスチャーをして回答する方法がいいですよ。遊びにかけられる時間や、スペースの大きさで判断してみてください。アレンジ例
ポイント獲得制のルールにする
間違えたら抜けていくのではなく、正解した子が1ポイント、というルールにすると、「今自分は何ポイントだっけ?」と数を数える練習になります。また、最後まで全員で遊ぶことができるのも魅力です。新年の自己紹介に応用する
「ご飯を食べるときの挨拶は『いただきます』である。」など、みんなが分かる問題に慣れてきたら、徐々に答えを想像する問題を出していくのもおすすめです。特に新年度には「○○先生の好きな色は赤である。マルかバツか?」「○○ちゃんの好きな動物はねこである。マルかバツか?」のように、遊びを通して先生やお友だちのことを知るきっかけにすることもできますよ。ピコピコテレパシーで遊ぶ
低年齢児の場合、「ピコピコテレパシー」というゲームで遊ぶのがおすすめです。手遊び歌を歌いながら「食べられるもの」か「食べられないもの」かを予想しカードを裏返すと答えが分かる、という遊びです。あらかじめイラストカードを準備しておく必要はありますが、答えが視覚でパッと認識できると子どもたちがより理解しやすくなるというメリットがありますよ。ピコピコテレパシーの歌詞は以下の通りです。歌詞
>>歌詞はこちらのサイトで確認作詞: 阿部 恵
作曲:宮本 理也
チーム戦にする
2チームに分かれて、最後まで残った人数で競ったり、親子でペアになって一緒に参加するのも楽しいです。お友だちや家族と協力することで、協調性や社会性を育むことができますよ。※掲載イラストや記事内容の 無断転載・二次利用、配布・加工は禁止とさせていただきます。
【関連記事】