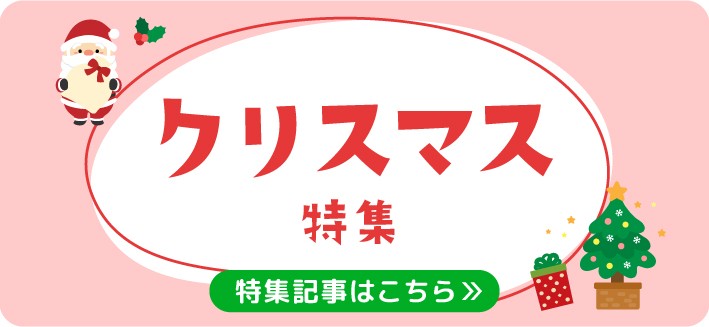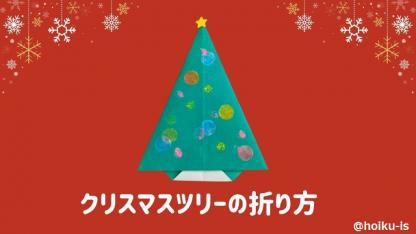布を使った遊びとは
タオルやガーゼ、シフォンなど保育園にはたくさんの種類の布があります。そんな布を使った遊びはいかがでしょうか?大きさや手触り、素材が違うことでいろいろな楽しみ方ができます。ねんねのお子さんから一人で遊べる幼児クラスの子どもたちまで楽しく遊べる遊びをご紹介します。難易度
★★☆☆☆対象年齢
0歳児/1歳児/2歳児/3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具
- 布(シフォン、シルク、タオル、手ぬぐい、ちりめんなど)
遊びのねらい
保育園や幼稚園、認定こども園での遊びの活動では、ただ単に保育のひきだしの一つとして遊びを行うだけでなく、「ねらい」を意識して取り入れるようにしましょう。そうすることで、月案や指導案の作成にも役立ちますし、子どもたちの成長を促すことにもなります。- 布(タオルやハンカチなど)の柔らかい布を触ることで、さまざまな感触を楽しむ
- 見立て遊びやごっこ遊びを通して、保育者と一緒に遊びを楽しむ
期待される姿
- 布(タオルやハンカチなど)を丸めたり、折ったり、結んだりして想像力や考える力が育つ
- 感触を楽しむことで、手指の感覚が刺激し、発達を促す
保育士の配慮と援助
質感や手触り、大きさなど異なる布を用意して、それぞれ布の特徴に合わせて楽しむようにしましょう。 また、布あそびをする時は、保育者がたくさん声がけをしましょう。環境構成
特別な準備が必要なく手軽に楽しめ、雨の日や暑さで外遊びに出られない時なども十分に楽しめます。乳児向け布遊びの遊び方・ルール
乳児向け の布遊びをまずご紹介します。布の感触遊び

【遊び方】
さまざまな布に触れて感触を楽しみます。タオル、手ぬぐい、シフォン、シルク、ちりめんなどをつかって、ふわふわ、さらさら、シャリシャリ、ごわごわといった肌にあたったときの感触の違いを楽しみます。たださわるだけでなく、握る、引っ張る、掴む、こするなどの触り方を変えてみるとまた違った感触が味わえます。いないいないばあ
【用意するもの】- ハンカチサイズ以上の布
布遊びの定番、いないいないばあです。布で保育者の顔を隠し、ばあの合図に合わせて布を外すと今まで隠れていた顔が現れて子ども達は大喜び。布をつかもうとするか、顔にかかった布を取ろうとするかなど発達の程度を確認することもできます。
じーじーばぁ

- ハンカチサイズ以上の布
子どもと対面ですわります。ねんねの子どもは寝たまま向かい合います。歌詞に合わせて布を動かします。
♪じーじー(保育者の顔を布で隠す) ばぁ(いないいないばあの要領で顔を出す)
じーじー(保育者の顔を布で隠す) ばぁ(いないいないばあの要領で顔を出す)
ちりん ぽろんと (布を左右に振る)
とんでったー (布を手から離す)
布がうごくと保育者の顔が見えたり、また隠れたり、最後に布が待っていく姿を目で追いかけたりと静と動の動きを備えた子どもたちが大好きな遊びです。布はシフォン地のような顔が透けて見えるものだと子どもから保育者の顔が見えるため子どもが安心を感じられます。
ちゅっちゅこっこ

- ハンカチサイズ以上の布
子どもと対面ですわります。ねんねの子どもは寝たまま向かい合います。歌詞に合わせて布を動かします。
♪ちゅっちゅ こっこ とまれ(布(軽い布がおすすめ)を上下に振る)
ちゅっちゅ こっこ とまれ(布(軽い布がおすすめ)を上下に振る)
とまらにゃ とんでけー(とんでけーの声に合わせて布を手から離し子どもにかかるようにする)
いない いない ばあ(子どもがスカーフを取る)
顔にかかった布を取れるようになる生後6か月以降から遊ぶのがおすすめです。布はシフォンのような軽い布で遊ぶとよいでしょう。お座りができて手を動かせるようになったら、子どもが自分で布をもって遊ぶのも面白いですよ。歌詞の意味は、鳥さん止まれ、止まらないなら飛んでいけ~ という内容だと言われています。
にぎりぱっちり

- ハンカチサイズ以上の布(くしゅくしゅしても元に戻るものがよい)
子どもと対面で座ります。用意した布をくしゅくしゅと手で丸めて両手の中に隠します。
♪にぎりぱっちり たてよこ ひよこ (手の中に布を入れた状態で手を左右に振ります)
ぴよぴよぴよぴよぴよ (手を緩めて布が出てくるように手を広げます)
動物の歌詞は、こいぬ、こねこ、ひつじなどの動物にして鳴き声をまねしてみてもいいですね。手の中に隠れていた布がもくもくもくと出てくる姿に子どもたちも興味津々になることでしょう。
ももやももや
【用意するもの】- ハンカチサイズ以上の布
布を手に持って歌詞に合わせて布を動かします。
♪ももや ももや ながれは はやい (布を振る)
せんたくすれば きものが ぬれる (布を振る)
あ どっこいしょ (腰に手を当ておばあさんが腰を伸ばすポーズをする)
桃太郎をモチーフにした歌ともいわれており、洗濯板で洗濯する様子をまねているともいわれています。桃太郎の絵本を読む前の導入として遊んでみてもいいですね。 布を振るだけでなく、洗う、すすぐ、絞るの動作を加えてみたり、「石鹸をつけてみよう」、「ぎゅっと絞ってみよう」といった声掛けをしてみるのもいいですね。
うえからしたから

- ハンカチサイズ以上の布
布の箸を持ち、布を歌詞の合わせて上下に動かします。ねんねの子どもの場合は、体をなぞるように布を移動させて最後にいないいないばぁをしてみても楽しめます。
♪うえから したから おおかぜ こい (布を上下に動かす)
こいこいこい (布を3回振る)
うえから したから おおかぜ こい (布を上下に動かす)
こいこいこい (布を3回振る)
年齢が上のクラスでは、大きな布を用意して、保育者が2名で布の端をもち子どもたちの上に布を移動させる、子どもたちが布の下をくぐるように遊ぶのも面白いですよ。
幼児向け布遊び
次に、幼児向けの布遊びをご紹介します。ごっこあそび
布を使ったごっこ遊びもいろいろありますね。子ども主体で遊ぶのであれば、- プリンセスごっこ
- ヒーローごっこ
- おままごと(ふろしきでカバンにする、お人形のだっこひもにする)
保育者が行うのであればシーツくらいの大きくて丈夫な布に子どもを乗せて床を滑らせることで電車ごっこなどもできます。
ハンカチおとし

子どもたちが中心を向いて大きな円になって座ります。1名がハンカチを持ち、気づかれないように座っている子の後ろにハンカチを落とします。ハンカチを置かれた子が気づいたら鬼にタッチしますが、鬼が逃げ切れたらハンカチを置かれた子が鬼になります。
しっぽとり

しっぽ取りの要領で、しっぽをハンカチやバンダナなどの布で行います。ある程度長さがないとうまくしっぽをつかめないので大き目の布で遊ぶとよいでしょう。
クラッカーあそび
【用意するもの】- 大きな布
大きな布の真ん中にカラーボールを子どもたちがたくさん入れます。 保育者が上下に揺らして、ボールが跳ねたり飛び出すのを楽しみます。 落ちたボールを拾い、入れるのを繰り返しできるので、遊びが盛り上がりますよ。
布を使った遊びの注意点
布選び
遊ぶ内容によって、布を選びましょう。顔にかかるような遊びだったらシフォンやオーガンジーのような軽くて透けるタイプの布を、ひっぱったりつかんだりする動作がある遊びでは丈夫な綿の布を選びます。布の大きさにも注意します。体に巻き付いてからまったり首を絞めたりしないようなサイズ感のものを選びます。遊ぶ環境の整備
子どもが布で遊ぶときは目を離さず、誤飲、窒息や巻き付きが起こらないように注意します。布があると滑りやすくなるため布を踏まないように注意が必要です。ほつれ、やぶれ
ほつれや破れにも注意しましょう。ほつれた糸が指に巻き付きヘアターニケット症候群と呼ばれる、血流が悪くなったり痛みを感じたりする症状がでる場合があります。布遊びをしたらよく手を洗い、体や衣類に糸くずがついていないかを確認しましょう。布を使った遊びで楽しく遊ぼう
布を使った遊びをご紹介しました。ちょっとした隙間時間や絵本を読む前の導入にも遊ぶことが出来ます。ぜひ遊びのレパートリーに加えてみてくださいね。おもちゃコンサルタントマスターによる講座のご紹介
芸術と遊びらぼではシフォン布遊びのWEB講座を開催しています。布を使った遊びに興味を持った方はこちらもぜひご覧ください。【W25】楽しい!心も柔らかくなるシフォン布遊び(シフォン2枚付き)
【関連記事】