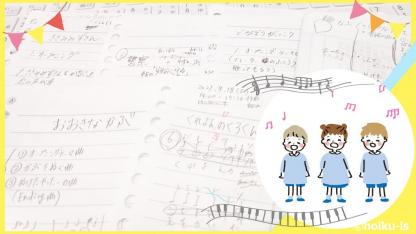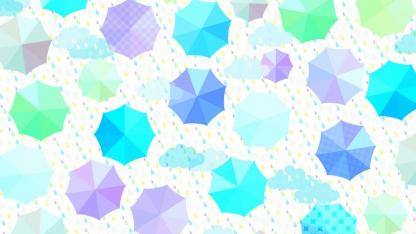卒園ソングの上手な教え方って?
前回は「音程良く歌うコツ」「喉を傷めない発声のコツ」について、ボイストレーナーの玉置彩音先生(オンライン歌唱指導Marsy所属)に教えて頂きました。 今回は、これからの卒園シーズンにぴったり! この時期に悩みがちの「卒園ソング」の歌い方や練習方法について、聞いてみました。声の出し方・気持ちの盛り上げ方・抑揚のつけ方の3つの視点でご紹介します。声の出し方「大きな声」=「怒鳴り声」に…どうしたいらいい?

<質問>
子どもたちに大きな声で歌うように声をかけると、怒鳴るように歌う子が多くみられます。さらに高音になると、極端に声量が小さくなってしまうのが目立ち、気になります。良い練習方法や言葉がけはありますか?<ボイストレーナーの解決策!>
怒鳴るように歌ってしまうことの原因として、大きな声を出すという意味を勘違いしていることや、友だちと過ごすことで自意識が高まり、負けないようにと力いっぱいに歌ってしまうことなどが考えられると思います。子どもたちには歌唱技術を求めるのではなく、歌うことの楽しみを教え、音楽を通して感性を養うことを大切にするべきだと思います。そのために、その曲の内容やイメージを伝え、それを元に「どんな声で歌うといいかな?」「次はもっと優しい声で歌ってみよう」と声がけをし、練習を進めていくと良いと思います。
音程は、声帯の長さを変化させることで変えているのですが、子どもの声帯は大人より短いので、高音を出すことは難しいと考えられます。また、子どもの声帯はとてもデリケートですので、力を入れた無理な歌い方をさせないようにしないといけません。
まずは、子どもにとって歌いやすい音域で書かれている曲を選ぶことが大切です。
気持ちの盛り上げ方「絵本」でイメージトレーニング


曲の内容やイメージを膨らますためには、曲に関連する絵本がオススメです。
絵本を通して「懐かしむ気持ち、しっとり歌い上げる、語りかける感覚」を五感で感じて、歌に繋げてみましょう。
卒園までに「元気な曲、かっこいい曲」など、いろんな曲調に出会ったと思います。あえて、卒園ソングを真逆の曲調(例えばヒーロー曲のように元気に)歌ってみて、どちらが雰囲気に合っているか、みんなで話し合っても良いですね。
【藤本さんおすすめの絵本がこちら↓】
>>[さよなら ようちえん (講談社の創作絵本)]
抑揚のつけ方「子どもに歌の強弱を教えたい…」どうしたらいい?
<質問>
子どもたちの歌が音程に変化がなく、1本調子で歌っていて抑揚やリズムが乏しいです。良い練習方法はありますか?<ボイストレーナーの解決策!>
子どもたちは楽譜を読んでいないので、耳からの情報を大切にして歌っています。抑揚は、先生の真似をさせてあげるのが一番良い方法だと思います。抑揚などについても言葉で説明するのではなく、先生ご自身が歌いながら説明してあげると子どもたちにとって分かりやすいですし、歌うことに集中させやすくなるとも思います。
遊びながら抑揚の練習!おすすめの実践方法

動物になりきってみることで、大きな声・高い声・小さな声などの練習ができます。例えば“大きな声”や“ダイナミックな歌い方”のときは、恐竜のように低音で「がぉ~」と唸ってみる、などがおすすめです。

“高い声”や“小さな声”の練習には、フクロウのように高音で「ホゥ…ホゥ…」とささやいてみるなど。
いろんな音に耳を澄ませて真似をしながら、自分なりの表現を見つけていきましょう。表現の引き出しが多くなれば、表現したい音のコントロールも上手になっていきます。
卒園まで日数がある場合は、ハンドサインやオーガンジーを使ってリトミックを取り入れて、表現力を磨いてみるのも良いですね。1年かけて遊んだリトミック・表現遊びの集大成が現れるときです。
さらに深く学びたい方には、私もお世話になっている、ボイストレーニングのオンライン教室もおすすめ。
>>オンライン教室はこちらから
先生自身の歌唱スキル向上だけでなく「今、子どもたちと歌っている卒園ソングの歌唱についての相談」など、幅広く悩みが解決できますよ。
次回は新年度直前の“就職応援企画”として、「おすすめピアノ教材3選」をお届けします!