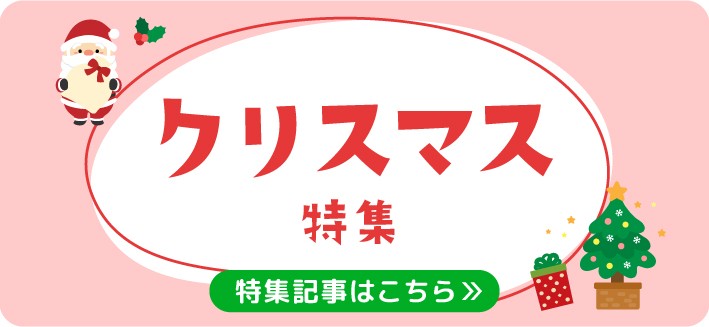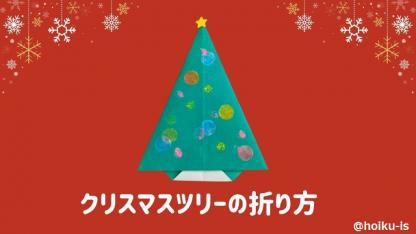全国各地で発生している風水害

ただし、突然起きる地震とは異なり、台風や大雨は事前にある程度の情報を得ることが可能です。「どのくらいの規模の台風か?」「線状降水帯がどのエリアに来るのか?」など、予め情報を知っていれば、対策をすることができ、被害を最小限に抑えることが可能です。
そこで今回は、風水害から子どもたちを守るために、園でどのような対策が必要なのかをお伝えします。
(1)ハザードマップで自園の周辺のハザードを知る

ここでは川の氾濫だけでなく、土砂災害や内水氾濫(※)などが発生した場合の状況が予測されているので、自園の周辺地域のハザードマップを見ておくことが大切です。内水氾濫は、川や山が近い場所で発生するとは限らないため、注意しましょう。
| ※「内水氾濫」とは、下水道などの排水施設の能力を超えた雨が降った時や、雨水の排水先の河川の水位が高くなった時などに、雨水が排水できなくなり浸水する現象。下水道や水路などから雨水があふれ出し、浸水被害が発生します。2019年(令和元年)の台風19号では、内水氾濫によって川崎市内のタワーマンションが大きな被害を受けました。 |
(2)警戒レベルについて

| 警戒レベル | 避難情報等 |
|---|---|
| 5 | 緊急安全確保(市町村) |
| 4 | 避難指示(市町村) |
| 3 | 高齢者等避難(市町村) |
| 2 | 大雨・洪水・高潮注意報(気象庁) |
| 1 | 早期注意情報(気象庁) |
「高齢者等」という言い方になっているため、「乳幼児は警戒レベル4で避難すれば良い」と思っている人も多くいらっしゃいます。しかし実際には、警戒レベル3は高齢者だけではなく、妊産婦や乳幼児を複数連れている場合なども含めた避難に時間を要する人が対象となっています。そのため、保育園は警戒レベル3が出た場合に避難をします。
水害時には、常に警戒レベルが今いくつなのかをチェックしておくと、避難すべきタイミングである警戒レベル3になった時に焦らず落ち着いて行動できます。
(3)事前の準備

①タイムラインの作成
天気予報で台風の接近などが分かった時の対応や、警戒レベル1から5の各段階それぞれのタイミングに行うことなどを時系列で決めた「タイムライン」を作成しておきます。決めておく内容の例としては、保護者への連絡のタイミングや、避難準備などになります。また、合わせて「職員はいつ帰宅するか」など園運営に関わる項目も事前に決めておくと、いざという時の心構えができできます。
②園の風水害対策について保護者に伝えておく

ただ、急に保護者にこのようなお願いをしても、仕事の都合もあるでしょうし、なかなか理解してもらえないかもしれません。日頃から保護者とのコミュニケーションを大切にし、園だよりなどを活用して園の風水害対策を伝えていくことで、園としての方針に理解をしてもらう努力も必要です。実際に風水害が予想される時には、できるだけ早めに、具体的な園の対応を伝えるようにしましょう。
③よりリアルな訓練を行う

例えば、「水害時に垂直避難ができない場合は別の建物へ避難する」という計画であれば、雨の日に避難する訓練をやってみましょう。
また、風水害では停電が発生することもあります。台風の時などは日中でも室内が真っ暗になることもあるため、子どもたちが不安にならないように停電時の訓練も行っておきましょう。例えば、ペットボトルと懐中電灯を使った手作りのランタンなどは子どもたちが楽しむこともできるので取り入れるのもおすすめ。災害時だからこそ子どもたちが楽しめる工夫というのも大切です。
避難訓練の実践方法については、こちらの動画でも詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。 【参考】
避難情報に関するガイドライン/内閣府(令和3年5月より避難勧告は廃止、避難指示1~5に改訂された)
>>詳細はこちら
子ども・子育て支援推進調査研究事業/厚生労働省(認可保育園に関しては、臨時休園などの意思決定は、保育の実施主体である市町村が行う)
>>詳細はこちら
公開情報を基に準備を整えよう

【関連記事】