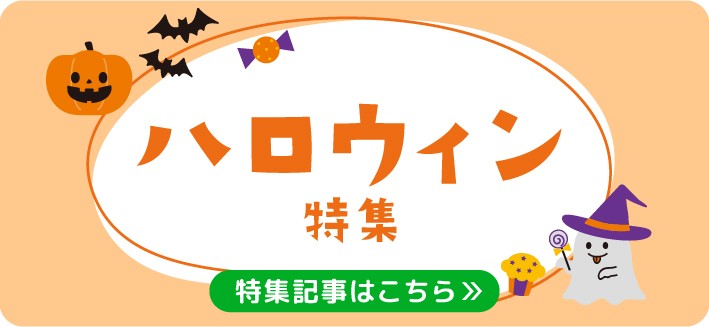ヒヤリ・ハットとは

実際に保育園では、ヒヤリ・ハット報告を重要視しています。なぜなら、今回は運良くケガにならなくても、次回同じような場面で重大事故に繋がる可能性があるからです。無事故のうちにヒヤリ・ハットの要因を考え、対策を練ることで、大きなケガを防げる可能性が高まります。ヒヤリ・ハット報告書を作成し、回覧や掲示、会議などで情報共有することで対策をとっている保育園は少なくないでしょう。
「ハインリッヒの法則」という、労働災害の調査から導き出された発生比率の法則によると、1件の重大事故の背景には29件の軽微な事故と、300件のヒヤリ・ハット事例が存在していると言われています。ヒヤリ・ハットには大きなものから小さなものまでさまざまありますが、まずはどのようなケースがあるのか、事例とともに見ていきましょう。
定番のヒヤリ・ハットを知ろう
ここからは、保育の現場でよく見られるヒヤリ・ハットをケース別に分類して紹介していきます。誤飲・誤嚥

- おもちゃを口に入れていた
- ヘアゴムなどを誤飲した
一般的に直径4cm以内の物は、誤飲した場合に窒息の可能性があると言われています。喉に詰まらなくても、飲み込んでしまうことで内臓を傷つけてしまう危険性も。
おもちゃや園の備品は置き場所を明確にし、保育室には発達に合ったおもちゃを置くようにしましょう。誤飲や誤嚥の可能性がある物は、子どもの手の届かない場所へ片付けることが基本です。
転倒・転落

- 走っていて転倒した
- 滑り台やブランコから転落した
すべり台やジャングルジム、ブランコなど、遊具からの転落事例も多くあります。ケガを完全に防ぐことは難しいですが、普段から検証を積み重ねていくことで、保育士の立ち位置を調整したり、遊びのルールを決めたりすることで、危険を回避できる可能性が高まります。
「どういう行動パターンで発生するのか?」「遊具や場所別の発生パターンは?」などについて、発生したケース毎に事例を記録したり、保育者間で情報共有する機会を設けるなど、園全体で経験とノウハウを蓄積していくことが必要です。
衝突

- 走っていた子ども同士が衝突した
- 机や棚に衝突した
机や椅子などの備品に衝突するケースもあります。その際、角のある部分にぶつかるとケガの深刻度が増す可能性があるため、保育室にある備品は事前にチェックして、危険な箇所にはコーナーガードを設置するなどの対策をしておくと良いでしょう。
午睡(お昼寝)

- うつぶせ寝になっていた
- 他の子どもが覆いかぶさっていた
乳幼児突然死症候群(SIDS)や、SUDI(予期せぬ乳幼児突然死)の知識も広く知られるようになり、午睡中の寝姿勢の確認(うつぶせ寝になっていないかなど)やブレスチェック(呼吸チェック)は基本となっていますが、他の子の動きや、掛布団・タオルケットが呼吸を妨げる要因になるケースなどもありますので、そういった点も常に想定しておきましょう。
また、お昼寝する部屋は暗くしすぎず、子どもの表情や顔色が見える明るさに保つことも大切です。
参考:教育・保育施設等における事故報告集計(令和4年)/こども家庭庁 >>詳細はこちら
食物アレルギー
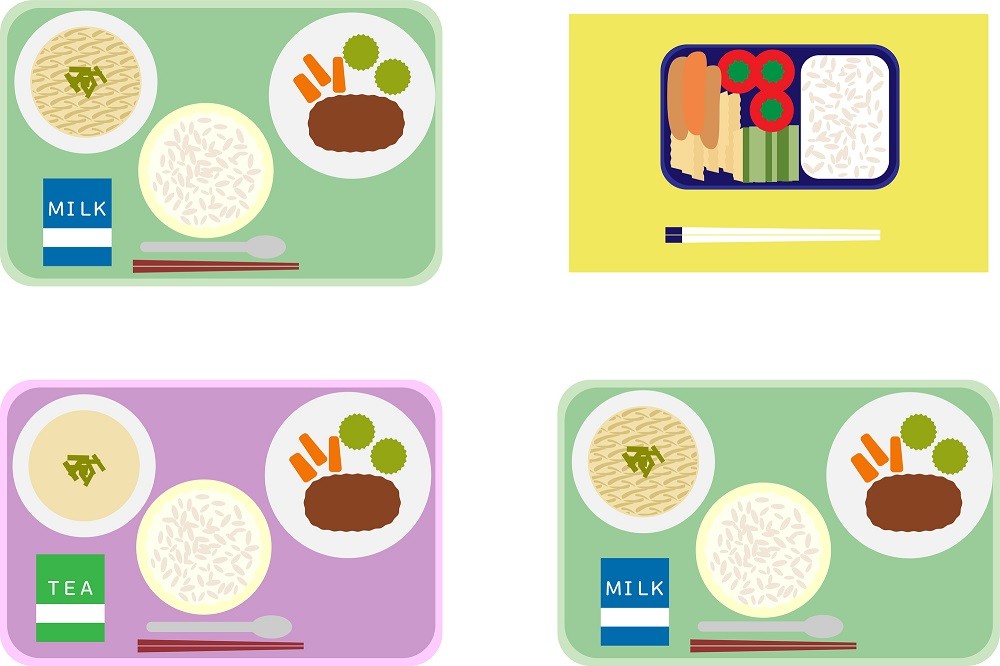
- アレルギー除去給食と通常給食を間違えて配膳した
- 落ちているものを食べてしまった
おかわりを配膳する際にも、うっかり普通食を渡してしまわないよう注意が必要です。対策として、アレルギー食であることに気付けるよう、異なる色の食器を使用することが有効です。
「食事については調理スタッフさんが気をつけているから大丈夫」という考えは捨てて、子どもの食に関わる全職員が意識して対応を行いましょう。
見落としがちですが、食事中に子どもが別の子に食べ物をあげてしまったり、落ちているものを食べてしまったりするようなケースもあります。アレルギーを持つ子どもの席や保育士の見守り方にも配慮が必要です。
噛みつき・ひっかき
【事例】- 隣に座っていた子に噛まれそうになった
- ケンカをして、ひっかかれそうになった
また、噛まれた子が噛むことを覚え、クラス内で蔓延する場合も。そうならないためにも、傷を負った子の心のケアを行なっていくことも大切です。
食事中の窒息

- 離乳食の固さが合っていなかった
- 食事をしながら寝ていた
また、0〜2歳児は食事中にウトウトする姿も見られます。食べ物を含んだまま身体を横にすると窒息の危険性があるため、口内を確認してから眠らせるようにしましょう。
泣いている時も危険なので、落ち着いてから食事を始めます。窒息時は声が出せないため、保育士の注意深い見守りが不可欠です。
子どもが見当たらない
【事例】- 子どもが物陰に隠れていた
- 園外保育中に迷子になった
狭い場所に隠れる子どももいるため、倉庫や押入れなど、子どもが入り込みそうな場所には鍵を設置しておきます。
散歩や遠足などの園外保育では空間が広がるため、一度集団から離れると見失う危険性が高まります。このようなヒヤリ・ハットを防ぐためには、広い視野で子ども全体の動きを把握しつつ、こまめな人数確認を行うことが欠かせません。
園で対策できる5つのポイント
ヒヤリ・ハット対策はどのようにしていけばいいのでしょうか? 必ず押さえておきたい5つのポイントをご紹介します。①子ども目線で環境確認

大人では危険に繋がらないことでも、子どもの高さではケガや事故につながる要因が潜んでいる場合があります。子どもの視線の高さや遊び方、興味などを踏まえて環境を整えることが大切です。
②職員間での情報共有
クラスで起きたケガや、遊びの中で危険に感じたことは、他の職員にも必ず共有しましょう。定期的にミーティングなどを行えると良いですね。他のクラスで起きたことは、自分のクラスでも起きる可能性があるという意識で取り組みましょう。定番ヒヤリ・ハット対策の第一歩は、情報共有からと言っても過言ではありません。③他園との事例共有

また、事故につながってしまった事例に関しては、その後の対応までチェックしておきましょう。同様の事故が起こってしまった際の指針となり、迷わず行動することができます。
万が一ケガが起きた場合に備えて、園の対応方法を確認しておきましょう。救急車を手配する手順や、保護者・関係者への連絡手順などをマニュアル化し、職員に共有しておきます。
④適切な職員配置と見守り
園でのヒヤリ・ハット対策には、状況に応じた適切な職員配置が不可欠です。保育士同士が声を掛け合い、子ども全員の状況を把握できる体制を整えましょう。ただし、保育士が十分に配置されていたとしても、その全員が子どもと直接関わっていたら見落としが生じる可能性もあります。そのため、状況を客観的に観察し、安全確保に専念する役割を設けることも効果的な対策です。
⑤発達に応じた安全教育
保育士がいくら注意を払っていても、多くの子どもが同時に危険な行動をとれば、安全の確保は困難です。そのため、子どもが自分で危険に気付いたり、友だち同士で教え合ったりする力を育むことも重要です。子どもが安全に気をつけて行動できるよう、発達に応じた安全教育を行っていきたいですね。
ヒヤリ・ハットの共有で重大事故を防ごう
思わぬ場所に事故やケガの危険は隠れています。重大事故を防ぐためにも、ヒヤリ・ハットを職員間で共有し、子どもたちが安全に過ごせる保育環境を作っていきたいですね。保育園の事故・ケガ対策を考えている方は、参考にしてみてください。
【関連記事】