ファミリーデーとは
はじめに、ファミリーデーの概要と子どもへの伝え方について見てみましょう。ファミリーデーの概要

家族の形が多様化してきた現代では、保育園で母の日や父の日といったイベントを行うことが難しくなってきています。そこで生まれたのが「ファミリーデー」という考え方です。
ファミリーデーに特定の日にちは設けられていません。母の日や父の日がある5〜6月の中の一日をファミリーデーとしている園が多いです。
「母の日」「父の日」とは
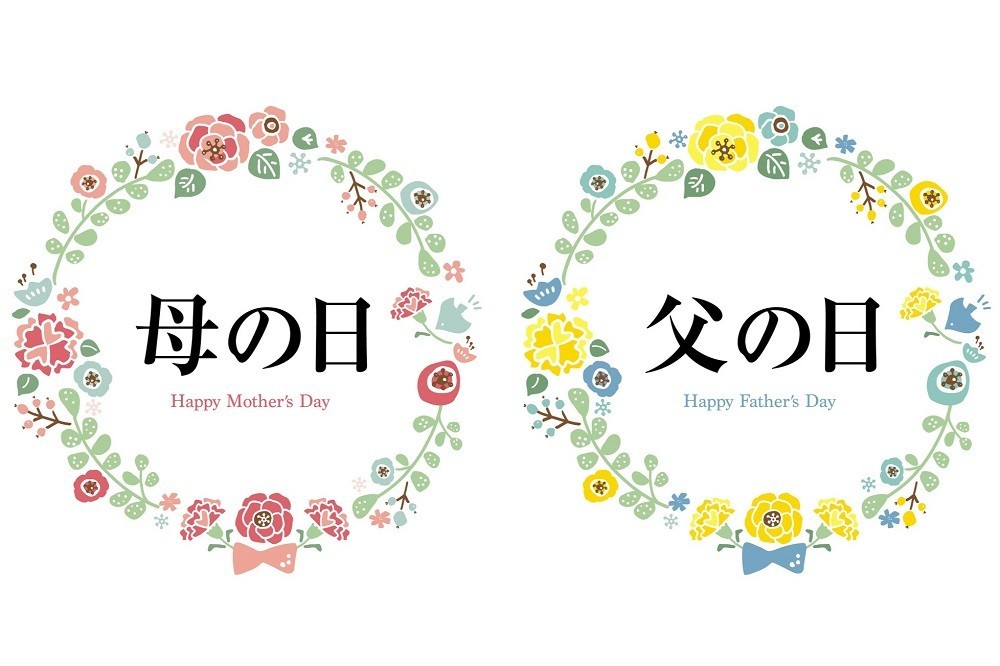
「母の日」は、母親に感謝を伝える日です。シンボルとして、赤いカーネーションが有名ですね。毎年5月の第2日曜日が母の日となっていて、2024年は5月12日(日)です。もともとは20世紀の初めにアメリカで始まった風習が、戦後に日本でも広まり定着しました。
「父の日」は、父親に感謝を伝える日です。日本では黄色いバラを贈る風習を始め、黄色がイメージカラーとなっています。毎年6月の第3日曜日が父の日となっていて、2024年は6月16日(日)です。こちらもアメリカで母の日の制定から間もなく始まった風習が、1950年代頃から日本でも広まって定着しました。
いずれも、1年に1回、母親・父親に感謝の気持ちを伝える日として定着しています。
ファミリーデーのねらい
ファミリーデーを保育園や幼稚園、認定こども園の活動として取り入れる際はきちんと計画を立てて、ねらいを持って行わなければいけません。ねらいとして、次の2つが挙げられます。- 家族を大切に思う気持ちを育む
- 家族に感謝の気持ちを伝える
子どもへの伝え方
子どもたちにファミリーデーや家族のことを、わかりやすい言葉で伝えてみましょう。【子どもへの伝え方の例】
- ファミリーデーは家族に「ありがとう」を伝える日だよ
- 家族って、一緒に暮らしている人のことだよ
- 家族って、みんなにとって特別で、大切な人だね
- 家族がいるから、生まれてこれたし、今も生活することができるんだね
- みんなにとって家族ってどんな人がいるかな?
ファミリーデーの製作活動
ファミリーデーの活動として、家族へのプレゼント製作をしてみてはいかがでしょうか。子どもたちが指先の機能を高めながら、楽しく取り組める製作をご紹介します。メッセージカード編
「ありがとう」の気持ちを言葉で伝えられるメッセージカード。手作りすれば、世界に1つだけの特別なカードが完成です。心を込めて作りたいですね。・お花が飛び出すメッセージカード カードを開いたら立体的なチューリップが飛び出します。お花の周りにはチョウチョやお日様などのイラストを描いても可愛いですね。 ・ちょうちょのデカルコマニーメッセージカード
2つ折りの画用紙に絵の具を置き、閉じて開けば素敵な模様が現れます。デカルコマニーで作ったチョウチョを貼り付ければ、春らしいメッセージカードの出来上がりです。 ・キャンディブーケのメッセージカード
フェルトで作ったお花が散りばめられたブーケ型のカードです。レースペーパーを挟めば、華やかさがアップ。リボンをほどいてブーケを開くとメッセージが現れる仕様です。 ・保育園でつくるメッセージカードの製作アイデア7選
他にもさまざまなタイプのメッセージカードを作ることができます。子どもの発達や興味関心に合わせた製作を行いたいですね。メッセージカードのアイデアは、こちらの記事を参考にしてみてください。
フォトフレーム編
写真を入れて飾れるフォトフレーム。手作りしたフレームに子どもの写真を添えれば、成長が感じられるプレゼントになります。・さくらの透明フォトフレーム 桜をバックに思い出の写真を飾ることができます。ラミネートフィルムを用いた透明感のあるフォトフレームです。タンポポやクローバーなどをあしらっても可愛いですね。 ・紙粘土のフォトフレーム
段ボールで作った型に紙粘土を付ければ、ふっくらと立体的なフォトフレームに。子どもたちのセンスでビーズを埋め込めば、個性溢れる作品の完成です。 ・空き箱で作るフォトフレーム
レトルトカレーなど、平たい空き箱を利用すれば簡単にフォトフレームを作ることができます。正面に写真を飾れるだけでなく、箱の中に写真を収納することもできますよ。
手作りプレゼント編
プレゼントを作って、ファミリーデーの記念に贈ってみてはいかがでしょうか。家族を思いながら作る時間も、子どもたちにとってかけがえの無いひとときとなるでしょう。・紙皿のあったかネックレス 紙皿の中をくり抜けば、ネックレスの型に。毛糸を巻き付けたり、飾りを付けたりすれば、可愛らしいアクセサリーが完成です。 ・紙粘土のペン立て・鉛筆立て 空き瓶を紙粘土で覆えば、手作りのペン立てに。毛糸を巻き付けたり、ビーズを埋め込んだりすれば、子どものセンスが光る贈り物になります。 ・フラワーペーパーで作るフワフワ花束
フラワーペーパーのお花で花束を作ってみてはいかがでしょう。フワフワで立体的な作品なので、優しい気持ちで丁寧に作る機会となりそうです。 ・折り紙メダル
家族に贈るメダルを折り紙で手作りします。「ありがとう」の気持ちを込めながら、丁寧に折りたいですね。 ・飛び出すメッセージカードの製作アイデア11選
余裕があれば、プレゼントにメッセージカードを添えてみてはいかがでしょうか。家族への思いを言葉で表現する貴重な機会です。手作りのカードで感謝の気持ちを伝えたいですね。
子どもたちの気持ちをのせるメッセージカードのアイデアは、こちらの記事をご覧ください。
保育参観で体験するファミリーデー

普段の保育を見てもらうのも良いですが、親子で一緒に遊ぶ時間を設けたり、事前に作っておいたプレゼントを渡す機会を設けたりすると、「ファミリーデー」らしさが出ますね。
保育参観の事前準備やおすすめのクラス活動については、こちらの記事を参考にしてみてください。
ファミリーデーの事前準備と注意点

現代では、必ずしもこどもたち全員が同じような家族形態とは限りません。両親が揃っている家庭もあれば、ひとり親家庭もあります。また保護者がパートナーと生活している場合も。
「父母」という言葉が適切ではない場合もあるので、ジェノグラムを用いて子どもの家庭環境を事前に把握しておくと良いでしょう。
ジェノグラムについては、こちらの記事を参考にしてみてください。
家族について考えてみよう
ファミリーデーは家族を想い、日頃の感謝を表現する機会です。身近な存在である家族について、子どもたちと一緒に考えてみる日にしたいですね。これからファミリーデーの活動を計画する方は、参考にしてみてください。
【関連記事】


















































