2つ目のモデルクラスの指導を開始

このクラスは3~5歳児の縦割りで、他園から転園してきた子どもが大半を占めています。中国の一般的な幼稚園は一斉保育で、勉強に力を入れている園が多いと聞きます。しかし、私たちが行っている保育は「子ども主体の保育」ですので、転園当初は戸惑う子どももいたと思います。しかしクラスの先生たちは優しく子どもに寄り添い、子どもたちが自分の「やりたい」を大切に出来るように保育を行ってくれていました。
指導開始は、以前のモデルクラス同様、室内の環境整備から行いました。担任の先生と話し合いを行いながら、子どもたちの興味のあるものや、流行っている遊びを十分に楽しむことが出来るように棚の位置を少し動かしました。教室が広くなったことで、子どもたちはのびのびと室内での遊びを楽しむことが出来ているように感じています。
環境を整備してからは製作遊び、お絵かき、ブロック、おままごとなど自分たちで遊びを選択し、その遊びを組み合わせてさまざまな遊びが広がっています。ブロックで車を作っていた子が、その車を絵に描こうとお絵かきコーナーで絵を描き始めたり、製作コーナーでは、粘土と紙を組み合わせて作品を作ったりと、いろいろな遊びを楽しんでいます。戸外では、砂場で「骨が埋まっているんだ!」と言った子が、友だちと協力してその骨を探して楽しむ姿や、追いかけっこ、だるまさんがころんだなど、ルールのある遊びを楽しむ姿も良く見られます。

こうしてお友だちとの遊びを楽しむ一方、子どもたち同士のトラブルも多くあります。先生たちは子どもの気持ちに寄り添って対応をしてくれているようですが、結論を先生が出してしまうことも多かったです。なるべく子どもの力でトラブルを乗り越えることが出来るよう、先生たちには指導を行いました。ポイントは、状況を把握して双方の意見を聞くこと。そして双方の意見を平等に扱う、子ども同士で解決が出来るように見守るということです。子どもたちが納得して答えを出すことができるように、今後も先生たちと一緒に子どもたちを見守っていきたいと思っています。
文化の違い、“普通”の感覚の違い
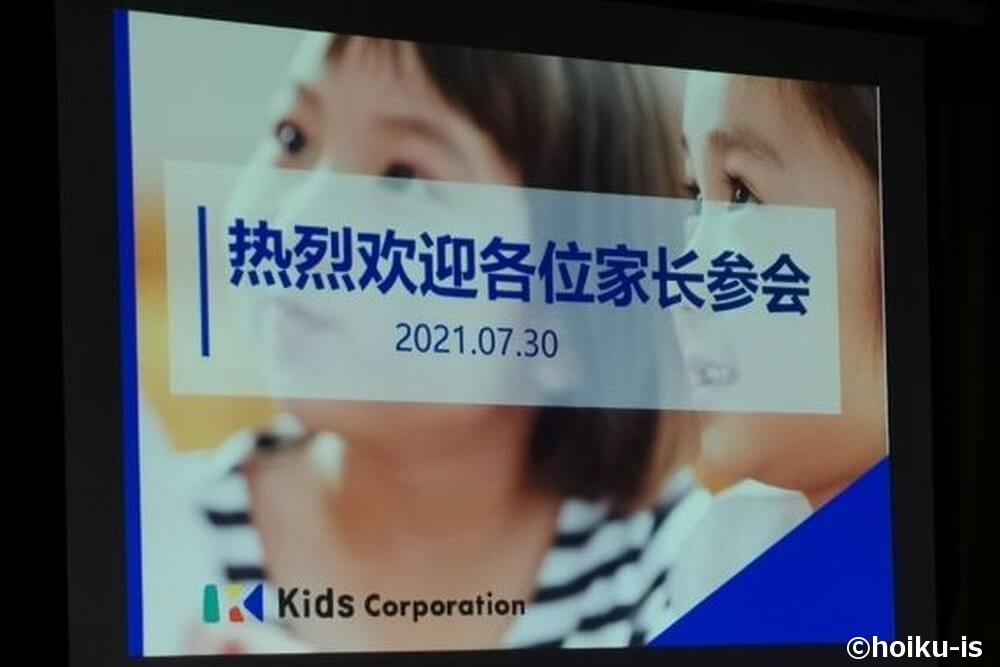
着任後、問題解決について会議を行うと、「中国は○○〇なので」「他の園は△△△でやってますから変えられません」といったやり取りが続き、苦戦しました。私たちが変更をお願いしている項目は、すべてに意味があります。それらを理解してもらえるよう、その意味について一つずつ説明を重ねました。今では少しずつ改善に向けて動き出し、協力を得られるようになってきました。
国を超えて仕事をすることで、文化の違いや“普通”の感覚の違いに気づくことが出来、とても良い経験になったと感じています。日本の保育現場での“普通”が、中国では“普通”ではなく“特別”になります。また、その逆のこともあります。
例えば先生同士で名前を呼び合うとき、日本では「○○(名前)先生」と呼びます。しかし中国では、名前やニックネームをそのまま呼び合うことが多くあります。もちろん日本のように「○○先生(老師)」と呼ぶこともありますが、名前のみで呼ぶのは、親しくなった証のようなものだと教えていただきました。
また以前も書きましたが、園で食べる食事の回数が多い点は、中国では“普通”で、日本からすると“特別”なことです。このように、さまざまな両国の違いを受け入れながら、「子どものために」という視点でいろいろ考えて保育を行う経験が出来てとても嬉しく思います。
現在は、園での食事回数について変更を図っている最中です。すべての年齢の子どもが、3回の食事と2回のおやつを園で食べる中国のやり方から、おやつ2回を減らして食事3回に変更しようと動いています。まずは食育の観点から、中国の提携会社の方には理解をしていただきました。そして保護者にも説明を行い、新年度スタートの9月から変更予定です。保護者の理解を得るために、他部署の先生方が分かりやすい資料の作成や、サポートをしてくださいました。そのおかげで、保護者の方も変更に向けて前向きに考えていただけているように感じています。

おやつがなくなるということは、1日の流れ(デイリープログラム)が変更になるので、先生たちの動き方も変わってきます。着任してから今までさまざまなことが変更になりましたが、その中でも一番と言って良いほどの大きな変化になると考えています。この変化を機に、職員全員がしっかりと目的を把握し、理解しながら進めることが出来るようサポートを続けていきたいと思います。
8月は1年の締めくくり

「中国の幼児教育を変えたい!」という想いを持っていたり、子どもたちの変化を見て、「子ども主体の保育がやりたい!」と考えている先生たちばかりなので、その気持ちを忘れることなく、これからも一緒に頑張っていければと思います。
▼ほかおすすめの記事はこちら

































