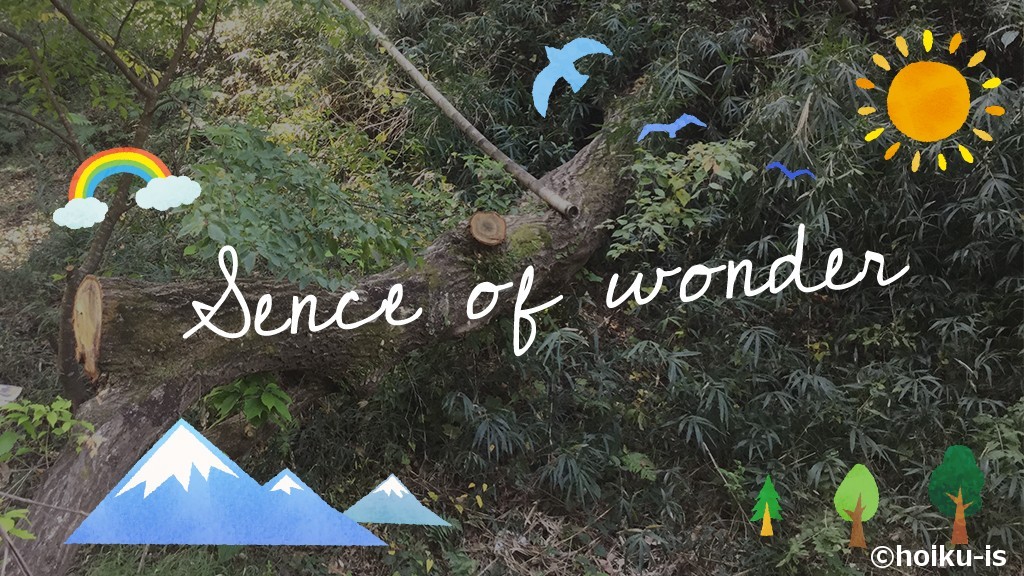先日の台風19号の後のことです。
保育園の子どもたちに
「台風すごかったね、みんなのお家はどうだった?」と聞いてみると、子どもたちは口々に自分の家の窓に雨が当たっていたこと、風で木が揺れていたこと、テレビで観た映像のことなどを興奮気味に話してくれました。
その後、みんなで公園に行ってみました。公園には、まだ青いどんぐりや悪玉菌のようなトゲトゲした形のモミジバフウの実、蕾んだままの緑色のまつぼっくりなど…普段よりもたくさんの種類の木の実や葉が、枝についたままの形であちらこちらに落ちていました。
子どもたちは思い思いに好きな実を拾いながら歩き、いつもよりも多い収穫で、持ってきた袋が大活躍でした。
しばらく行くと…一本の大きなポプラの樹が根こそぎ倒れていました。その倒木の前には人が近づかないように、2〜3個の工事用の赤いコーンが置かれていました。
私は、子どもたちが倒木を近くで見るチャンスと思い、どんな危険があるかを確認しました。その樹は大きくて、私が幹に体重をかけてもびくともしません。枝も太く張りがあり、幹をしっかりと支えているような形で倒れていたので、大丈夫と判断して、子どもたちと一緒に倒木に近づくことにしました。
数人の子どもたちは、目の前に見えていた、根っこが抜けてできた大きな穴に入って遊び始めました。他の子は、樹の幹の方へと回り込んで探索がスタート。
「えー!?これなんで?」と3歳の男の子が驚いて声を挙げました。根こそぎ倒れたため、地面がそのまま根っこと一緒に縦に持ち上がっていた部分を見つけたのです。その子にとって、“地面が自分の目の前に壁のようにある状態”が驚きだったようでした。その声を聞いて、「どうしたの?」と女の子が見にくると、「ほら、これ。」と教えていました。その女の子にとっては特に驚きの出来事ではなかった様子で、ただその地面の部分を触ってみていました。きっと崩れてしまうと思ったのでしょう。その触れ方はとても優しく、小動物を撫でているかのような様子でした。それを見て男の子も一緒に優しく撫でたり、指で突いたり、その地面にまだ生えていた葉っぱを引っ張ってみたりと触れ始めました。
そのうちに、子ども達は幹の表面を触ってみたり、大きな枝についている葉っぱを引っ張ってみたりしながら遊び始めました。幹の上に登ってみようと、何回か幹に飛びついた子もいましたが、大きすぎて登れないことを知ったようでした。
この倒木との出会いによって、持ち上がった地面や穴、樹そのものの感触や大きさをダイレクトに体験する機会となり、子ども達自身が台風や自然の大きさを肌で感じることができました。
一週間経っても子どもたちの中には、この時の体験が残っていて
「おおきなき、たおれてたね!!すごかったね!」
とあの体験を再体験しているかのように、話していました。
倒木で遊ばせるかどうか、賛否あるかと思います。しかし、どこが危ないのか、どうすれば安全かを確認できれば、子どもたちにとって最高の機会になります。
それは、私たち大人が教材として用意できない、自然の大きさを体感する機会であり、それを逃すなんてもったいないと思いませんか?

【ほか自然体験に関するおすすめ記事はこちら】