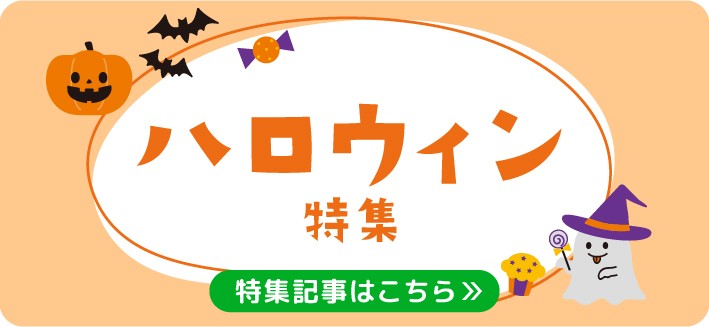「自然をどのように保育に取り入れたら良いですか?」
このような疑問を持っている方は多いのではないでしょうか? 実際に、保護者や保育者の皆さんからこの質問を受けることがたくさんあります。
「どのように?」と方法を聞かれれば、私が知っている方法を伝えることもできます。「こんなこともできるよ」「あんなこともできるよ」と、方法はさまざま。
でも実は、遊び方を私はあまり知りません。方法については、“野遊びの本”や“自然体験”について書かれた本がたくさん出ているので、それを見る方が早いでしょう。
このような質問を受ける度に感じるのは、「自然」の捉え方が違うのかもしれないということです。
私にとっての「自然」とは、利用するものではありません。「いつもそこにあるもの」なのです。
足元に、綺麗な色の葉っぱが落ちていれば拾います。
見上げた時に、空に浮かぶ雲の色に見惚れます。
かっこいい形と丁度いい長さの棒があれば、手に持ってみます。
子どもたちもこんな風に「自然」に触れているのではないでしょうか? そしてきっと、「よし、自然を使って遊ぼう!」とは思っていないでしょう。

ある日の夕方、お散歩に出かけると空に月が見えました。2歳のHくんは、「あ!おつきさまだ!いってみよう!」と、月が見える方へ走って行きました。
しかし途中で、「あれ〜?おつきさまどっかいっちゃったな〜。あっちかな?」と、木の陰に隠れてしまった月を見失った様子。
月を探しながら走っているHくんを見守りつつ、ついて行くと、私の目に飛び込んで来たのは、大きなオレンジ色の夕日。
「Hくん、おひさま見えるよ!」と声をかけると、
「わ〜おひさまだ〜きれ〜」と言い、しばらく一緒に眺めていました。
すると、また月を探しに行こうとしたHくんがきょろきょろしたかと思うと、「あ!おひさま、もう1こあった!」と、夕日とは逆の方を指さしました。
指差す方を見てみると、そこには建物の窓ガラスに映った夕日でした。二つの夕日に照らされて、Hくんの嬉しそうな顔。
「もう1こあった!」と気づいた、そのHくんの感性がすてきだと感じた出来事でした。
子どもにとって、「自然」は遊び道具なのでしょうか?
「自然でどう遊ぶか?」ということではなく、
ただそこにある、“面白いもの” “きれいなもの” “不思議なもの”なのではないでしょうか。
「おつきさま探し」という遊び方がある訳ではありません。そこには「月に興味を持った子ども」がいたのです。そして、二つの夕日を見つけたのは、想定外の出来事でした。
こうした偶然に出会うすてきな発見…“セレンディピティ”が起きるのが、自然であり、それはいつも“すぐそば”にあるのです。
【ほか自然体験に関するおすすめ記事はこちら】