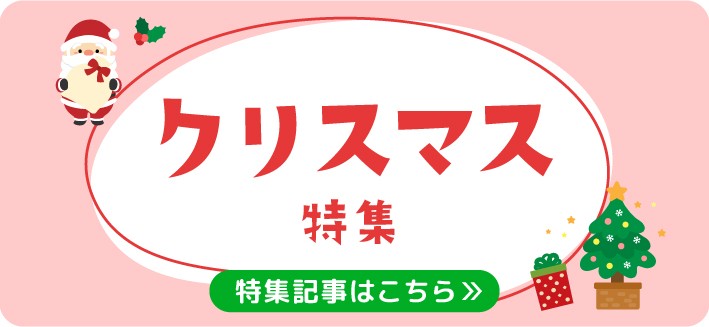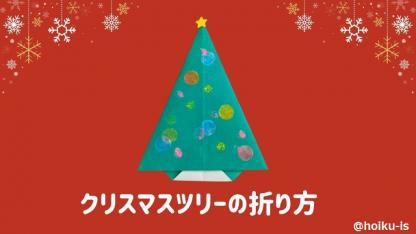「ちょちちょちあわわ」とは
「ちょちちょちあわわ」は、その言葉がなんだかかわいくてついつい声に出したくなる言葉ですが、子どものからだを触ることで刺激を与えたり、繰り返し行うことで次はどうなるという予測をする動きにもつながります。いないいないばあなどの子どもの大好きな動きもありますのできっと楽しんでくれることでしょう。今回は「ちょちちょちあわわ」の基本的な遊び方や歌詞の意味、遊ぶ際の注意点、年齢別のアレンジ遊びの方法をご紹介します。
難易度
★☆☆☆☆対象年齢
0歳児/1歳児/2歳児用意する物・道具
- 特になし
遊びのねらい
保育園や幼稚園、認定こども園での遊びの活動では、ただ単に保育のひきだしの一つとして遊びを行うだけでなく、「ねらい」を意識して取り入れるようにしましょう。そうすることで、月案や指導案の作成にも役立ちますし、子どもたちの成長を促すことにもなります。- スキンシップを通して子どもが安心感を持つ
- コミュニケーションで親しみや共感を持つ
期待される姿
- 心の情緒が安定する
- 感覚機能の発達を促す
- 感情が豊かになる
保育士の配慮と援助
身体に触れることを自分の手でできるうれしさは、子どもの運動意欲を刺激し、身体の名前も覚えます。保育者が一緒に行うことでの満足感を味わえますので、ちょっとした時間や子どもがむずがっている時などいつでもどこでも遊べます。ちょちちょちあわわの遊び方
ちょちちょちあわわは子どものからだにタッチして遊ぶ遊びです。1対1で行われるため、信頼関係やスキンシップによるコミュニケーションを図ることが出来ます。最初は「頭を触りますよ。次は体を触りますね。」などの声掛けをしながらタッチしていくと良いでしょう。遊び方
- おすわりができる子どもは膝の上に乗せて、ねんねの子どもは保育者と赤ちゃんが対面するようにします
- 歌詞に合わせて以下のように動きます
基本的な遊び方






遊び方のアレンジ
ひじを別の部位に変えてタッチ
「⑥ひじぽんぽん」のところをおなか、ひざ、ほっぺた、肩などほかの部位に変えてタッチしてみましょういないいないばあ を加えてみる
「⑥ひじぽんぽん」のあとにいないいないばぁを加えてみましょう。いつもと違う保育者の動きに子どもも興味を示すことでしょう。
大きくなったら自分でやってみる
保育者のマネができるようになったら、保育者と一緒に子ども自身が手をたたいたりあたまをさわったりしてみます。ちょちちょちあわわの豆知識
普段の生活では聞きなれないちょちちょちあわわ、言葉の意味をご紹介します。(わらべうたのため解釈はいくつかあります)。ちょちちょち:「手打ち」(手をたたく)
あわわ:開いた口を手のひらで軽くたたいて「あわわ」という声を出すこと
かいぐりかいぐり:両手を胸の辺りで横にしてぐるぐる回す動き
とっとのめ:魚・鶏・鳥などをいう幼児言葉
おつむ:頭
てんてん:手で自分の頭を軽くたたく子供の遊び