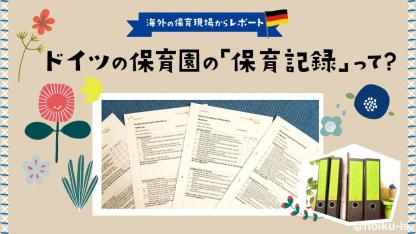噛みつきが起こる理由

それでも全てを防ぐことは難しいですよね。しかし、「なぜ子どもたちは噛みついてしまうのか?」ということを知っておけば、事前に気配りをするポイントが分かってきます。まずはその理由から考えてみましょう。
①言葉が出ない
乳児クラスなど、主に0~2歳頃の子どもに多い噛みつきの理由です。うまく言葉で感情表現ができず、思い通りにならないと、噛みついてしまうことがあります。自我が芽生えてきている証でもあり、自分を表現する手段の一つでもあります。②不安定になっている
子どもの体調や環境に変化があった場合、噛みついてしまうことがあります。咳や鼻水など体調の変化や、引っ越しをした後、お母さんの妊娠など、さまざまな原因で身体や心が不安定になっていることが理由として考えられます。
突然噛みつきすることが多くなった場合は、体調面はもちろん、家庭環境などに変化がないか確認してみると良いかもしれません。
③関わりのひとつとしている
中には、うまく周囲と関わることができずに噛みついてしまう場合もあります。このときは攻撃的な意味に限らず、「一緒に遊びたい」「楽しい」などのプラスの感情の表れであることも。うれしさや楽しさの興奮が、噛みつきに繋がることもあります。噛みつきが起こった際の子どもへの対応

①噛んでしまった子どもへの対応
お友だちを噛んでしまった子に対しては、いきなり注意するのではなく、その子の気持ちを引き出してあげましょう。理由を聞きながら気持ちを代弁したり、受け止めたりすることが大切です。また中には、攻撃的な意味はなく、どのように関わっていいのかわからないという場合もあります。「おもちゃ貸してほしかったね。」「○○ちゃんと一緒に遊びたかったね。」などと子どもの気持ちを受け止めた上で、噛んでしまうとお友だちが悲しい気持ちや痛い思いをしてしまうことを伝えることが大切です。
②噛まれてしまった子どもへの対応
言葉で伝えることが難しい子どもは、泣いて痛みを訴えることがあります。「どうしたのかな? びっくりしたね」と気持ちを受け入れ、噛まれてしまった部位の確認をしましょう。相手の子どもを責めるのではなく、「お友だち、一緒にあそびたかったのかな」など、相手の気持ちを代わりに伝えて、子ども間での関係性を構築していくことも大切です。
ケガの応急処置

<応急処置のポイント>
- 氷のうや保冷剤をすぐに使用できるように準備しておく。
- 保冷剤を使用する場合は、タオルやガーゼで巻いて使用する。
- クーリングしている間は子どもの様子や皮膚を観察する。
皮膚の内側で起こる出血です。皮膚の下は、毛細血管という細い血管で覆われていますが、その壁は薄いため、噛まれるなどの衝撃が加わるとすぐに破れてしまいます。破れた血管から出た血液がまわりの皮膚の組織にひろがるため、それがあざとなって現われます。
保護者対応

①噛みつかれてしまった子の保護者への対応
まずはトラブルが起きてしまったことを謝罪し、どのような場面で発生してしまったのか、応急処置をどのように行ったのかを具体的に伝えましょう。今後の予防策も合わせて伝えるなど、丁寧な対応が大切です。中には、「噛まれ痕は消えますか?」と心配される保護者の方もいます。園側で判断はできないので、必要な時は受診を検討し、医師の指示を受けましょう。病院では軟膏の処置がされることもあります。
②噛んでしまった子の保護者への対応
噛んだ子どもの保護者には加害者意識が残ることがあるため、保護者の心のケアも保育者の重要な関わりの一つです。噛んでしまった経緯と合わせて、噛んでしまった子どもの気持ちを伝えるなど、保護者の方が安心できる声かけを心がけましょう。また園によって、「噛んだ子の保護者には伝えない」「乳児の場合は伝えない」「何度も繰り返した場合に伝える」など、対応方法が決まっていることがほとんどです。まずは園内で決まっている対応ルールを確認しておきましょう。
噛みつきトラブルの予防法

活動の場面では、玩具の数や配置、空間的な余裕、保育者の人員配置などあらゆる側面に配慮した関わりが必要です。しかし、なかなか保育者が子どもの様子を把握しきれない場合もあります。そんな時は、過去の噛みつきトラブル事例などから気を付けるべきケースを予測し、子ども同士の関わりを見守りながら仲介に入れるように準備することも大切です。
噛みつきが頻繁に発生すると、どうしても神経質になってしまいがちですが、できれば子どもたちの活動に過度な制限はせず、楽しく安心して過ごせるように心がけたいですね。
また保育者は、保護者と普段からコミュニケーションをとり、信頼関係を築いていくことも大切。発生したときの対応がスムーズになるだけでなく、環境や体調の変化など、噛みつきトラブルを未然に防ぐための情報を得られるようにしておくといいですね。
子どもに寄り添った関わりを
噛みつきは起きてはいけないことではありますが、子どもに自我が芽生え始めた成長の証でもあります。子どもたちの気持ちも大切にしながら、なるべく寄り添った関わりを実践していけるといいですね。【関連記事】