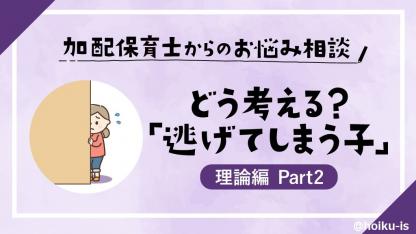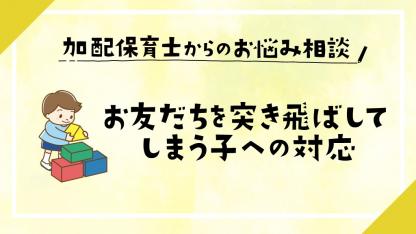今回のケース
今回は、蛇口を見るとどんなときでもお構いなく手を洗って先生に注意されてしまう正太郎君(※)のケースです。正太郎君だって本当は、先生にほめられたいのです。正太郎君は4歳6か月になる自閉症スペクトラムの男の子です。衝動性と多動性の高いADHDの傾向もあります。
正太郎君は蛇口の水で手を洗うのが大好きです。何度注意しても、蛇口を見かけると、どんなときでもお構いなく、手を洗おうとします。保育士はこの子の状況ををどう捉え、どう考え、どう対応したらいいでしょうか?『だから、だってフォーム』=「ボク、○○だから蛇口を見ると手を洗いたくなるんだ。だって、蛇口をひねって手を洗うと●●なんだもん。」を使って考えてみてください。
一つ目の仮説
正太郎君の「自分が好き」「人が好き」を育てるために、正太郎君の「だから」と「だって」をみつけて対応してあげたい。あなたはどんな仮説をたてますか。仮説1
先が予想できなくていつもドキドキしているんだ。だから、水を触りたくなっちゃう(〇〇)。だって、水を触る感覚はよくわかるもの。自分にわかる感覚を感じていると、気持ちが落ち着くよ。(●●)。
対応:目で見てわかるようにスケジュールを示すなど、正太郎君が「次になにをするのか」見通しを持てるように工夫する。水で遊んでいい時間も確保する。
発達障害のある子は、その特性から周りの状況の意味を適切に判断することが苦手です。
そのため、
- 今、周りで何が起きているかがよくわからない
- 先を予想することができない
想像してみてください。もしあなたが知らないところでひとりにされて、周りで人が何かやっているけど何をしているのかわからない、周りの人がしゃべることばもわからない、誰も何も説明してくれず、次の瞬間、何が起きるかわからないとしたら?
不安でたまらないでしょう。そして、この状況では、たとえおいしい食べ物やきれいな花がそこにあったとしても、とてもそれを楽しむことなどできません。発達障害のある子の状況はこれに似ています。
発達障害のある子は「わからない」ことばかりで不安の中にいる。皆さんには、まずこのことをわかっていただきたいと思います。
「安心するための行動」とは
ところで、不安なとき、私たちは深呼吸をしたりして自分の気持ちを鎮め、安心しようとします。正太郎君の場合、その「安心するための行動」が水で手を洗うことなのです。蛇口から出る水が手に当たる感覚、水の匂い、キラキラ光る水しぶき。その感覚は、正太郎君にとって「知っている」「わかる」ものです。
また、水で手を洗う度に先生が「水遊びはしません!」と言っているならば、「水遊びはしません!」ということばも正太郎君にとっては、手を洗うと必ず得られる、という意味で「わかる」ことなのかもしれません。
手を洗うことで得られるこれらの感覚は、わからないことの海の中でもがく正太郎君にとって数少ない「わかるもの」であり、正太郎君はこの世界に「自分にわかるものがある」ことを感じたくて手を洗うのです。
だとすれば、どう対応すればいいのか?
それは、正太郎君が今を安心して過ごせるように周囲が工夫する。これに尽きます。そのためには、「今何をしているのか」「次に何をするのか」を「正太郎君がわかる」ようにする必要があります。
「お散歩に行って帰ってきたら手を洗ってお給食よ」とことばで説明したのでは、発達障害のある子は「わからない」ことがあります。わかるようにするためには「目に見える形で示す」ことをします。
例えば、お散歩、部屋遊び、手洗い、給食、お昼寝など、一日の活動をイラストにして、それを使って正太郎君にスケジュールを示します。
活動の順番にカードを積んでおいて終わった活動のカードを片づけると、いつも一番上に、今している活動が来るので、わかりやすいかもしれません。
そういう工夫をして、今やっていること、次にやることが「目でみてわかる」ようにしていると、そのうち正太郎君も「今はお部屋遊びだな。手は洗えないんだな。お部屋遊びが終わったら手が洗えるんだな。」とわかるようになっていきます。
その過程で、自分のわかる感覚を求めて行う手洗い行動が減ることが期待できます。

二つ目の仮説
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。