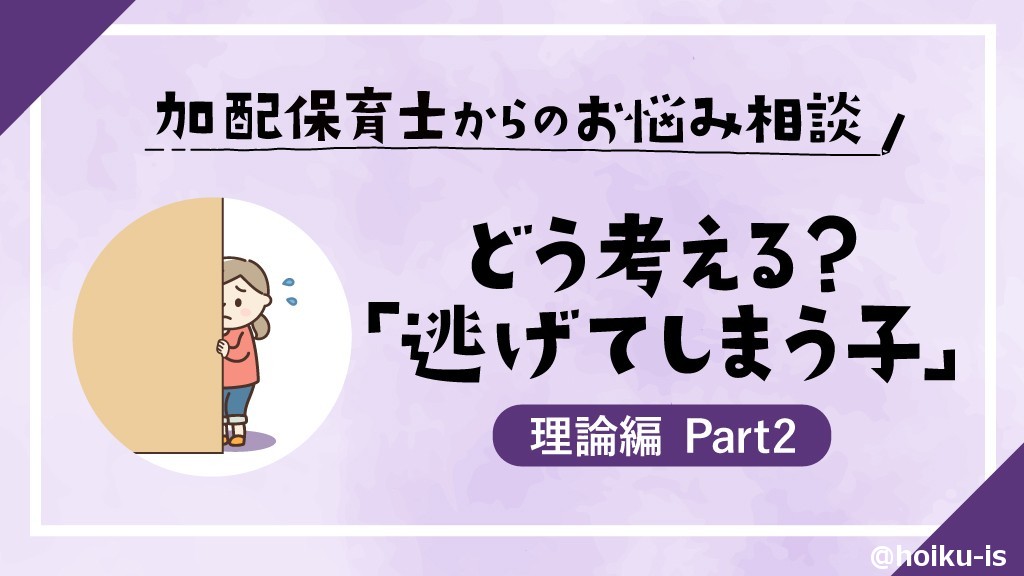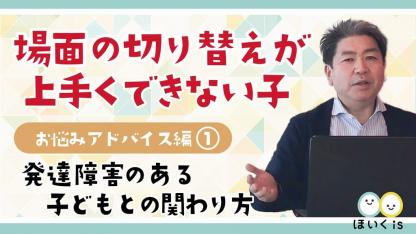前回に引き続き、加配保育士さんから相談のあった「家ではお話をするのに、園ではひとこともお話をしない美知瑠ちゃんとの関係づくり」を考える「理論編」の2回目です。
<前回の記事はこちら>
子どもの3つの願いを叶える関わり方

では、この3つの願いを叶えるには、どのような関わり方が必要なのでしょうか。
①「尊重されたい」という願いを叶える関わり
例えば、- うまく積み木を積めないけれど一生懸命積んでいる子どもに「手伝うよ」と言うのではなく、その子を「挑戦する人」として見守る。
- 塗り絵で花びらを茶色で塗った子どもに「花びらは茶色じゃないよ」と言うのではなく「今日は茶色で塗りたかったのね」と子どもの思いをくむ。
②「安心したい」という願いを叶える関わり
「安心」は、子どもが遊び、楽しみ、学ぶための前提になります。発達障害のある子の場合、感覚過敏のために安心できないでいることが多くあります。 感覚過敏以外にも、人の存在、自分に対する働きかけ、大きな声強い声などで不安になる子もいます。
「安心できない」原因をみつけ、安心できるように環境を整えることが、「安心したい」という願いを叶える関わりです。
③「信頼したい」という願いを叶える関わり

この基本的信頼感が、自分は安心・安全であるという感覚の基盤になります。
子どもに信頼されることの大切さ

つまり、発達障害のある子は安心・安全の感覚が薄弱で、常に不安の中にいるわけで、だからこそ、特に発達障害のある子の場合、保育士が子どもに信頼されることは、とても大切なのです。
では、子どもに信頼されるにはどういう関わりをしたらよいのか。
まず、子どもに「信頼されること」は、非常に、大変に、重要だということを肝に銘じていただきたいのです。片付けや絵を描くことなど何かが「できる」ようになることの「前」に「信頼」です。
子どもは「理解して対応してくれる人」を信頼します。
これまでのコラムでお伝えしてきたことを含めて、様々な手段で子どもの行動の理解を深め、適切な工夫と対応をすることを、あきらめずに続けていきましょう。
それが子どもの「信頼したい」という「願い」を叶える関わりです。
子どもの「願い」が叶えられていない関わりの例

巡回相談では保育士の関わり方も見せてもらいますが、時に「これは子どもの“願い”を叶える関わりではないなあ」と感じることがあります。
それは、例えば次のような関わり方です。
① 子どもに言うことを聞かせよう、子どもを変えようとする関わり方
言うことを聞かせるために、保育士は大きな声で脅すような声がけをしたり、時に子どもの能力を越えた要求をしたりします。「いつまでも、お部屋のおもちゃのお片付けできないお友だちは、明日遊ばせないよ!」
「昨日も言ったよね。先生なんて言ったっけ?先生がお話しする時は、お口は??チャック!」
こんな感じです。
保育士の要求に応えないと叱られるので、子どもは安心できません。
安心させてくれない、大きな声で脅すようなことを言う相手を子どもは信頼しません。
特に発達障害のある子の場合、保育士の要求がわからない、要求に応えられないことが多く、過大な要求による過負荷で子どもがパニックに陥ることがよくあります。
その場合、子どもは、叫ぶ、泣く、先生に近づかない、ものを投げる、他児への暴力、噛みつく、どこかに居なくなる、隠れるなどの行動を示しがちです。
②子どもに流される関わり方

子どもが他の子が遊んでいるおもちゃを奪ってしまっても、「●●ちゃんがこれ使いたいんだって ゴメンね」と元々おもちゃを持っていた子に保育士があやまり、当の「●●ちゃん」は奪ったおもちゃで遊び続ける。
積み木がうまく積めないで崩れたとき、八つ当たりをして保育士の顔を叩いたり、髪の毛を引っ張ったりしても、「そんなに嫌だったの?かわいそう、かわいそう」とことばを返す。
このようにしてよいことと悪いことがはっきり示されない、子どもの気分次第で基準が変わると、子どもは「何をしていいのか?」「してはいけないことは何なのか?」がわからなくなってしまい、不安になります。
また、子どもは生活習慣や社会のルールを学ぶことができません。行動の指針を示してくれない大人を、子どもは信頼しません。
何をするかがわからないことが不安につながる

「今はこうします」「これはいけません」とはっきり示されないと、自分が今どうしたらいいのかが本当にわかりません。
そして「今何をするのか」「次に何をするか」が明確にわからないことは、発達障害のある子にとってとても不安なことです。だから安心できません。 子どもは、くるくる回る、どこかへふらふらっと出ていく、へらへら笑う、いたずらをする、奇声をあげるといった行動をとります。
「①子どもに言うことを聞かせよう、子どもを変えようとする関わり方」「②子どもに流される関わり方」いずれの場合も、尊重されたい・安心したい・信頼したい、という子どもの「願い」は叶えられていません。
その結果、ものを投げる、他児への暴力、どこかへふらふらっと出ていく、奇声をあげるなどの大人にとって「困った行動」が出てきます。
保育士の関わり方が「困った行動」の原因になることも

巡回相談では子どもの「困った行動」へのアドバイスを求められます。
以前、「子どもの「困った行動」の原因には、環境刺激(物理的、人的刺激、活動の難易度が子どもにマッチしているか、生活リズム、家庭環境等)がある」というお話をしました。 それと同時に、実は今回お話ししたような「保育士の関わり方」が「困った行動」の原因であることも往々にしてあるのです。
次回のテーマ
次回は、加配保育士さんから相談のあった「家ではお話をするのに、園ではひとこともお話をしない美知瑠ちゃんとの関係づくり」を考えるための理論編、3回目です。「①子どもに言うことを聞かせよう、子どもを変えようとする関わり方」「②子どもに流される関わり方」
この2つのタイプの保育についてもう少し考えてみたいと思います。
(次回は2022年12月下旬公開予定です)
▼合わせて読みたい!おすすめ記事