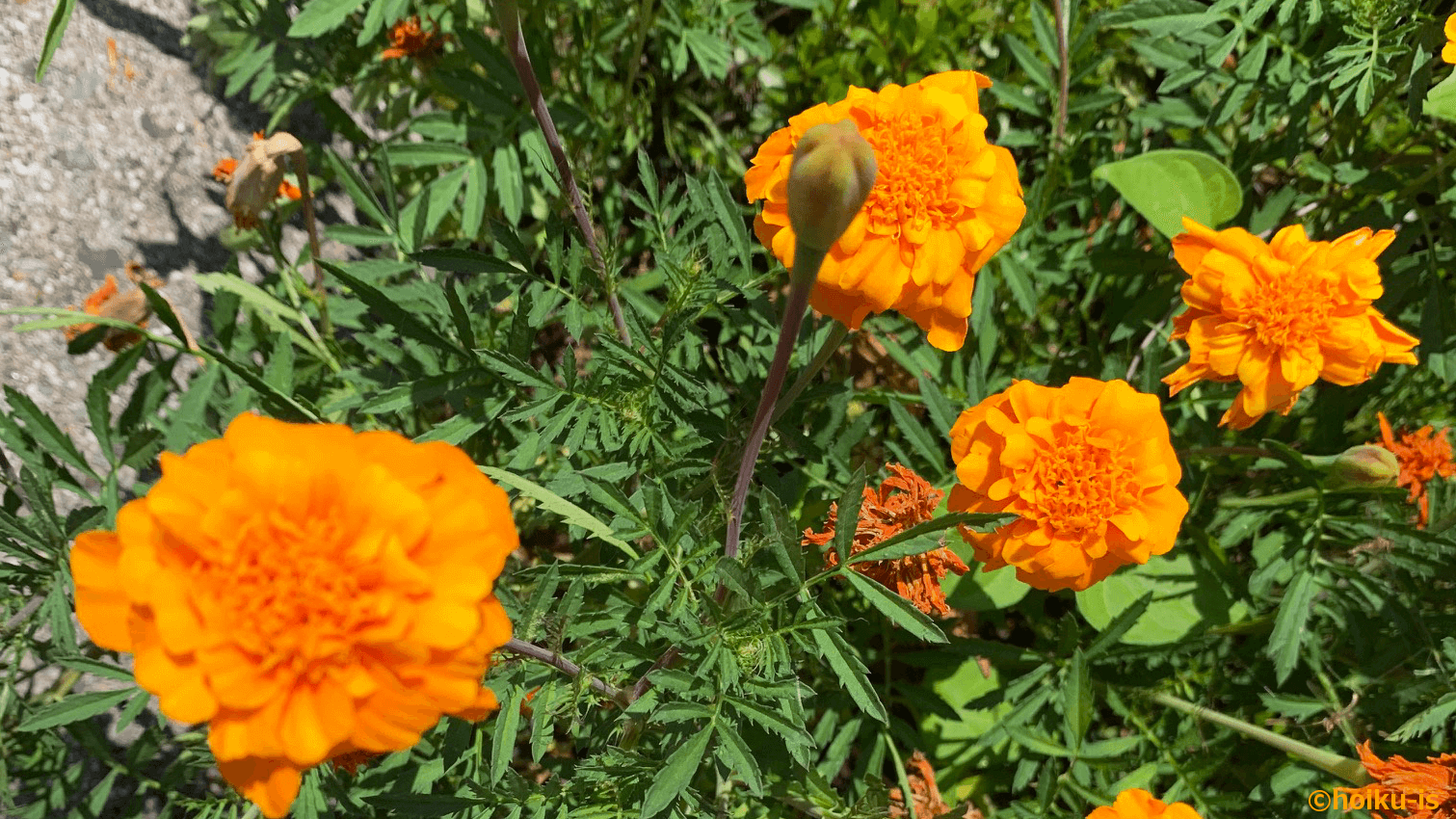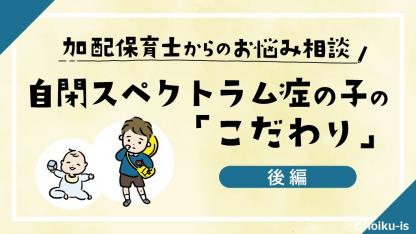今回のケース
今回は、自由遊びの時間になると、部屋から出て行ってしまう裕子さん(※)のケースです。裕子さん(3歳)は自閉症スペクトラムの女の子です。朝の会では返事もしますし、絵本の時間に集中して聞くこともできますが、自由遊びの時間になるとフラフラと部屋から出て行ってしまいます。どこに行ったかわからなくなってしまうと困りますし、他の子はお部屋で遊んでいるので裕子さんもお部屋で遊んでほしいのですが…。
保育士はこの子の状況をどう捉え、どう考え、どう対応したらいいでしょうか? 『だから、だってフォーム』=「私、○○だからお部屋から出て行っちゃうの。だって、お部屋から出て行くと●●なんだもん。」を使って考えてみてください。
「だから」と「だって」を考える
裕子さんは困った顔をしています。「私、お部屋を出て行くから先生に注意されちゃうの。どうしたらいいの? 本当は、先生にほめられたいのに…」と伝えているのです。
裕子さんの「だから」と「だって」は何でしょうか。どう対応したら、裕子さんの「自分が好き」「人が好き」を育ててあげられるでしょうか。
いかがですか?
仮説1
「お部屋では『自由遊び』をしないといけないけど、私は何をしたらいいかわからないの。だから出ていくのよ(〇〇)。だって、お部屋の外にはわかること、楽しめることがあるかもしれないもの(●●)。」
対応:自由遊びの時間になったら、裕子さんが自由遊びの時間を過ごせそうなおもちゃや活動を先生と一緒に探してあげる。
自由遊びの時間は、やることが決まっていません。かといってなんでもいいわけではなく、お水をまく遊びや危険なことなどはダメです。
自閉症スペクトラムの子は、決まったことや言われたことはできても、自由遊びのようなあいまいな制約がある中ではどうしたらいいかわからないことがあります。
何をして遊んだらいいかわからない、これで遊びたいと思ってもそれはしていい遊びなのかわからない。裕子さんは不安で困ってしまいます。
そのような状態では「自分が好き」を実感できません。そして、「なんで誰もどう過ごせばいいのかを教えてくれないの?」と先生や遊んでいる友だちにいら立ちを感じるかもしれません。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。