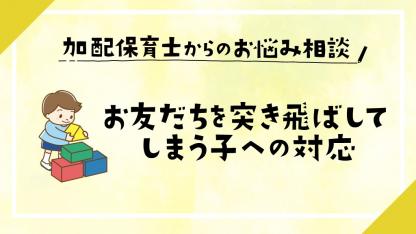今回のケースのおさらい
今回は、最初のケースの回答編ということで、「困った行動」への対応の基本についても書きました。ちょっと長くなってしまうので、回答編は6月と7月の2回に分けてお届けします。では前回のケースを思い出しましょう。
>>発達障害のある子の保育とは?児童発達支援の専門家コラムがスタート
紙芝居の時間に、隣の翔太君を叩いて泣かせてしまう4歳の竜星君(※)。
なぜ、竜星君は翔太君を叩くのか、竜星君にどう対応したらいいか? というお話でした。
「この子はなぜ叩くのでしょうか?」
保育の現場でよく見かける光景です。特に発達障害のある子はよくこういうことをします。ここで皆さんに2つ質問をします。
- Q1 なぜ彼は叩くのでしょうか?
- Q2 1で答えた理由で叩くのだとあなたが考えた理由は何ですか?
保育士Aさんの答え
- Q1 なぜ彼は叩くのでしょうか?
- A1 乱暴な子で、叩くことが悪いと思っていないから
- Q2 「乱暴で叩くことが悪いと思っていないから叩く」と考えた理由は何ですか?
- A2 翔太君を叩くから
でもこうやって問いと答えを並べてみると変だなと思いませんか? 乱暴だから叩く、そう思う理由は叩くから、というのは「右は左の反対、左は右の反対」と同じで、一見もっともらしいが実は何も言っていないのです。このような考え方を循環論といいます。「乱暴だから叩く」は循環論であって、子どもの行動の「理由」は結局解明されていません。
竜星君は乱暴だから叩くと考える先生は、竜星君に「叩いてはだめよ」と言い、「もうしません」「ごめんね」を言わせたりします。
でもその方法では「叩く」行動は減らないことが多い。特に発達障害のある子の場合、ほぼ効果はありません。行動の理由を正しく理解しないで対応しているからです。
ではどうすれば竜星君が叩く理由を正しく理解し、適切な対応がとれるのでしょう。
『だから、だってフォーム』を使って仮説を立てる
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。