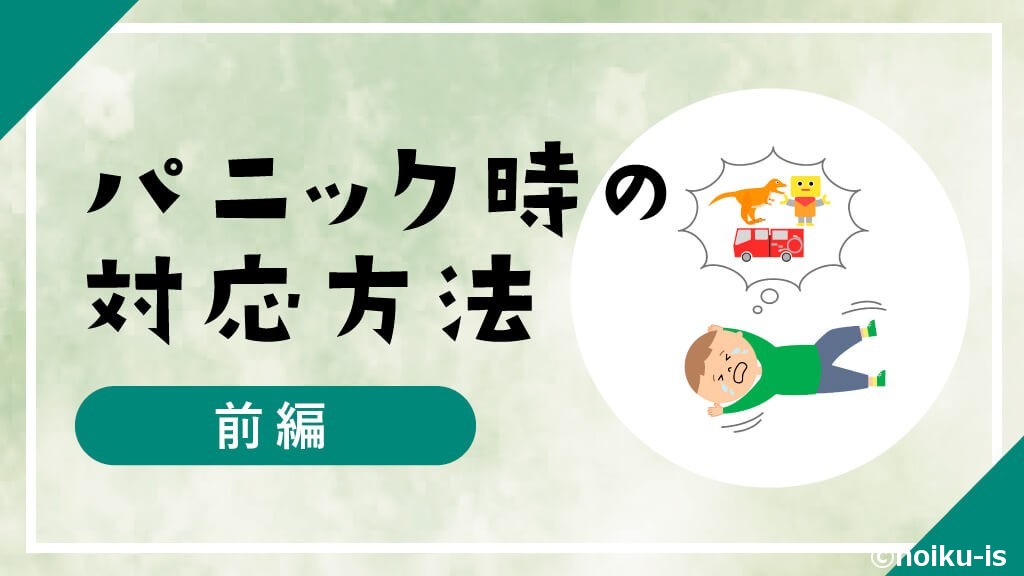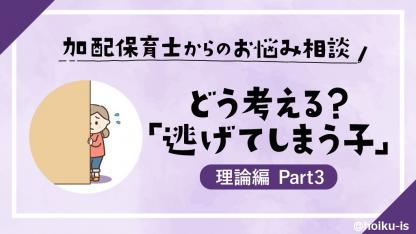>>連載の記事一覧はこちら
今回のテーマ
|
こんなケースはどう関わる? 「子どもが一度パニックになると、そこからなかなか平常に戻れない」 |
パニックに対応する時の基本姿勢
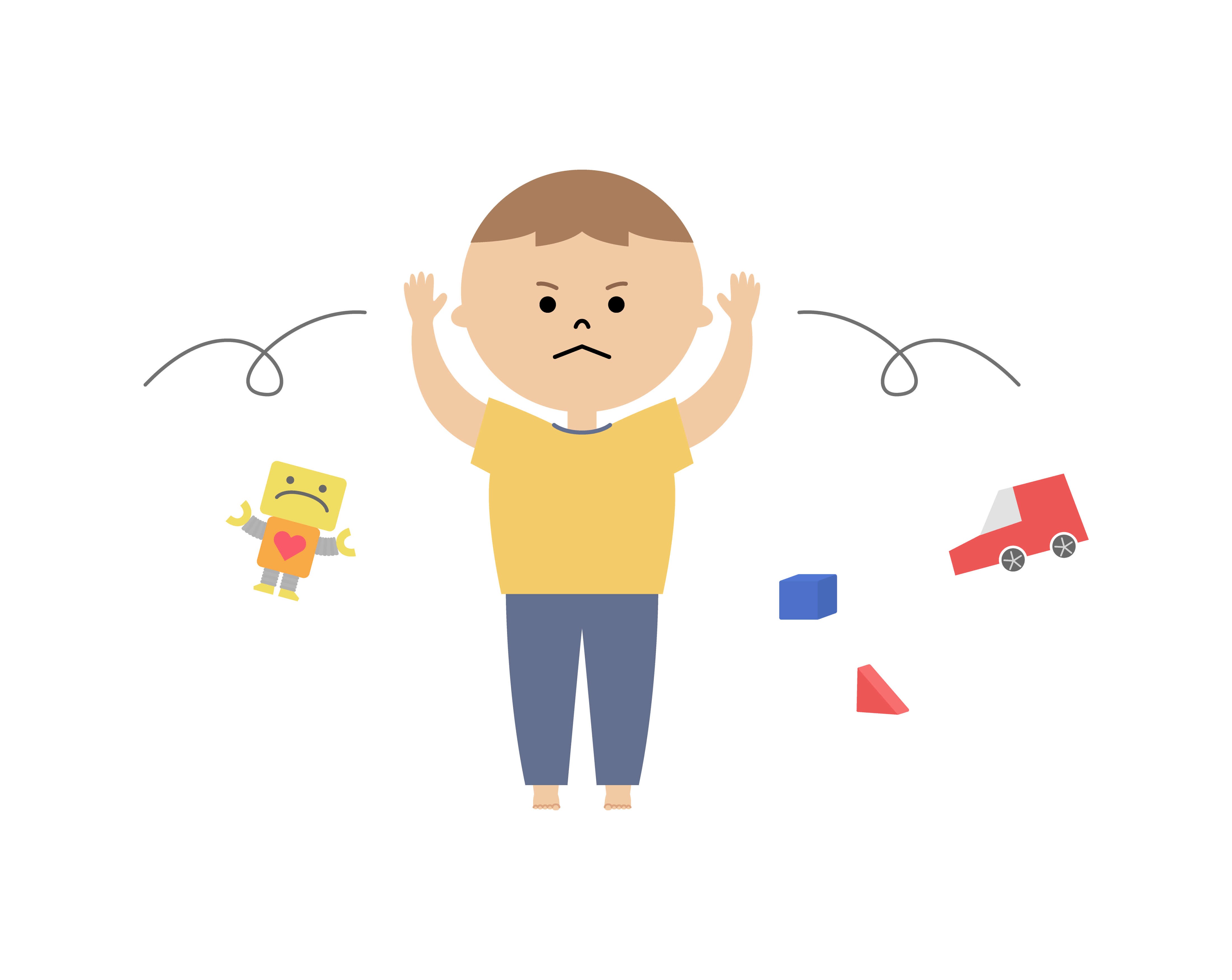
パニックの原因には主に、
- 状況事象の影響
- 感覚過敏
- こだわり
- 予定の変更、予測がつかない状態
- 複数作業、過負担
パニックの原因を特定する方法
パニックの原因を特定する際に大事なことは、この2つです。①子どもがパニックを起こす前後の状況を観察すること
②子どもの気持ちを想像しながら、子どもの気持ちに沿って原因を考えること
パニックの前後の状況を観察しても原因が見当たらない場合には「5つの原因」のうち、
「1、状況事象の影響」を考えます。
そして「仮に」でもいいので原因と思われるものを特定し、原因に応じて対応します。
対応したことでパニックが起きなくなったならその原因で「ビンゴ」!
変わらないならば他の原因を探します。パニックは困るので、どうしても子どもを叱りたくもなりますが、叱ることは解決には結びつきません。
どうかあくまでも「子どもの気持ちに沿う」ことをいつも頭において「原因」を探してほしいと思います。
パニックを防ぐ対応「状況事象の影響」

状況事象の影響への対応
「困った行動」に影響を及ぼす要因を状況事象といいました。 状況事象に対しては、直接的な対応と間接的な対応があります。●直接的な対応
室温や光や湿度、のどの渇きなどが状況事象かもしれないなら、カーテンや室温調整、加湿器の使用などを試します。また、こまめに水分を取らせるなどで対応してみます。
苦手な子どもや人が状況事象かもしれなければ、その子どもや人とは必要以上の接触が起こらないように工夫します。
●間接的な対応
睡眠不足や食事リズムの乱れ(朝食を抜く、お菓子のみの食事など)や家庭での叱責などは保育現場で直接的な対応をするのは難しく、家庭での対応が必要になります(間接的な対応)。

保護者に協力を求める場合
ただ、間接的な対応で保護者に働きかける際は、少し配慮がほしいと私自身は思います。発達障害のある子の場合、保護者は子育てに疲弊していることが多いです。わかっていても「朝ごはんを間に合うように食べさせる」「睡眠をとらせる」ことが本当に大変なこともあるのです。
そこに例えば、「朝ごはんを食べてこないと園で機嫌が悪くて困ります。きちんと食べさせてください」とガツンと言われてしまうと、保護者はしんどくなってしまいます。
担当保育士と保護者との信頼関係の度合い、保護者のキャラクター、対応のしやすさの度合など様々なことを考慮します。
どういう言い方で伝えるか、保護者へのアプローチを考えてほしいと思います。

保護者への上手な伝え方
周囲から子どものことをあれこれ言われてばかりの中で、保育士から直接何か言われることに過剰に反応してしまい、なかなか情報交換ができない保護者もいます。保護者全体に向けた形で、子どもとの関わり方や睡眠や食事の大切さについて学ぶ会を持ったりお便りでとりあげるという方法だと、保護者が抵抗を感じることなく、伝えたいことを伝えられます。
「睡眠が不十分」という状況事象があった「千春ちゃん」のケースでは、園では、運動量を多くしたり日光に当たったりと日中の活動性を高めること、しっかり午睡ができるように工夫することができます(直接的対応)。
保護者に配慮した上で睡眠の状況を聴き取り、保護者に可能な対応を求めることも考えていきます(間接的対応)。

パニックを防ぐ対応「感覚過敏」

前回ご紹介した修平君のケースでは、指や手に触覚過敏があると予想されるので、糊付けのときに薄いビニール手袋を使ったり、先生や友だちに手伝ってもらったりすることを考えました。 感覚過敏の原因を排除することが難しい場合は、感覚過敏の原因から遠ざかることを考えます。
|
(感覚過敏の原因から遠ざける例) 聴覚過敏がある場合、大きな音で音楽を流す集会には参加しない、節分の鬼の面を異常に怖がるならその子の前では鬼の面はかぶらないなど。 予告をすることでパニックにならないですむこともあります。 |
今回のまとめ
今回は、パニックの原因の特定方法から「状況事象の影響」と「感覚過敏」が原因になっている場合の対応方法をお伝えしました。次回は「こだわり」「予定の変更」「複数作業」が引き起こすパニックの対応方法をお伝えします。
(2022年1月下旬配信予定です)
▼ほかおすすめ記事はこちら