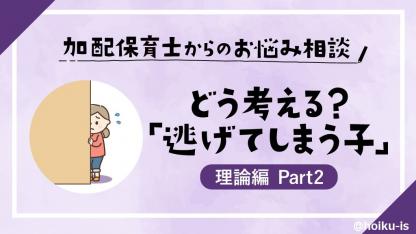粘土遊びの機能
粘土遊びも、前回の砂場遊びと同じく保育園では定番の遊びです。まずは、粘土遊びの機能から見ていきましょう。主に次の6つの機能があります。
①さまざまな感覚入力を経験できる
砂場遊びと同じく、粘土遊びでもさまざまな感覚刺激を受けることができます。- 触覚刺激:粘土のヒヤッとした温度の感触、取り出したばかりの粘土のゴツゴツした感触、丸めて転がした後のつるつるの感触、さまざまな粘土の手触りなど、皮膚を通して感じる刺激
- 視覚刺激:カラフルな粘土の色や、自分の作品を見たり、周囲の友だちが粘土遊びをする様子を見たりするなどの視覚刺激
- 重さの感覚(固有覚):小さい球状に丸めた粘土、大きい球状に固めた粘土、細長く伸ばした粘土など、さまざまな形と大きさの粘土の重さの違いなど、重さを感じる感覚刺激
- 嗅覚:粘土の独特の匂い
②手先が器用になる

手を使うことで、人間の脳は他の動物に比べて飛躍的に大きくなりました。粘土をこねたり丸めたりという動作は、もちろん手や指を使いますし、粘土遊びで使う型やヘラなどの道具を使うと、手ではできない変形や、より繊細な造形ができます。
楽しい、もっとこうしたいという能動的な思いで手や指、道具を使ううちに手先が器用になります。
③模倣力が向上する
子どもは自分もいろいろ作ってみたいと思い、丸める時の手の使い方、道具の使い方など、保育士や友だちのやり方をじっと観察します。そうして動作を理解し、記憶し、自分で再現するうちに模倣(まねする)の力がついてきます。模倣力は、他の活動やことば、社会性など、さまざまな能力を獲得する上で重要な力です。④創造力や発想力が育つ
粘土遊びはいろいろに展開できます。単純にちぎる、丸める、伸ばすというところから、伸ばした粘土を蛇に見立てたり、立方体や三角錐の形を重ねて「家」を作ったり、粘土をのし棒で伸ばして「パン」を作りパン屋さんごっこをしたり、子どもの発達段階に応じて、感覚あそびから創造力や発想力を発揮できる遊び、友だちと共同でする遊びまで、幅広い遊びができます。また、落ち葉や枝、どんぐりなどの自然の素材、割りばしやボタンなどの素材と組み合わせて、さまざまなものを作ることができるのも粘土のおもしろいところです。
⑤集中力の向上
粘土の感触や、ちぎる、丸める、固める、重ねるなどの動作、想像力を働かせながら自分で作りたいものを考え、計画し、目標の作品を作り上げる、作品を使って友だちと遊ぶなど、粘土遊びのさまざまな要素が子どもを魅了します。以前のコラムで、遊びとは「自分から、満足するところまで、楽しむもの」だというお話(※)をしましたが、粘土遊びは、自分から、満足いくまで作る、楽しいという点で、まさに「遊び」です。
夢中になって遊んでいるとき、子どもは自然と集中します。独特の手触り、思い通りに形を変えられるという特性を持つ粘土で思う存分遊ぶ中で、子どもは集中する経験を積み、集中力がついてきます。同時に、そうして思いっきり遊ぶことで子どもは、心の落ち着く時間と安心感を得ることができます。
(※)『発達障害がある子と“ルールのある遊び”、どう対応する?【保育者の関わり講座】』
⑥抽象的な言葉を含む、ことばの理解がうながされる
粘土遊びでは、実にたくさんの種類のことばが登場します。「ちぎる」「丸める」「伸ばす」などの動詞、「小さい」「重い」「軽い」などの形容詞、「1個」「2枚」などの数詞、「本」、「個」、「枚」などの助数詞、「三角」「四角」などの形を表すことばなどです。
子どもは、ことばを、実体験を通して学びます。特に、形容詞や数詞などの抽象性の高いことばは、実体験を通して学ぶことが不可欠です。その点、粘土遊びは楽しい、伝えたい、わかりたいという状況の中で、さまざまなことばを聞くので、多くのことばの理解を深めることができる貴重な機会になります。

発達的視点からの粘土遊びでの関わり方のポイント
続いて、粘土遊びでの保育者の関わり方について一つずつ見ていきましょう。①子どもの興味を確実に捉え共に楽しむ

では、子どもの興味を捉えるにはどうしたらいいのでしょうか?
まずは、子どもの遊び方をじっくりと観察します。粘土でどのような遊びをしているか? 感触を楽しんでいるのか? ちぎるのか? ちぎって丸めることに興味を示しているのか? 粘土用のナイフで切るのか? などを静かに観察して子どもの興味と楽しみ方を捉えます。
そして、子どもの遊びを共に楽しむにはどういう関わりをしたらいいかを考えます。子どもが遊ぶ様子を側で楽しむように見ていることが良いのか、それとも、子どもと同じ動作で遊ぶことが良いのかなどです。
例に挙げた2つは大した違いはないように思えますが、発達特性のある子の場合、これが大きな違いだったりもするのです。
子どもに「先生はこの粘土遊びをいいと思ってくれる」「この遊びを一緒に楽しんでくれている」と思ってもらえるような関わりを目指しましょう。子どもがそう思ってくれているか? は、子どもの表情や声、子どもたちから発せられる「雰囲気」から読み取ります。最初はうまくいかないかもしれませんが、ぜひそのような関わりを目指していただきたいと思います。
②粘土遊びをさらに楽しむことができるようにガイドする
子どもの興味や楽しさを中心にすることを前提とした上で、子どもがさらに粘土遊びを楽しむことができるように、保育士がガイドすることも大切です。粘土を丸めているなら、子どもよりも極端に大きい球を作ってみたり、反対に極端に小さい球を作る。粘土で車を作っているなら、その子の好きな標識や信号機を作ったりするなどもアイデアの一つです。子どもが思いついていない遊び方の提案です。
子どもからすると「おっ、それおもしろい」「やってみたい」「もっとこうしてみたい」と、思うようなアイデアを見せることで、さらに子どもが粘土遊びを楽しむことができるよう「ガイド」します。
忘れてはいけないことは、常に、「子どもの興味や楽しさを中心に置く」ことです。特に発達特性のある子どもの場合、「ガイド」は慎重に行います。
例えば、自分の遊びをひたすら繰り返す子ども、粘土遊びの手順にこだわりがある子ども、粘土遊びに使う道具を触ってほしくない子どもなど、粘土遊びの楽しみ方に強いこだわりがある場合があります。ですから、強引に保育士のアイデアを押し付けないように細心の注意をしたいものです。
③ことばがけの仕方を意識する
先ほどお話したように、粘土遊びは子どものことばの理解をうながすいい機会です。意識してことばがけをしましょう。ひとつは、オノマトペを上手に使うことです。オノマトペは語感が子どもの注意を引きますし、楽しいです。また成人語の理解が難しい子どもでも、オノマトペだと伝わることが多くあります。粘土遊びの場面であれば、粘土遊びがさらに楽しくなるように、「コロコロ」「ビヨーン」「ペタペタ」などの表現を使ってみるといいかもしれません。
また、「丸めよう」「重ねてみて」「1こ、2こ、3こあるね」「高くつめたね」など、子どもの理解に合わせたことばがけを意識的にすることで、抽象的なニュアンスを含むことばの理解をうながしたいものです。
ただし、発達特性のある子の場合、粘土遊びに集中していると保育士がことばをかけても聞いていない(耳に届いていない)ことが多くあります。
子どもの粘土遊びへの集中を邪魔しないように、でも子どもの耳にことばが届くように、根気強く、繰り返し、単語で話しかけましょう。
ことばのリズムや音に興味を持てるように、心地よい、明るい声で、話しかけることも心がけたいです。
発達的視点からの粘土遊びで注意したいこと

①感覚過敏に注意する
油粘土のべたべたした感じや匂いを嫌う子どもがいます。そのような子どもの場合は、小麦粉粘土を代替として使うなど、子どもが安心できる材料を使いましょう。②異食、誤飲、アレルギーに注意する
子どもによっては、粘土を口に入れてしまうことがあります。そのような恐れのある子どもの場合は、小麦粘土、お米粘土、寒天粘土などを使うのもアイデアです。小麦アレルギーの子どもの場合には、小麦粘土ではなく、お米粘土や寒天粘土などを選びましょう。
粘土遊びは発達特性がある子も楽しく遊べる活動です。ぜひ、取り入れてみてください。
【関連記事】