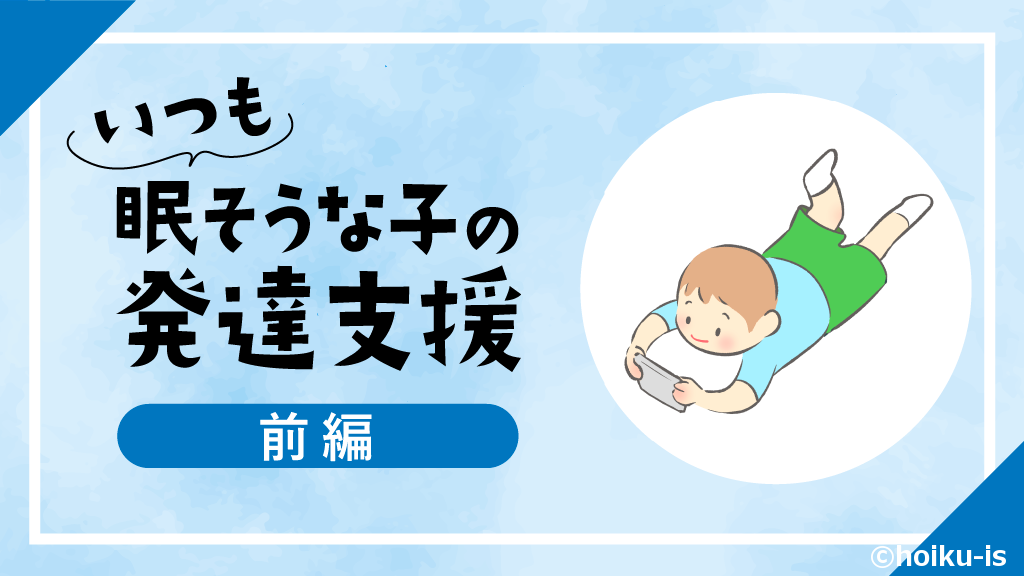今回のテーマ「眠そうな子」の原因究明
これまで2回にわたって「睡眠の基礎知識」をお話ししました。 今回からは、より具体的に「園でいつも眠そうな美空ちゃん」への対応策を考えていきます。まずは今回のケースの振り返りです。
|
美空ちゃんのケース 4歳の美空ちゃんは、登園時のお母さんとのお別れがとても大変で、30分は大泣きをします。30分を過ぎるとおままごとなどで遊び始めるのですが、しばらくすると、うとうとすることがよくあります。大好きな給食の時間になると目をさましますが、食事中もうとうとし始めることも。保育園にいる間はとにかく眠そうです。 |
幼児の睡眠障害の基準
前回お話しした基準は、次のようなものでした。① なかなか入眠できない
② 睡眠中、何度も目が覚めてしまうため睡眠がまとまらない
③ 一度目が覚めると1時間以上起きている
④ 睡眠時間が短い(9時間以内)
⑤ 不機嫌で泣いてばかりいる
美空ちゃんは園で⑤の状態であり、給食の時間ですらウトウトしてしまいます。眠いと不快だし集中できないので、いろいろな活動も楽しくできません。
美空ちゃんが楽しく園生活を送るには睡眠の問題への対応が必要です。具体的にどのように対応すればいいのでしょうか?
1、睡眠の状態を把握する
まず、最初に行いたいのが睡眠の実態把握です。- 入眠時間
- 起床時間
- 夜中、目が覚めてしまうかどうか
2週間の間、毎日記録するのはかなり大変なもの。そこでおすすめなのは、日本眠育推進協議会のサイトの睡眠記録表「すいみんログ」 のフォーマットです。昼寝を含めてその日寝ていた時間を黒く塗るだけで記録できます。

|
日本眠育推進協議会「すいみんログ」 https://www.min-iku-suishin.org/miniku_log/ |
睡眠の問題に対応するには、家庭の協力が必須です。園での状況と睡眠の問題への対処の必要性を保護者に伝え、協力してもらいましょう。
2、早寝早起きを困難にしている要因は?
次に、その子にとっての「睡眠障害の原因」を考えてみます。一般的に、幼児の睡眠困難の原因には次のようなものがあります。
- 起床時間が一定しない
- 太陽の光を浴びる日中の活動(元気に身体を動かす)が少ない
- 日中のストレス
- 就寝直前の入浴による体温上昇
- 入眠前の興奮状態(スマホ、DVD、遊び)
- 他の家族と一緒に深夜まで起きている
- 疾患等
【原因1】起床時間が一定しない

平日と休日のリズムは同じ?
平日は早起きするが、休日は遅くまで寝ているために起床時間が一定しないことはよくあります。起床時間が一定しないと、睡眠リズムが崩れがちになります。前回お話ししたように、人は朝きちんと起きて太陽の光を浴びることで、夜になると自然に眠くなり、朝になると自然に目が覚めるという規則正しい生活リズムができます。
反対に、朝きちんと起きて太陽の光をしっかり浴びることができないと、夜になっても眠くならず、なかなか寝つけない、寝つけないから朝起きられなくて朝の太陽の光を浴びられない、という悪循環に陥ってしまいます。
休日に気を付けたいポイント
平日は遅刻できないから無理やりでも起こすが、休日くらいゆっくり寝させてあげたいという気持ちはよくわかります。しかし「休日だけは朝遅くまで寝る」ことが、起床のリズムを崩す原因になることが多いのです。
休日も平日と同じく、朝きちんと起きて太陽の光を浴びることが、睡眠リズムを保つ上ではとても重要なのです。
【原因2】太陽の光を浴びる日中の活動が少ない

人は脳の温度が低下するときに眠くなります。運動をすると脳の温度が上昇するので、運動しないときよりも、脳の温度の「下がり幅」が大きくなります。その結果、より眠くなり、快眠が得られるのです。
日中に運動することのメリット
太陽の光の下で運動をするとセロトニンが作られるので、眠気を誘う物質であるメラトニンも多く作られることになります。この意味でも、日中の運動は良質な睡眠に結びつくのです。逆に、太陽の光を浴びず、運動をしないと、運動によって脳の温度が上がることもなく、セロトニンも分泌されないので、眠りにくいことになります。

【原因3】日中のストレス
ストレスが睡眠障害の原因になることはよく知られています。入眠時の自律神経は、体をリラックスさせる副交感神経優位になります。しかしストレスがあると、緊張するときに優位になる交感神経が活発になるので、リラックスできず眠れないのです。【原因4】就寝直前の入浴

子どものいる家庭では、夕食が6時から6時半くらい、入浴は夕食後の8時くらいから、という家庭が多いのではないかと思います。
入浴~入浴後の体温変化に注目
お風呂から上がると徐々に体温が下がりはじめ、2時間~2時間半経った頃に眠くなると言われます。例えば午後8時~30分間入浴すると、午後10時半~11時頃に眠くなることになります。つまり、8時の入浴では9時には眠くならないのです。子どもがなかなか寝つかないのには、入浴の時間帯が関係していることもあるのです。
もし9時に眠くなるようにしたいなら、入浴の最適時間はその2時間から2時間半前の6時半くらいからということになります。それを考えると、早い時間に眠るには、時間を都合して「夕食前にお風呂に入る」のがよい、ということになります。
【原因5】入眠前の光刺激や興奮

注意したいスマホ・パソコン・テレビ
スマホ、パソコン、タブレットなどからは強い光が出ていて、その光が目に入ると脳は太陽の光を浴びたと錯覚して、メラトニンの分泌量を抑制します。そうすると夜になっても眠くならず、脳が目覚めてしまって眠りが浅いなどの睡眠障害が起きやすくなります。
スマホ、パソコン、タブレットの光に限らず、寝る場所に光や音の刺激がたくさんあると、脳が目覚めてしまい、睡眠に影響が出ます。また、寝る前に親子で激しい運動をしたり、おもちゃで遊んだりすると、交感神経が興奮してしまい、体温が上がって、眠りにくくなります。
【原因6】他の家族と一緒に深夜まで起きている

深夜まで娯楽を楽しむ親や年上の兄弟姉妹の部屋から漏れてくる声や音、そして光などが刺激になって、なかなか寝つけない子どももいるのではないでしょうか?
また、家庭によっては父親の帰宅時間が遅く、帰ってきた父親と夜遅くに遊んだり、遊びはしないけれど父親が気になって寝つけない、こともあります。
【原因7】疾患等
アトピーが痒い、呼吸器疾患で息が苦しいなど、疾患が睡眠障害の原因になっていることもあります。次回は、この7つの「子どもの睡眠障害の原因」についての話を前提に、「園でいつも眠そうな美空ちゃん」にどう対応するかを具体的に考えていきます。
▼こちらも読みたい!おすすめの記事