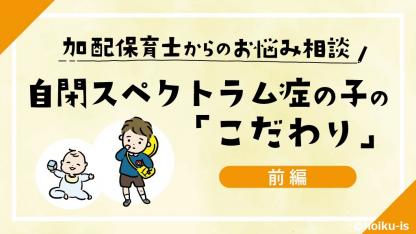>>連載の記事一覧はこちら
今回のポイント
今回は「知的に重度で自閉スペクトラム障害のアオト君」の「遊び」をみつけるというテーマの最終回です。「ブロックや人形を渡してもぽいっと放り投げてしまうなど、なかなか園生活で好きな遊びを見つけられない、アオト君の具体的な「遊び」を考えます。
まずは、前回検討した①~④のサポートポイントを思い出してみましょう。
まずは子どもの状態を観察する
「遊び」の時間に、アオト君がいる場所、見ていること、やっていることを観察します。
アオト君が「いる場所」は?

決まった場所によくいるなら、その場所が好きなので、「なぜその場所が好きなのか」を考えます。
例えば「いつも窓の近くにいる」「窓から入る風を浴びようとする様子や窓の方を見るような様子が見られる」なら、風が好き?日光が好き?と想像してみます。
好きな感覚がわかればその感覚が得られる「遊び」を考えられますし、また、「遊び」の場所になる、安心できる心地よい場所がわかります。
アオト君がよく「見るもの」は?
アオト君が何かを「見る」のは、その「モノ」や「コト」や「場所」を認識しているからです。認識していなければ、注目することもなく、視線は「スーッ」と流れてしまうはずです。
「見る」こと全部が「やりたい」「行きたい」ことを意味するわけではありませんが、「遊び」になりえるのは認識できるものだけ(サポートポイント①)です。
アオト君が認識している「モノ」や「コト」や「場所」を知ることは、「遊び」をみつける手がかりになります。
アオト君が「やっていること」は?
何かのおもちゃを触っているならば、アオト君はそのおもちゃを認識しており、アオト君はそのおもちゃを触ることで何かしらの刺激や情報を得ています。しかしいま、アオト君は「ブロックや人形を渡すと投げてしまう」のです。
このことから、例えばブロックについて言えばアオト君はブロックを「モノ」として認識することはできるが、ブロックの機能(積んだり、穴にいれたりして「遊ぶ」ことができる)やブロックの「遊び」方は理解していないことがわかります。

アオト君を観察した結果
実際にアオト君の自由時間を観察した結果、●ブロックは投げてしまうが見る
●よく窓の近くにいる
ということがわかりました。
そこで「遊び」を探すにあたってまず、
①ブロックを使う②風の刺激を検討することとし、加えて③その他の刺激についても検討することにします。
具体的なサポート方法4ステップ
サポート1、認識できる活動(刺激)の検討
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。