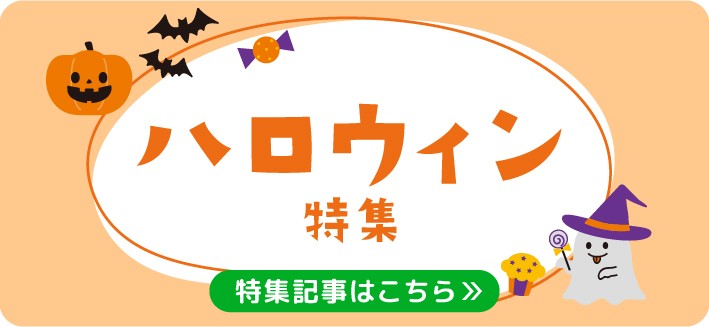※ご視聴にはほいくisメンバー・園会員(いずれも無料)へのログイン・登録が必要です
子どもによる変化を見逃さない

保育を行ううえで、環境設定は大切ですよね。子どもの主体性を引き出すような環境を作るにはどうすれば良いでしょうか。
私は、“子どもが関わって変化するもの”を見逃さないことが大切だと考えています。例えば、子どもたちが遊ぶ場所に積み木を置いたとします。でも、それを子どもがバラバラとひっくり返したとしたら? そこには何かそうさせるものがあったんだな、と思い、バラバラっとすることを一緒に楽しみます。そこから保育を始めていく、という感じです。大人が先に未来を想定してものを出すわけですが、その環境を子どもがどう感じ取ってどう動いたのか、そこが環境設定のスタートだと思います。
子どもが動いたときをスタートとすれば、「なるほど、ここが居心地がいいんだな」「ここで使うかと思ったけれど、こっちに持ってくるんだな」など、いろいろ見えてきますよね。
環境設定のポイントは、子どもがどう動くのかをよく見ることです。
もちろん、“何をどこに置くのか”という設定も大切です。そこで私が考えるのは、“一種類にしない”ということ。
10人子どもがいれば、10個あればいいのかというと…実はそれでも全部欲しい子が出てくるんです。それよりも、いろいろな種類のものが2,3個ずつある方が、それぞれの「おもしろい」を見つけられる子どもたちになっていきます。多様であることが重要ですね。
また、おもちゃはできるだけ見立てられるものの方が良いと思います。スポンジだったらケーキにもなるし、洗濯もできるし(笑)。でも、ケーキの形のおもちゃは、ケーキにしかならないですよね。
子どもの遊びが広がるようなおもちゃがいいのですね。私が見た光景では、積み木を見立て遊びに取り入れている子が多くいました。
それはすごく大切なポイントです。中には、積み木はここで遊ぶ、おままごとはここで、と整理してしまう保育者もいます。でも、できるだけそれをせず、子どもがさまざまなものを持ち込んだり思いがけない使い方をしているのを大事にしてほしいと思います。そこに、その子なりの目の付け所やこだわりがあるので、それを一緒におもしろがる。そうすると、子どもはどんどん自分で考えていろいろなことをするようになっていきます。
もちろん、何でも「いいよ」というわけではなく、そこに子どもが表現したい大事なものがあると感じたときに、子どもの動きを見守ってみてください。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。