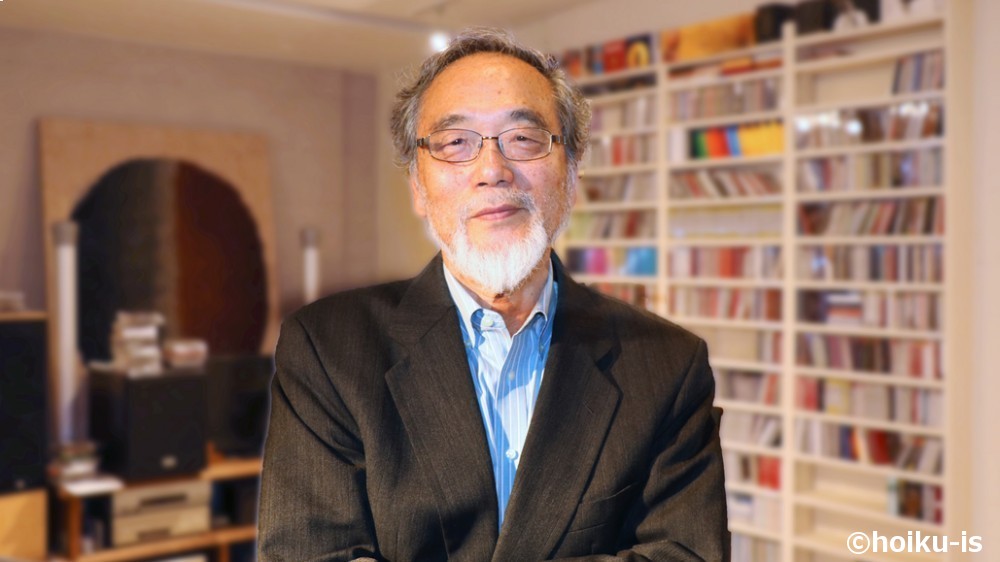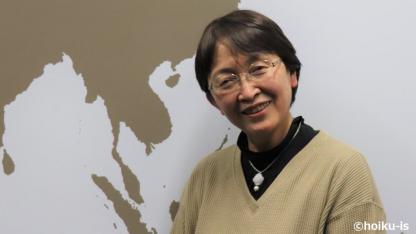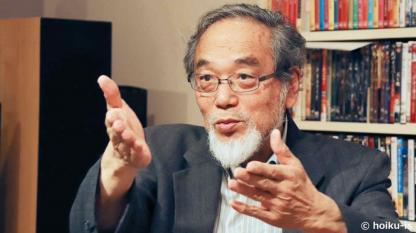保育を取り巻く環境は常に変化しています。特に近年は、2018年4月に施行された「保育所保育指針」を始めとする3法令の改定、2020年からスタートする教育改革など大きな変革期を迎えています。「いま保育で何が起きているのか?」について、この分野の第一人者である汐見稔幸先生に伺うインタビューシリーズです。
第1回のテーマは、保育園・幼稚園と小学校との連続性、「子ども主体の保育」とその後の集団生活への繋がりについて。「子ども主体」という言葉と共に、子どもの興味や意思を大切にした保育が注目されています。一方、小学校で集団生活が始まると、逆に子どもたちが不自由さを感じてしまうのでは…? という素朴な疑問をぶつけてみました。
「子ども主体」は「好きなことをする」ではない
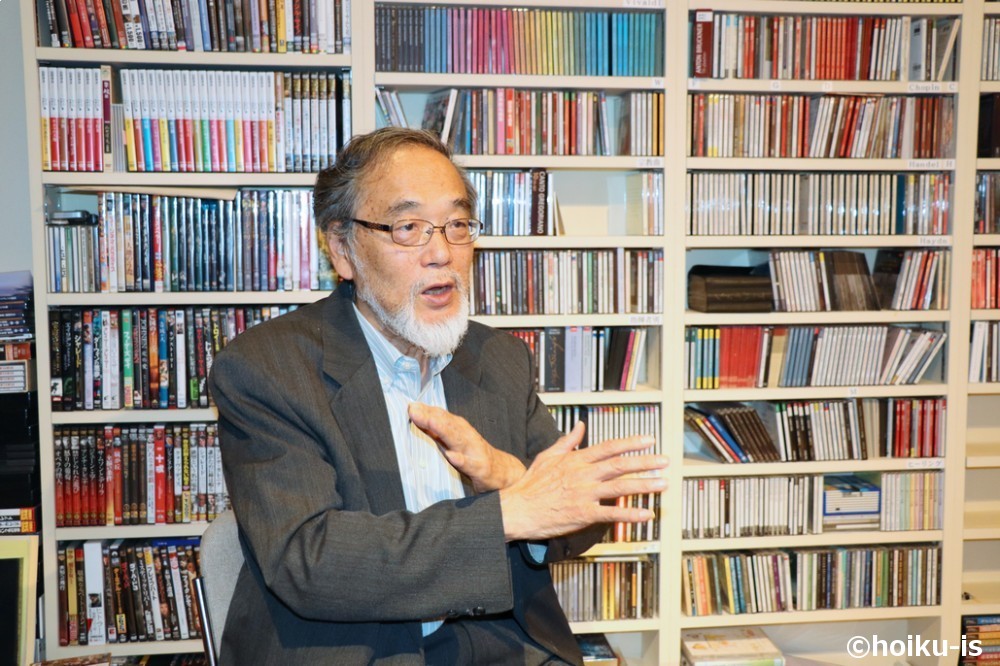
保育所保育指針では「子ども主体の保育」が謳われています。そうなると、小学校での集団生活で困るのでは? という疑問を持つ方もいるようです
子ども主体の保育をしていると、集団生活でうまく行動できない子どもになってしまうのではないか、というのはちょっとした誤解がありますね。
「子ども主体の保育」というのは、それぞれが好きなだけ好きなことをやればいいという意味ではありません。自分でやりたいことを見つけて、方法を考えて達成していくこと。その自主性や主体性を園で育てていこうというのが趣旨です。
例えば運動会を開催するにしても、先生が種目や方法を全部決めて子どもたちが訓練していくっていうのをよくやりますよね。
そうではなく、「今年はどんなものをお父さん、お母さんに見てもらいたい?」ということをみんなで議論して決める。それが子ども主体なのです。
子どもに任せて、どうすればいいのかを自ら決めていく経験を積めば、集団的な行動はかえって自覚的にやれるようになっていくはずです。
「子ども主体で育ってきた子どもたちはわがままなのでは?」「座っていられないのでは?」という考えは、そもそも「子ども主体」の解釈が間違っているのですね
そうです。いつも先生が指導その通りにさせていると、「先生が言わなきゃ何してもいいんだ」と思う子になってしまいますよね。
しかし、子どもたちが自分で決められる世界が増えてくれば増えてくるほど、子どもたちは「自分たちに任されているのに、自分たちがわがままになったらどうなるんだろう」ということを考えます。逆にしっかりしますよ。
子ども主体で育った子どもが集団生活に適応しにくいというのは、誤解ですね。
幼保小連携で大切なことは何でしょうか?
遊びの中でどう相談しているのか、躓いたときにはどうしているのか。そういうやり方を幼稚園や保育園でどこまでやってきているのか。これから小学校に来る子どもたちが、どういう成長過程を経ているのかを小学校の先生に把握してもらうことが、幼保小連携で一番大切なポイントだと言えるでしょう。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。