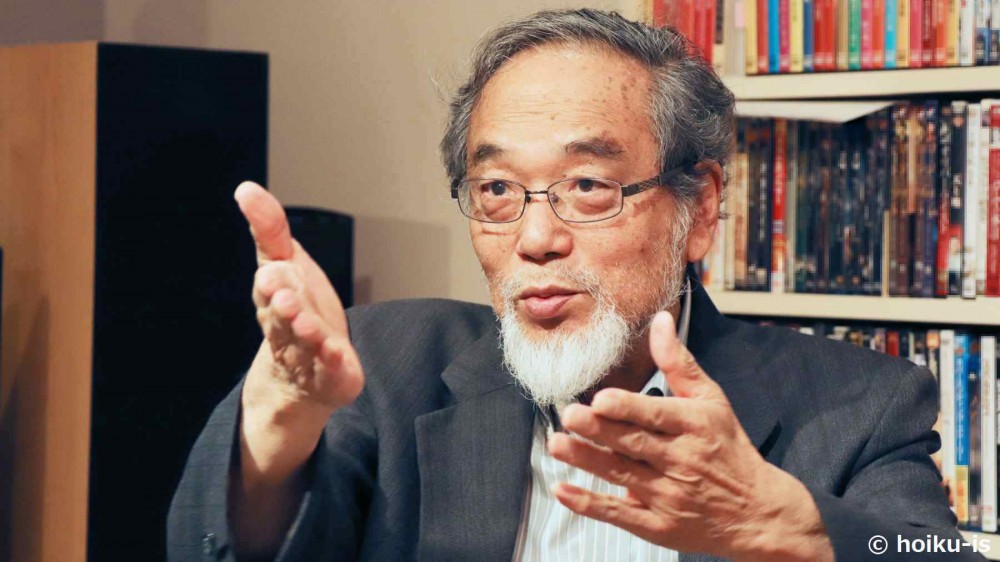「教育」と「保育」をもう一度同じに

幼稚園の先生と保育園の先生では、「教育する人」「保育する人」というイメージの違いがあります。実際も、例えば保育士だとあまり教育をするという感覚ではない方も多いのではないでしょうか。
確かにそうですね。しかし、今は保育と幼児教育は全く同じものだということになってきています。本当は保育という言葉は、戦後は「保護教育」という意味で使っているんです。
子どもは保護しながら教育をしなければいけない。だから幼児期における教育のことを「保育」というのだと言っていたんです。しかし保育園が「保育」と言い出したので、幼稚園がそれに対して「教育」だと言い出した背景があります。
今、「幼児教育振興法」というものが国会に出されているんです。これだけ保育や幼児教育が大切となっているのに、それを支えている法律がないので作ろうとしているのですが、ここでは、幼稚園、保育園、認定こども園は対等の幼児教育機関になっています。
そういう動きがあるんですね。以前、ある認定こども園の取材で園長先生から「幼稚園教諭の方と保育士の方では同じ職場でも意識の差がある」という話を伺ったことがあります。
そうですね。保育園と幼稚園は、保育時間の差だけでなく福祉施設と教育施設の差が微妙にあるんです。
幼稚園は文部科学省管轄なので、「教育」という言葉もたくさん使いますから、「自分たちは教育している」という意識があるんですよね。実際にやっていることにはどんどん差が無くなっているんですが。
「保育」と「教育」は同じなので意識の差もなくしていきたいところですが、この差がなくなるにはまだ数年時間がかかると思います。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。