指導計画の源は子どもの提案
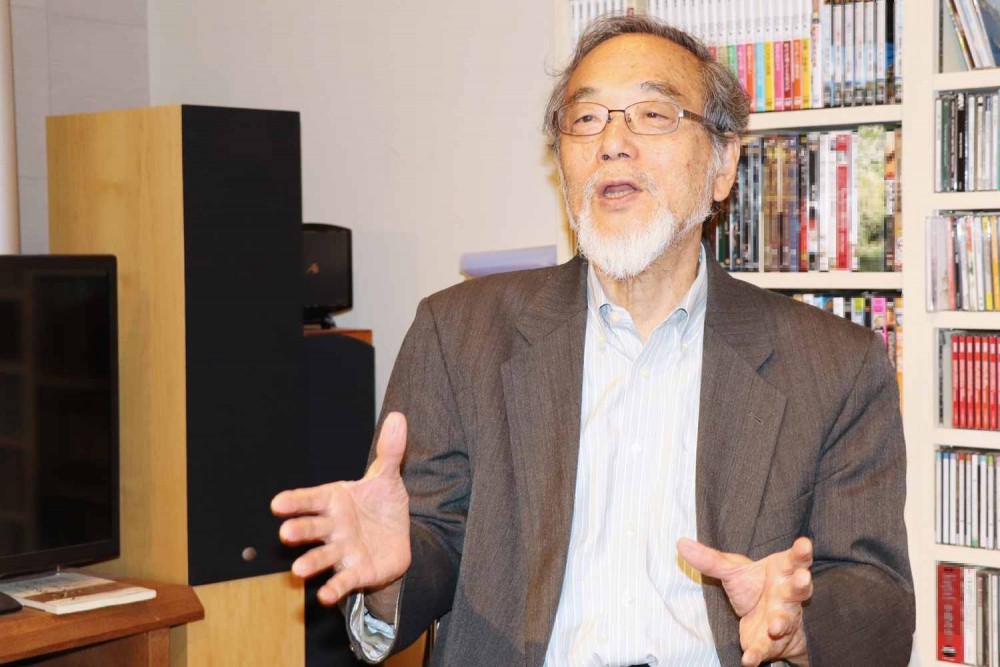
子どもが主体性を持って活動できるようにするために、保育者が子どもをよく見て環境を作ることが大切だと分かりました。しかし、現場に出るとどうしても指導計画に縛られてしまう保育者の方も少なくないのではないでしょうか。
指導計画がなにかというと、これもまた誤解されているんです。先生が頭の中で計画を立てたものを子どもにやらせるだけだったら、子どもは自分が本当にしたいことを見つけることができない。先生の頭の中にあるイメージを、子どもたちにさせることが指導計画というのは間違いだと思います。
そうではなく、「昨日まで子どもたちはこれをしていた」「それはこう発展するんでないかな」と考えたうえで、子どものそれまでの姿をきちっと評価して、次の活動を予見するんです。大まかな計画でいいんです。
立てた計画は、ほとんどが思い通りにはいかないですよ。その通りに行けばむしろラッキーです。指導計画は、子どもの育ちを評価してその可能性を勘案して作るものです。

私が現役のころは、よく先輩に「昨日と同じ活動をしないで」と言われていました。毎日活動を変えるべきなんでしょうか?
それを保育者が決めるのはおかしいですね。子どもが何かをおもしろがっているのなら、それを続けさせてあげたほうがいいですよ。大人が勝手にマンネリ化を恐れて毎日同じことをしない、というルールを作るのは間違いです。
もしマンネリ化しているように感じたら、保育者が子どもの興味を考えて何かを持ち込んでやったり、みんなで話し合ってみたり、側面援助をするんです。
マンネリ化しているかどうかは、子どもが決めること。楽しんでやっていたかもしれないのに、それを大人がて勝手にやめさせてしまうのはもったいないですよね。こだわってずっと続けている遊びがあると、考えたり工夫するチャンスが増えます。
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。



































