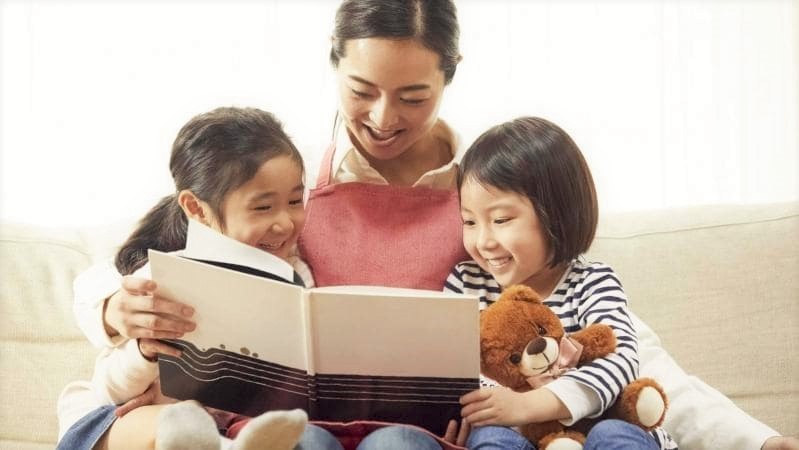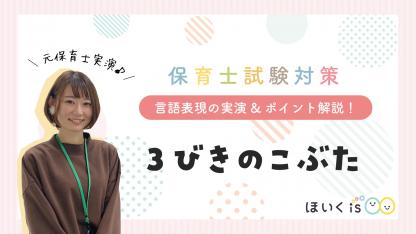2022年(令和4年)保育士試験の日程と概要が発表されていますが、受験予定の方はチェックしましたか。もちろん、皆さん「実技試験まで進む!」つもりでしっかりと対策しておきましょう。今回は、「言語に関する技術」から選択課題となっている4つの題材ごとのポイントをご紹介します。
>>試験対策関連一覧はこちら
「言語に関する技術」のポイント
保育士実技試験の科目のひとつである「言語に関する技術」。何もない状態で物語を3分以内で話す“素話(すばなし)”が課題となっています。まずは今年の題材や合格のポイントを確認しましょう。
2022年の課題は?
今回の「言語」の題材は、以下の4つとなりました。こちらは前年(2021年)から変わらず同じとなっています。
- ももたろう(日本の昔話)
- 3びきのこぶた(イギリスの昔話)
- 3びきのやぎのがらがらどん(ロシアの昔話)
- おおきなかぶ(ノルウェーの昔話)
どれもなじみのあるお話ですね。それぞれにあったポイントを押さえて練習をしておきましょう。
試験の条件・注意点
言語試験では、以下のような条件の指定や注意点が手引きに記載されています。こちらは
最低限の合格基準とも言えるので、しっかりと確認しておきましょう。
- 15人程度の子どもがいることを想定する
- 3歳の子どもがお話の世界に入り込めるように3分にまとめる
- 適切な身振り・手振りを加える
- 題名は開始合図のあと、一番最初に子どもに向けて言う
- 絵本や台本、人形などの道具の使用は禁止
- 3分間は退場できない
また、お話をする際の姿勢は、立つ・座るのどちらでもOK。会場では、子どもに見立てた椅子などが前方に用意されるので、そちらに向かって実演することになります。
題材ごとの実演ポイント
4つの題材ごとにポイントとなる部分を見ていきましょう。
ももたろう

ひとつめは、昔話として定番の「ももたろう」です。
★point
- 登場人物が多く、声の使い分けが重要
- 比較的長いお話なので、3分以内におさめられるように調整する
ももたろうには、「ももたろう」「おじいさん」「おばあさん」「さる」「きじ」「犬」「鬼」とたくさんの登場人物がいるため、
声の使い分けが重要になってきます。声色やスピードの変化、抑揚がないとダラダラとした印象になってしまうので要注意。よく知られていてメジャーなお話ですが、実は難易度が高い題材のひとつです。
▼こちらの動画の講座を参考にして練習してみてくださいね。
3びきのこぶた

こちらは比較的登場人物が少なく、繰り返しの内容が覚えやすいため、選択している方も多いかもしれませんね。
★point
- 場面による表情の変化が重要
- まとめすぎると早く終わってしまうので注意
「こぶたたちがオオカミに家を壊される場面」「オオカミがやっつけられる場面」は、“悲しい”、“怖い”などのマイナス感情の表現がポイントです。話し方だけではなく、
顔の表情にも変化をつけると良いですよ。また淡々と進めてしまうと
時間が余ってしまうため、読むスピードや間の取り方にも気をつけましょう。
▼こちらの動画の講座を参考にして練習してみてくださいね。
3びきのやぎのがらがらどん

お話の内容に着目すると、4つの課題の中でも難易度がかなり高い方かもしれませんね。
★point
- 声の使い分け難易度が高い
- 怖い雰囲気を出す工夫が必要
がらがらどんのお話は他の題材と違い、少し怖い雰囲気が出ていますよね。最後のオチも迫力があるため、その雰囲気を表現することが一番のポイントです。また、お話の中に「しゃがれた声」という表現があることから、
がらがらどんの声の出し方や話し方を工夫しましょう。
▼こちらの動画の講座を参考にして練習してみてくださいね。
おおきなかぶ

お話自体をすでに暗記しているという方も多く、比較的挑戦しやすい題材ではないでしょうか。
★point
- 登場人物が多いが会話が少なくナレーションベース
- 単調になりやすいので、声の抑揚で工夫をつける
登場人物は多いですが会話自体も少なく、声の使い分けが苦手だという方にはおすすめです。その分ナレーションでの表現で惹きつけなくてはいけないので、
声の抑揚や適度な身振り手振りがポイント。「うんとこしょ どっこいしょ」の部分は、引っ張る人が増えるごとに言い方を変えると場面の変化が分かりやすいですよ。
▼こちらの動画の講座を参考にして練習してみてくださいね。
題材ごとの魅力を表現しよう
「言語に関する技術」の受験時間はたった3分、あっという間です。その3分間はぜひ、“子どもたちに楽しくお話をすること”を意識してみましょう。何よりも自分自身が物語を楽しみながら受験できると、良い結果が付いてくると思います。頑張ってくださいね。
【関連記事】