11月は児童虐待防止推進月間

また毎年標語が決定され、意識付けのひとつとしてポスターや啓発活動で広く使用されています。
<過去の標語>
令和元年 189(いちはやく) ちいさな命に 待ったなし
平成30年度 未来へと 命を繋ぐ 189(いちはやく)
平成29年度 いちはやく 知らせる勇気 つなぐ声
参考:令和2年度「児童虐待防止推進月間」の標語を募集します 期間は4月24日(金)から6月17日(水)まで/厚生労働省
令和2年の虐待相談件数
近年、テレビで虐待についてのニュースを目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。痛ましい事件が日々起きている中、保育士という立場にある皆さんはしっかりと虐待についての意識を持つことが求められます。厚生労働省が発表した、令和2年(2020年)1月から6月までの児童相談所での虐待対応件数は、以下のようになっています。
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|
| 2020年 前年比 |
14,799 (+21%) |
15,004 (+11%) |
23,601 (+18%) |
| 2019年 | 12,249 | 13,517 | 20,074 |
| 年 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| 2020年 前年比 |
14,475 (+4%) |
13,462 (-4%) |
17,473 (+8%) |
| 2019年 | 13,879 | 14,001 | 16,146 |
前年と比べるとほぼ全ての月で増加しており、厚生労働省では新型コロナウイルスの流行により、自宅にいる時間が長くなったことの影響を懸念しているようです。
しかしこの数字はあくまで児童相談所(児相)に寄せられた件数。実際は見過ごされてしまっているものや、いまだに気付かれないケースも多くあるのではないかと考えられています。
参考:子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について/社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会
オレンジリボンと189

オレンジリボンとは
オレンジリボンとは、子ども虐待防止のシンボルマークとなっているリボンです。またオレンジリボン運動は、そのリボンを広めることで虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。オレンジリボン運動の始まりには、2004年(平成16年)に栃木県小山市で起きた幼い兄弟の虐待死事件があります。当時3歳と4歳だった兄弟が、父親の友人の男に暴行を受け、川に投げ込まれて命を奪われるという痛ましい事件が起きました。
これを受けて2005年(平成17年)、「カンガルーOYAMA」という団体によって運動が開始。現場にはお地蔵さんが設置されて、今も手を合わせる人や献花が絶えないそうです。
189とは
「189」は、児童相談所虐待対応ダイヤルの番号です。“いちはやく(1=いち、8=はや、9=く)”虐待を知らせるための専用ダイヤルとなっていて、匿名で通告や相談を行うことができます。- 189にかけると近くの児童相談所に繋がる
- 匿名性で、内容に関する秘密が守られる
- 通話料無料で24時間繋がる
実際に虐待でなくても、子育てに悩んでいて苦しい想いをしているお母さんやお父さん、保護者の方がいるのかもしれません。そのときは、通告をきっかけに適切な相談場所でのサポートが受けられます。
また保育園には、虐待の早期発見・通告の義務があります。とにかく迷ったらまず、189に電話をかけましょう。
参考:NPO法人児童虐待防止全国ネットワークホームページ
園で虐待に気付くために
虐待にいちはやく気付き、子どもの安全や健康を守るために保育士が日々気を付けておきたいことをご紹介します。子どもの状態に気を配る

着替えやおむつ替えのときには、身体を目視して行う。なんだか今日は元気がないと感じたら、話を聞いてみる。そんな小さな当たり前や行動が大切です。児童虐待には、身体的なもの以外にも、心理的虐待、性的虐待、ネグレクトなどがあります。目で見えるもの以外にも、言葉や態度などにも注意を払えるようにしましょう。
日々状況を確認することで、何か不自然な点があった場合に気付くきっかけにもなります。もちろんこれは、体調不良や病気などに気付くきっかけにもなるので、毎日の習慣としておきたいですね。
保護者に寄り添う
子どもの様子だけでなく、保護者の様子にも気を配りましょう。何か悩んでいたり、体調が優れない様子が見られたら一声かけるだけでも、相手の気持ちが楽になることもあります。寄り添いながら、一緒に子どもを見守っていけるようにしたいですね。園内での対応も気を付ける
近年では、園内で保育士から子どもに対する虐待が発生したケースもニュースになっています。毎日大切な子どもたちを預かる場所で、そのようなことがあってはいけません。他の先生の対応や声かけで気になることがあったときは、見て見ぬふりをせず誰かに相談しましょう。児童虐待をなくすために
児童虐待について一人ひとりが意識をすること、理解をすることで、子どもたちの未来が守られます。ぜひこの機会に、虐待について考えてみてください。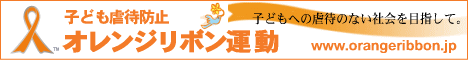
【児童虐待に関する記事はこちら】



































