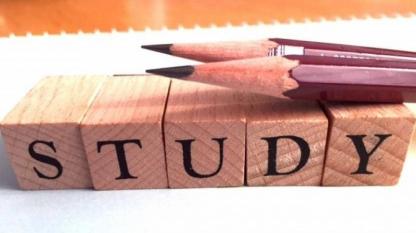子どものイヤイヤの原因を考えよう
1、2歳頃の子どもを担当すると「イヤイヤ期」の対応で悩んでしまう保育士さんも多いと思います。自我が芽生えて、自分の意思がはっきりし出すこの時期は、先生の話をなかなか聞いてくれない…なんてことが増えてきますよね。子どものイヤイヤ期には、どのような思いがあるのでしょうか? まずはその原因から考えてみましょう。自分でやりたい

言葉でうまく表現できない
まだ言葉がつたない時期で、自分の思いをうまく表現できないことから「イヤ」になってしまうことも。イヤイヤには先生も困ってしまうかもしれませんが、同じように子どもの方もどう伝えたら良いか分からず困っているのです。やりたくない
先生の言ったことをやりたくない、という思いから「イヤ」が出ることも多くあります。例えば、遊んでいるときに「ご飯を食べよう」「トイレに行こう」と言われても「もっと遊びたい」という思いが勝ってしまいますよね。「イヤ」という短い一言の中にも、「自分は〇〇がしたいからイヤだ」という思いが隠れています。保育士がするべき声かけ7つのポイント
どのようにイヤイヤ期の子どもたちに声かけをしていくと良いのでしょうか。心にとどめておきたいポイントをご紹介します。①子どもの話を聞く

②受け止め、代弁する
子どもの「イヤ」を叱るのではなく、受け止めましょう。「そうだよね、まだ遊びたかったよね」「イヤだったよね」と言葉で表現することで、気持ちを分かってもらえたと落ち着くこともあるでしょう。③見通しをつける
「お片付けが終わったら、ご飯を食べよう!今日は〇〇ちゃんの好きなお魚の日だね」と、先の見通しがつくような声かけをしてみましょう。次が分からないのに「ダメ」「やめよう」と言われても子どもたちも困ってしまいます。ワクワクするような声かけができるといいですね。④落ち着ける環境に行く

そんなときは「じゃあ一緒にコートをかけに行こうね。〇〇くんの場所はどこかな?」と言いながら一旦その場を離れ、園の外に出て外の空気を吸いに行っていました。このようなときには、安全確保や他の先生への共有も忘れずに。
⑤やりたくないことを遊びにする
子どもたちが「イヤ!」と思うことを、「あれ、なんか楽しそうだな」と思わせるのも、イヤイヤ期の子どもたちと向き合う大切なポイントです。例えば、片付け中に担任が「さぁ、◯◯くんが積み木を片付けています。おぉーっと、□□ちゃんも大きなカバンをしまっています、これはすごい!△△くんはできるでしょうか?」などと実況中継をします。
すると、「イヤ!」と言っていた子も実況してもらう遊びに興味が出て、動き出すことがあります。このやり方が必ず通用するわけではありませんが、「ただの片付け」が「おもしろい遊び」になるような工夫をしたいですね。
⑥「終わり」をわかりやすくする
「どこまでやったら終わりにするか」をわかりやすく伝えると、子どもも気持ちを切り替えやすくなります。今やっている遊びを「すぐにやめなさい」と言うのではなく、
- 10数えたら片付けよう
- 砂場の山が完成したら部屋に入ろう
- ままごとのご飯ができたらトイレに行こう
⑦子どもに選ばせる
「片付けだよ」「着替えるよ」などと保育士が頭ごなしに決めるのではなく、選択肢を示して子どもたちに選ばせるやり方も効果的です。- 積み木とブロック、どっちを片付けたい?
- ズボンとTシャツ、どっちから着替える?
- トイレに行くのは、今とちょっと遊んでからとどっちがいい?
「自分で選んだ」という気持ちも子どもにありますし、「大好きな先生と約束をしたこと」も次の行動につながるきっかけになります。とはいえ一筋縄でいかないのがイヤイヤ期ですが、日々のこうした積み重ねが子どもの成長につながります。
子どもの気持ちに寄り添った声かけを
イヤイヤ期の対応にはきちんとした正解がないので、悩むことも多くあると思います。しかし、子どもには子どもなりの気持ちが隠れています。その思いを感じ取り、寄り添った声かけができるといいですね。その子に合った声かけの仕方を探してみてくださいね。【関連記事】