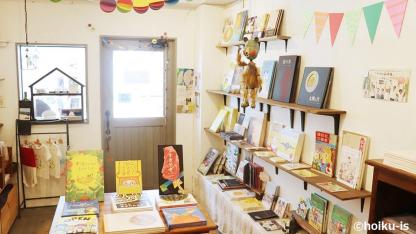ケンカのとき

お互いの言い分を聞く
まずは、「どうしたの?」とお互いの言い分や気持ちを聞きましょう。ケンカの背景には、子どもたちなりの言い分があり、それぞれの気持ちが隠れています。それを聞き出すのが保育者の役目。決して、状況だけで判断して「おもちゃを取った〇〇くんが悪い」などと決めてしまわないようにすることが重要です。子どもの気持ちに共感する
話を聞いてお互いの気持ちがわかったら、共感する言葉をかけましょう。「〇〇くんは、こうしたかったんだね」「△△くんは、こう言ってほしかったんだね」と、一人ひとりに語り掛けることで、子どもたちは「気持ちをわかってもらえた」と落ち着くことができます。解決方法は子どもたちに
最後は「どうすればいいかな?」と、子どもたちに解決方法を問いかけてみましょう。ここでも保育者が「じゃあこうしようね」と答えを出さないことが大切。子どもたちの発言を聞きながら、自分たちで主体的に解決できるようお手伝いをしましょう。ご飯のとき

バタバタしがちなご飯の時間。特に乳児クラスでは大変ですよね。ご飯が食べ進まない、遊んでしまう、そんなときの声かけを見ていきましょう。
食べ物への興味を引き出す
まずは食べ物への興味を引き出すような声かけをしてみましょう。「食べたらどんな音がするかな?」「この間絵本で見た野菜だね!」など、楽しみながら食べ進めていける工夫をしたいですね。食べることを強要するのではなく、自主的に食べられるような声かけが大切です。「一口」作戦
どうしても苦手なものは、無理をせず「一口」頑張ってもらうのもいいですね。「一口だけ食べてみよう!」と優しく声をかけてみましょう。食べられたら褒めることも忘れずに。少しずつ食べられる量が増えていくといいですね。中断するのも選択肢
スプーンを投げたり、お皿をひっくり返したり、1~2歳頃の時期には遊び食べも見られますよね。これは成長過程で当たり前のことですが、何度も繰り返すときには、スプーンを片付けたり、食事を中断するのも選択肢のひとつ。次第に「遊んでいるとなくなってしまう」ということを理解してくれるようになっていきます。トイレや着替えのとき

遊びを取り入れる
「みんなで電車になってトイレまで行ってみよう!」「〇〇くんの足はどこから出てくるかな~?」と、楽しみながらトイレや着替えを促してみましょう。「トイレに行くよ!」「早く着て!」と強制するのはNG。遊びを交えながら、楽しく生活習慣を身に着けていけるといいですね。「やって」には手助けを
中には自分でできるのに「ボタンをとめて」「おむつ履かせて」などと言われることもあるでしょう。そんなときは、「先生はここまでやるから、その後は〇〇ちゃんやってみよう!」と手助けをしてみましょう。お願いする理由は子どもによってさまざま。受け入れることも大切です。子どもの自主性を大切に
さまざまな場面で必要となる声かけ。それぞれの場面に合った言葉を選んでいくことが大切です。子どもの気持ちを汲み取った対応を心掛けて、自主性を育てていけるといいですね。【関連記事】