トイトレはいつから始める?

とは言え、一人ひとりでタイミングは異なるということを理解し、無理せず個々に合った時期を見定めて始めるようにしましょう。
トイトレの準備をしよう
トイレトレーニングを始める際には、事前にしっかり準備をしておくことが必要です。ポイントごとにご紹介します。トイレ環境を確認する

- ペーパーが取りやすい距離かどうか
- 手洗い場までの導線は行きやすく安全か
- パンツやズボンを履く場所はあるか
トイレを楽しい場所にする
子どもたちの中には、トイレという場所自体が苦手な子もいます。まずは「トイレは怖い場所でない」ということを知ってもらうためにも、明るい雰囲気を作りましょう。例えば、トイレの中を壁面製作で飾るなど、行くのが楽しくなる工夫をしてみてくださいね。危険なものはしまう
子どもたちが触ると危険なものは、しっかりとしまっておくか手の届かない場所に置くようにしましょう。特に洗剤などは液体や口に入るサイズの固形のものが多いので、誤飲につながる危険性があります。使った後は出しっぱなしにせず、元あった場所にしまうなど管理を徹底することが大切です。保護者に共有をする
トイレトレーニングを始めるときには、必ず保護者への共有を忘れずに。トイトレは保育士だけでなく、保護者の協力や理解もとても重要です。開始のタイミングについても、家での様子と照らし合わせながら相談していきましょう。トイトレの進め方
準備ができたら、子どもたち個々のペースに合わせて実際のトイレトレーニングに入りましょう。ここでは、大まかなステップ別に進め方をご紹介します。①トイレについて知ってもらう
まずは、トイレに興味を持ってもらうことから始めましょう。普段おむつを履いている子どもたちにとっては、あまり目にしたことがない「トイレで排せつをする」ことを想像しにくいという面があります。例えば絵本を用いた導入で、トイレの使い方や、どんなところなのかを知ってもらいましょう。こちらの記事で、おすすめの絵本を紹介しているので参考にしてみてください。
②トイレに誘う

また定期的にトイレに行っておむつを確認するだけでも、子どものおしっこの間隔を掴むことができます。「この子は2時間おしっこの間隔があいている」と分かれば、トイトレを進める参考になりますね。
③トイレに座る習慣をつける
嫌がる様子がなければ、実際に子どもを便座に座らせてみましょう。座る習慣ができてくれば、トイレでおしっこが成功する機会も増えてきます。場合によっては、座ってもすぐに「出ない」と言われたり、逆にいつまでも座っていたがったりするということがあるかもしれません。そんなときは、「10秒数えてみよう」と一緒に数を数えてみるのがおすすめ。それでも出なければ、無理せず切り上げましょう。
④トレーニングパンツを履く
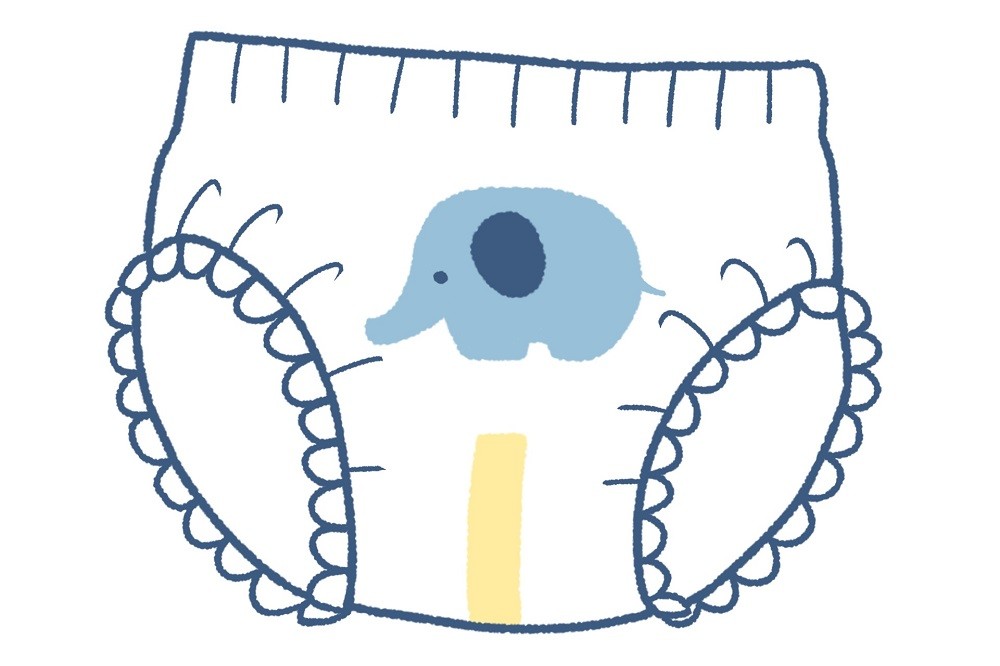
おむつよりも濡れた感覚が分かりやすいため、失敗も経験しながら少しずつおしっこが出る前にトイレに行きたがるようになります。ただし、子どもが嫌がるときは無理に履かせず、少しずつ慣れることができるようにしていきましょう。
便器タイプ別の対応

また男子用の小便器の場合、ただ立つだけではおしっこが便器から漏れてしまいます。子ども用のものは手すりがついているのが一般的なので、子どもに手すりを掴んでもらい、保育士が優しく腰の部分を前に押してあげましょう。少しずつその姿勢の感覚が身についていけば、ひとりでも出来るようになっていきます。
また便器の中に目印のマークやシールを付け、「あのマークに向かっておしっこを出すよ」と教えると分かりやすいですよ。
根気よく進めよう
トイレトレーニングは、子どもによって進み具合の差が大きいものです。焦ったり早く終わらせようと気負ったりせず、個々のペースに合わせて根気よく進めていきましょう。【関連記事】





































