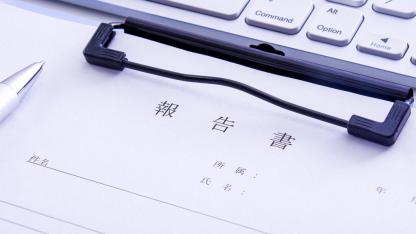春・夏に流行しやすい感染症
一見すると、風邪や熱の諸症状にも見えるものが多く、判断するのは難しいですが、一つひとつ特長を押さえておきましょう。
アデノウイルス感染症
アデノウイルスによって、さまざまな病気が引き起こされます。多くは飛沫感染や接触感染をします。その中でも保育園や幼稚園でよくみられるのが「咽頭結膜熱(プール熱)」「胃腸炎」です。
●咽頭結膜熱(プール熱)
アデノウイルスの感染により、結膜炎などの症状を引き起こします。
- 1日の中で高熱と微熱を行き来する
- 頭痛
- 腹痛、下痢
- 目の充血
- 目やに
便から感染することもあるので、おむつ替えのときには注意が必要です。
●胃腸炎
乳幼児期に多く見られ、保育園でも流行りやすい病気です。
- 腹痛
- 下痢
- 嘔吐
お腹の不調が見られますが、発熱は軽いことが多いとされています。どちらも手洗いなどをしっかり行い、予防しましょう。
参考:アデノウイルス解説ページ‐アデノウイルスの種類と病気/NIID国立感染症研究所
ヘルパンギーナ

1歳~4歳ごろまでにかかりやすいと言われ、夏風邪の代表とされています。咳での飛沫感染をします。
- 38℃~40度の発熱
- のどの痛み
- 食欲不振
一般的には2日~3日程で回復していきます。発症後からしばらくは便からウイルスが排泄されるため、おむつ替えの後にはしっかり手を洗うことが、感染拡大の防止には必要になってきます。
参考:ヘルパンギーナ/厚生労働省HP
手足口病
主に夏に流行し、5歳以下の乳幼児に多くみられる病気です。名前の通り、口の中や手足に水疱性の発疹が出るのが特徴です。
- 口の中、手足に発疹
- 発熱
感染経路として接触感染もあるため、子ども同士のかかわりが多い保育園や幼稚園では集団感染しやすく、注意が必要です。着替えやおむつ替えなどの際には子どもの様子をしっかり確認しましょう。
参考:手足口病に関するQ&A/厚生労働省
麻しん(ましん/はしか)
麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症です。
- 高熱
- 咳
- 鼻水
- 発疹
飛沫感染、空気感染、接触感染など感染経路が広く、感染力が強いと言われています。肺炎や中耳炎を合併しやすいので、注意が必要です。
参考:麻しんについて/厚生労働省
風しん
風しんウイルスによって引き起こされる発疹性感染症です。
- 発熱
- 発疹
妊娠20週頃までの妊婦が風しんに感染すると、先天性風しん症候群の子どもが生まれる可能性が高くなると言われています。子ども同士の感染だけでなく、妊娠中の保育士さんや保護者への感染にも特に注意が必要です。
参考:風しんについて/厚生労働省
おたふくかぜ

流行性耳下腺炎とも呼ばれます。冬にも流行が見られ、発症は3~6歳頃に多いと言われています。
- 両頬が腫れる
- 耳下腺の腫れ
妊婦が感染すると自然流産することもあるため、風しんと同様妊娠中の方は特に感染に注意が必要です。
参考:流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)/厚生労働省
子どもの様子をしっかりチェック
保育園や幼稚園ではさまざまな感染症が流行し、子どもだけでなく保育士さん自身や保護者にも感染することがあります。おむつ替えや着替えなどの際に子どもの様子を確認するのはもちろん、1年を通して手洗いうがいを心掛けるなど、日頃からの対策が感染拡大の予防のために重要になります。
【関連記事】