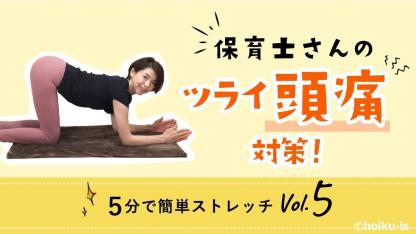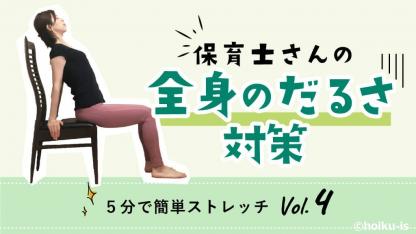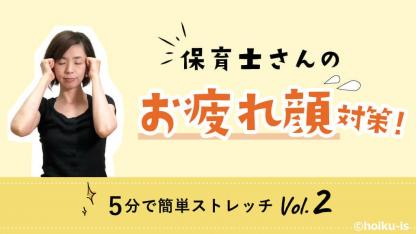そもそも首&肩こりの原因って?
保育者の皆さん、毎日お疲れさまです! ヨガインストラクターのごとうりえです。気温が変わりやすい日々が続いていますが、体調を崩されていないでしょうか?
季節の変わり目はできるだけ「早寝早起き」を意識して、自律神経を整え免疫力を高めてくださいね!
今回のテーマは「肩こり&首こり」です。慢性的に悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

子どもを抱っこしたり、重いものを運んだり…保育士さんのお仕事は常に、肩や首に負担がかかっています。
書類を作ったり製作をしたりする際に、ずっと同じ姿勢が続くのも痛みの一因です。
首&肩こりの原因になる姿勢
どんな姿勢が原因になりやすいかというと、前かがみの姿勢。これが続くと筋肉が緊張して血行が悪くなります。ポイントは背中側の肩甲骨と、頭と首の骨をつないでいる筋肉。この2か所をしっかり動かすことを意識することが大切です。
胸の前も凝り固まりやすいので、今回のストレッチでは鎖骨が左右に広がるイメージを持ち、深い呼吸とともにほぐしていきましょう。
それでは!5分で簡単にできる 「肩こり解消ストレッチ」を3つご紹介していきます。
【動画で簡単】肩こり解消ストレッチ
|
<どこでする?> 座った状態でポーズをとっていきます。椅子に座ったままでもOKです! <準備するもの> 床に座る場合はお尻の下にヨガマットやブランケットを敷いて、腰が丸まらないようにしましょう。 |
その1「肘曲げサイドストレッチ」


- 楽な座法で座り、両手を肩の下に置きます。
- すう息で片手を上げ、はく息で側屈します。
- 上の手を後頭部に当て、すう息で上の肘と胸を天井の方に向け、吐く息で上の肘と膝を近づけ背中を丸く、目線は床に向けます。これを3回繰り返します。
- すう息で上半身を起こし、はく呼吸で手を解放します。
|
【ポイント】 ●下の手で床を押し、上の肘は天井に向けるようにして胸に呼吸を入れていきます。 ●上の肘と同じ側のお尻でも床を押し、体側を伸ばします。 ●肘と膝を近づけ背中を丸め首や肩の力を抜きましょう。 |
その2「胸と背中のストレッチ」


- 両手を体の前で組みます。
- すう息で背骨を伸ばし、はく息で手の甲を前に押し出し背中を丸め、目線はおへそをのぞき込みます。
- すう息で両手をお尻の後ろで組み肩甲骨を寄せ、胸は前に押し出します。目線は斜め上に向けます。
背中の後ろにしわができるように肩甲骨を寄せたり、広げたりと大きく動かしていきます。
|
【ポイント】 ●手の甲を前に押し出した時は、背中を丸めて肩甲骨を広げます。 ●後ろに組んだ手は斜め下に押し下げ、胸の前を伸ばします。 ●首や肩の力を抜いてリラックスしながら行います。 |
その3「首伸ばしストレッチ」


- 両手を体の後ろで組みます。
- 組んだ手をわき腹に添えます。すう息で背骨を伸ばし、はく息で頭を組んだ手と同じ側に傾けます。20秒呼吸を繰り返し、首から肩にかけての伸びを感じます。
- はく息で手の位置は変えないまま、さらに頭を斜め下に傾けます。15秒呼吸を繰り返し、首の斜め後ろの伸びを感じます。
- はく息で両手を解放させ頭を下に転がし、すう息で顔を正面に戻します。反対側も同じようにしていきましょう。
手を組むのが難しい方は、両手は肩の下に置いて、首だけ動かすのでOKです!

|
【ポイント】 ・肩の高さを平行に保ちましょう。 ・伸びている所に意識を向け呼吸を届けます。 |
【時間がない時は】夜寝る前に「全身脱力ポーズ」
今回ご紹介したストレッチで肩周り、首周りをほぐしていきました。忙しく時間がない時は、夜寝る前に体の緊張を解く、簡単なストレッチを取り入れてみてください。①全身リラックス、ゴロンゴロン首ほぐし
ベットの上で仰向けになって、全身の力をゆるめ脱力します。両手と両足は楽な位置でOK。
頭を左右にゴロンゴロンと動かし、首や肩周りの緊張を解きます。
呼吸が深まるのでリラックス効果が高まり、心地よい睡眠を導きます。毎日繰り返すことで慢性的な疲労を改善しましょう!
②仰向けのまま「バナナのポーズ」

- 仰向けのまま、足幅を骨盤幅に広げます。
- 下の足首の上に反対足の足首を重ねます。
- 上の足と同じ側の手首を反対の手で掴み頭の先に伸ばします。
副交感神経を高めて身体をリラックスモードへ。肝臓を刺激する効果もあるので良質な血液が全身の細胞をめぐり、様々な体調の改善につながっていきます。
日常生活で気を付けたいポイント
これから冬にかけては、寒さで筋肉がこわばりやすくなります。肩甲骨周りから肩の血行不良が起こりやすくなるので、肩こりが悪化することも。またパソコン作業やスマートフォンを長時間見ている時の姿勢も、ちょっと注意!
前傾姿勢になったり、目の使い過ぎなどにより、頭の重さを支える首の筋肉も凝り固まってしまうので、大きな負担になります。
是非、隙間時間にストレッチを取り入れて、意識的に体を動かしてみてくださいね。明日からも無理せず、体を大切に過ごしていきましょう♪
次回は、ツライ生理痛を緩らげるストレッチをご紹介します。是非お楽しみに!
(2021年11月15日に配信予定です)
▼ほかおすすめの記事はこちら